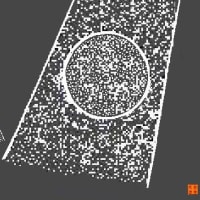夏の怪奇小説特集 水本爽涼
第五話 スバラシイ(1)
朝早く、会社へ出勤すると、開口一番、部長から呼び出されました。そして、「君ねぇ、来年からさ、浜松の出張所の方へ行って貰おうと思ってんだが…」と、言い渡されました。
「浜松? …」と、一瞬、私の脳裏は真っ白になりました。
実を云いますと、私の会社というのは、東京に本社を持つ大手企業系列の関連子会社なのですが、最近は企業競合の荒波に押され、事あるごとに業績改善、業績改善と社内で叫ばれている時期でもありました。
私は企画部総務課の課長代理でして、と云いましても課員数が十数人なのですが、代わり映えしない日々を、鳴かず飛ばず勤めておりました。
そう、今振り返れば、そうした日々は感動がないと云いますか何と申しますか、胸に突き上げるような喜びがない、いわば、働き甲斐のある職場ではなかったのです。そして、世渡りが下手、また運もなかった…いえ、実力がなかった所為(せい)もあったのでしょう。十数年の間に、出世していく同僚社員を仰ぎながら、本社からリストラでこの子会社へ派遣されたという粗忽者なのです。
その無感動の一場面をお見せしましょう。
お茶を淹れて盆の上へ置き、それぞれのデスクにはこんでいる女事務員の姿が見えます。彼女の姿は、机上の書類に目を離し、顔を上へ向けた刹那、私の視線に飛び込んだのです。
机に湯呑みを置きながら、なにやら話しているのが小さく聞こえてきます。
「ホントはねぇ、お茶汲み、なんかしなくってもいいんだけどさぁ…、なんか習慣になっちゃってるのよねぇ」
話し相手の男性社員は、たしか同期入社組だったと思うのですが、笑って頷(うなず)いています。
私はというと、机上の書類に目を通していたとはいえ、実は眠気でウトウトしていたのが事実でして、事務員の話す姿が見えたのは、まどろみから目覚めた、すぐ後だったのです。
結局のところ、私の会社での立場といいますのは、その程度のものでして、大した役職を与えられている訳でもなく、課長代理という名ばかりの肩書きを与えられ、かといって、疎んじられているというのでもないのですが、昼行灯の渾名(あだな)をつけられておる、いてもいなくても影響力のない存在でした。
続












![連載小説 幽霊パッション 第三章 (第百五[最終]回)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/19/cf/a4d652a78f65b5a64a7098195c68c8c7.jpg)