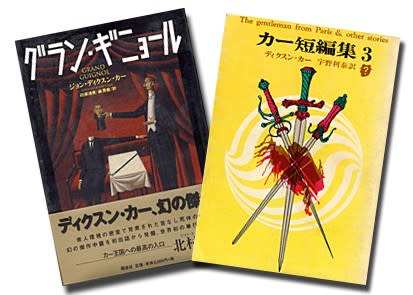
■中編『奇蹟を解く男』(創元推理文庫『カー短編集3巻』所収)だけど、
『評伝ジョン・ディクソン・カー 奇蹟を解く男』によると、
1955年に書き上げて、1956年1月から3月まで『House Wife』という雑誌に連載された、とある。(同書P405)
★題が一緒なんで、ややこしいけれど、H・M卿最後の中編のことですね。
■女性雑誌連載なので、ヒロインが窮地に立たされるストーリーは変わらない。カーは長編にする気があったようだ、としてある。
★『騎士の盃』のあとに書かれたとは思えない、40年代作品を彷彿とさせる面白さがあります。
■『奇蹟を解く男』が雑誌連載3回分ということは、前述の雑誌連載表の連載回数(3回から4、5回)とほぼ同じなので、
各作品の連載時の長さも『奇蹟を解く男』程度だったと分かる。ここから、アブリッジ版は相当に短い、ということだね。
【『奇蹟を解く男』は一万五千語、『夜歩く』の原型中編『グランギニョール』は二万五千語、『夜歩く』は七万語。】
★長めの短編、ぐらいの感じですもんね。もし先に完全原稿があって、それを要約するとしたら約4分の1ぐらいに削らないといけない。
■クイーンの場合は、完全版を書いたリーが、もういちど自分の書いた文章を削っていくという、大変な作業をしていたらしい。
★カーがそんな面倒なことをする人とは思えませんねえ。
■そこなんだよ。すると二つの可能性が考えられる。
一つは、雑誌連載用に短い作品を書いておき、さらに単行本用に書き足していた、というカーが原稿を二つ書いておいた可能性。
もう一つは単行本用原稿を雑誌編集者が要約していた可能性。
★要約版と完全版を書くとしても、結局二回書くことになりますよね。
横溝正史が短編や中編を長編へ書き直していたことは知られていますが、カーがそんなマメなことをしますかねえ?
雑誌編集者が要約する場合は、伏線やストーリー展開に矛盾が生じないように削ることが可能なのか疑問です。
■前述の雑誌連載作品リストを見てみると、いわゆる「2番目の事件」とか「無駄な展開」が散見されるんだ。
たとえば『皇帝の~』の終わりのほうにある妹襲撃(のような)事件、『テニスコートの謎』の2番目の事件とか。
たぶん枚数(英語圏なので語数)をかせぐために挿入されたエピソードだと邪推したい。
あるいは、編集者向けに「あきらかにここはカットできる場所」と分かるように書いたのか。
★二度書き説支持ですか。『第三の銃弾』の簡約版がEQMMに載ったときは、ダネイが原稿を刈りこんだそうですよ。
自分でやらずにダネイにむかって「君も冗長だと思うだろう?」とか言ったそうです。(『評伝 ジョン・ディクスン・カー 奇蹟を解く男』P240)
■ダネイは他人の原稿を直すのが好きそうだから、よかったんじゃないか。
ところでカーの作風が40年代に入って変わった、という認識はわりと広まったとおもうんだが、
「なぜ変わったのか」という理由まではあまり見ない気がする。
★そうですか。
■雑誌用にアブリッジ版を書くため、という理由を当てはめると、説明できるような気がするんだ。
アブリッジ版は短いので、初期作品のように多数の登場人物を出すわけにいかない。
そして女性読者を想定して、事件の舞台は家庭または狭い人間関係の中で、男女間あるいは夫婦間の愛憎をテーマにしている。
★なるほど。
■つまり40年代の傑作、佳作群は、雑誌掲載を前提にして書かれた作品ではないか。
★もしそれが本当ならば、アブリッジ版も読んでみたいですね。新訳プロジェクトもいいけれど。
■あくまで希望的観測だけど、中編版が存在するなら一冊にまとめられないだろうか。
一般的にカーは長編作家と思われているみたいだけど、面白く書ける長さは中編だった、という売り言葉をつけて『カー原型中編集』とか。
★デビュー作の『夜歩く』はオリジナルが中編でしたものね。
ハヤカワさん、創元さん、原書房さん、扶桑社さん、どこでもいいけどご一考願えませんか。
※あくまで希望的な想像でしかなく、『評伝』を読むかぎりでは、同じ原稿を二度書くなどという面倒なことをする人とは思えません。
雑誌連載は編集者が要約した、と考えるほうが妥当かと思います。
雑誌連載
1937年『四つの凶器』 Woman's journal 37年12月~38年4月
1937年『孔雀の羽根』 The Passing Show 37年11月~38年1月
1938年『曲がった蝶番』 The Passing Show 38年10月~39年1月
1938年『五つの箱の死』 Home journal 38年8月~9月
1939年『緑のカプセルの謎』 Woman's journal 39年5月~7月
1939年『テニスコートの謎』 Modern Woman 39年11月~40年3月
1940年『かくして殺人へ』 Woman's journal 40年6月~9月
1941年『殺人者と恐喝者』 Woman's journal 41年5月~8月
1942年『皇帝の嗅ぎ煙草入れ』 Woman's journal 43年2月~5月
1944年『爬虫類館の殺人』 Woman's journal 43年12月~44年2月
1946年『別れた妻たち』 Woman's journal 47年4月~6月
1947年『眠れるスフィンクス』 Woman's Own 47年5月~7月
1950年『ニューゲートの花嫁』 Woman's journal 50年6月~9月
1952年『赤い鎧戸のかげで』 Argosy 52年1月~4月
1955年『喉切り隊長』 Argosy 55年5月~8月
1956年『奇蹟を解く男』 House Wife 56年1月~3月
『評伝ジョン・ディクソン・カー 奇蹟を解く男』によると、
1955年に書き上げて、1956年1月から3月まで『House Wife』という雑誌に連載された、とある。(同書P405)
★題が一緒なんで、ややこしいけれど、H・M卿最後の中編のことですね。
■女性雑誌連載なので、ヒロインが窮地に立たされるストーリーは変わらない。カーは長編にする気があったようだ、としてある。
★『騎士の盃』のあとに書かれたとは思えない、40年代作品を彷彿とさせる面白さがあります。
■『奇蹟を解く男』が雑誌連載3回分ということは、前述の雑誌連載表の連載回数(3回から4、5回)とほぼ同じなので、
各作品の連載時の長さも『奇蹟を解く男』程度だったと分かる。ここから、アブリッジ版は相当に短い、ということだね。
【『奇蹟を解く男』は一万五千語、『夜歩く』の原型中編『グランギニョール』は二万五千語、『夜歩く』は七万語。】
★長めの短編、ぐらいの感じですもんね。もし先に完全原稿があって、それを要約するとしたら約4分の1ぐらいに削らないといけない。
■クイーンの場合は、完全版を書いたリーが、もういちど自分の書いた文章を削っていくという、大変な作業をしていたらしい。
★カーがそんな面倒なことをする人とは思えませんねえ。
■そこなんだよ。すると二つの可能性が考えられる。
一つは、雑誌連載用に短い作品を書いておき、さらに単行本用に書き足していた、というカーが原稿を二つ書いておいた可能性。
もう一つは単行本用原稿を雑誌編集者が要約していた可能性。
★要約版と完全版を書くとしても、結局二回書くことになりますよね。
横溝正史が短編や中編を長編へ書き直していたことは知られていますが、カーがそんなマメなことをしますかねえ?
雑誌編集者が要約する場合は、伏線やストーリー展開に矛盾が生じないように削ることが可能なのか疑問です。
■前述の雑誌連載作品リストを見てみると、いわゆる「2番目の事件」とか「無駄な展開」が散見されるんだ。
たとえば『皇帝の~』の終わりのほうにある妹襲撃(のような)事件、『テニスコートの謎』の2番目の事件とか。
たぶん枚数(英語圏なので語数)をかせぐために挿入されたエピソードだと邪推したい。
あるいは、編集者向けに「あきらかにここはカットできる場所」と分かるように書いたのか。
★二度書き説支持ですか。『第三の銃弾』の簡約版がEQMMに載ったときは、ダネイが原稿を刈りこんだそうですよ。
自分でやらずにダネイにむかって「君も冗長だと思うだろう?」とか言ったそうです。(『評伝 ジョン・ディクスン・カー 奇蹟を解く男』P240)
■ダネイは他人の原稿を直すのが好きそうだから、よかったんじゃないか。
ところでカーの作風が40年代に入って変わった、という認識はわりと広まったとおもうんだが、
「なぜ変わったのか」という理由まではあまり見ない気がする。
★そうですか。
■雑誌用にアブリッジ版を書くため、という理由を当てはめると、説明できるような気がするんだ。
アブリッジ版は短いので、初期作品のように多数の登場人物を出すわけにいかない。
そして女性読者を想定して、事件の舞台は家庭または狭い人間関係の中で、男女間あるいは夫婦間の愛憎をテーマにしている。
★なるほど。
■つまり40年代の傑作、佳作群は、雑誌掲載を前提にして書かれた作品ではないか。
★もしそれが本当ならば、アブリッジ版も読んでみたいですね。新訳プロジェクトもいいけれど。
■あくまで希望的観測だけど、中編版が存在するなら一冊にまとめられないだろうか。
一般的にカーは長編作家と思われているみたいだけど、面白く書ける長さは中編だった、という売り言葉をつけて『カー原型中編集』とか。
★デビュー作の『夜歩く』はオリジナルが中編でしたものね。
ハヤカワさん、創元さん、原書房さん、扶桑社さん、どこでもいいけどご一考願えませんか。
※あくまで希望的な想像でしかなく、『評伝』を読むかぎりでは、同じ原稿を二度書くなどという面倒なことをする人とは思えません。
雑誌連載は編集者が要約した、と考えるほうが妥当かと思います。
雑誌連載
1937年『四つの凶器』 Woman's journal 37年12月~38年4月
1937年『孔雀の羽根』 The Passing Show 37年11月~38年1月
1938年『曲がった蝶番』 The Passing Show 38年10月~39年1月
1938年『五つの箱の死』 Home journal 38年8月~9月
1939年『緑のカプセルの謎』 Woman's journal 39年5月~7月
1939年『テニスコートの謎』 Modern Woman 39年11月~40年3月
1940年『かくして殺人へ』 Woman's journal 40年6月~9月
1941年『殺人者と恐喝者』 Woman's journal 41年5月~8月
1942年『皇帝の嗅ぎ煙草入れ』 Woman's journal 43年2月~5月
1944年『爬虫類館の殺人』 Woman's journal 43年12月~44年2月
1946年『別れた妻たち』 Woman's journal 47年4月~6月
1947年『眠れるスフィンクス』 Woman's Own 47年5月~7月
1950年『ニューゲートの花嫁』 Woman's journal 50年6月~9月
1952年『赤い鎧戸のかげで』 Argosy 52年1月~4月
1955年『喉切り隊長』 Argosy 55年5月~8月
1956年『奇蹟を解く男』 House Wife 56年1月~3月















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます