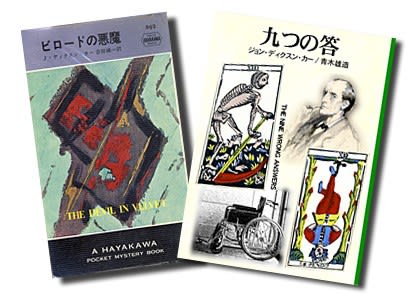
★『九つの答』(1952)はこんなに束が厚いのに内容は残念ながら……。
■その前年に出た『ビロードの悪魔』(1951)は同じくらいの束の厚さなのに、
『ビロード~』のほうが面白いんだよなあ。
それに『九つの答』は評論家や版元に不評だったそうだ。(『評伝 ジョン・ディクスン・カー 奇蹟を解く男』P388)
★読者にも、でしょうね。
■じつはこの2作には似ている点もある。まず主人公が入れ替わりだということ。
★カーの好きな『ゼンダ城』ギャンビットですね。
■物語のスタート早々に「犯人」が話の主軸から外れること。
★それは、カーがよく使う手法です。『毒のたわむれ』『皇帝の~』とか。
■似た設定であり、束の厚さからは両作ともに力を入れていたことが分かる反面、
おもしろさが月とスッポンなのは何故だろうね。
イギリスの冒険小説家の長編デビュー作
エリック・アンブラー「暗い国境」(1936年)
ハモンド・イネス「The Doppelganger」 (1937年)
イアン・フレミング「カジノ・ロワイヤル」(1953年)
アリステア・マクリーン「女王陛下のユリシーズ号」(1955年)
ジャック・ヒギンズ「Sad Wind from the Sea」(1959年)
ギャビン・ライアル「ちがった空」(1961年)
ジョン・ル・カレ「死者にかかってきた電話」(1961年)
デズモンド・バグリィ「ゴールデン・キール」(1963年)
※『ビロードの悪魔』のおもしろさは、
1にタイムリミットの設定(日記に記された殺人を回避できるか)、
2に歴史改変の可否(最後に主人公が選ぶ未来はどっち)、
3にチームプレイ(犬も含むw)という点ではないでしょうか。
ミステリとしての「意外な犯人」は、カーとしては「してやったり」だったのかもしれませんが、
さほどおもしろさに貢献しているとは感じませんが、どうでしたか。
版元は「ミステリ」として売ろうとしたのでしょうが、面白さは「SF」の範疇だったのでは。
似たようなSF『闇よ落ちるなかれ』がスプレイグ・ディ・キャンプの代表作ならば、
『ビロードの悪魔』は「SF」作家カーの代表作といえるのでは。
『九つの答』は結局ハヤカワミステリ文庫に入らなかったので、冗談で作ってみました。
■その前年に出た『ビロードの悪魔』(1951)は同じくらいの束の厚さなのに、
『ビロード~』のほうが面白いんだよなあ。
それに『九つの答』は評論家や版元に不評だったそうだ。(『評伝 ジョン・ディクスン・カー 奇蹟を解く男』P388)
★読者にも、でしょうね。
■じつはこの2作には似ている点もある。まず主人公が入れ替わりだということ。
★カーの好きな『ゼンダ城』ギャンビットですね。
■物語のスタート早々に「犯人」が話の主軸から外れること。
★それは、カーがよく使う手法です。『毒のたわむれ』『皇帝の~』とか。
■似た設定であり、束の厚さからは両作ともに力を入れていたことが分かる反面、
おもしろさが月とスッポンなのは何故だろうね。
イギリスの冒険小説家の長編デビュー作
エリック・アンブラー「暗い国境」(1936年)
ハモンド・イネス「The Doppelganger」 (1937年)
イアン・フレミング「カジノ・ロワイヤル」(1953年)
アリステア・マクリーン「女王陛下のユリシーズ号」(1955年)
ジャック・ヒギンズ「Sad Wind from the Sea」(1959年)
ギャビン・ライアル「ちがった空」(1961年)
ジョン・ル・カレ「死者にかかってきた電話」(1961年)
デズモンド・バグリィ「ゴールデン・キール」(1963年)
※『ビロードの悪魔』のおもしろさは、
1にタイムリミットの設定(日記に記された殺人を回避できるか)、
2に歴史改変の可否(最後に主人公が選ぶ未来はどっち)、
3にチームプレイ(犬も含むw)という点ではないでしょうか。
ミステリとしての「意外な犯人」は、カーとしては「してやったり」だったのかもしれませんが、
さほどおもしろさに貢献しているとは感じませんが、どうでしたか。
版元は「ミステリ」として売ろうとしたのでしょうが、面白さは「SF」の範疇だったのでは。
似たようなSF『闇よ落ちるなかれ』がスプレイグ・ディ・キャンプの代表作ならば、
『ビロードの悪魔』は「SF」作家カーの代表作といえるのでは。
『九つの答』は結局ハヤカワミステリ文庫に入らなかったので、冗談で作ってみました。















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます