引き続き、山名初代 諸井国三郎先生の話であるが、読んでいただいてどのように感じられただろうか。
私が第3節で不思議と感じる点をいくつか挙げておきたい。
吉本八十次氏が番頭のウソに付き合わされて諸井家に入る事柄もさることながら、①2カ月ほどしてから彼がおたすけを始める事、そしてその様子を見ていた国三郎夫婦が、吉本八十次氏がいなくなった後に、②娘の身上に対して夫婦で相談して親神様に願う事などである。
①吉本八十次氏が諸井家に入ってから、農作業をしているのだから、多少のけがはあったと思われるが、多少のけがではなく、二日二晩苦しむ身上に対して神様に願っているのである。そして、先に神様の話をするのではなく、本人の代わりにお詫びをして、御守護を頂いた後に神様の話をしている点である。
その後、不思議な助けを求める人が出来て、雇い主の諸井国三郎夫妻も、その話を聞きながら、おたすけの手助けをしているのである。
②そして、吉本八十次氏がおぢばに帰ってから、奥さんの熱心な態度で、夫婦そろっての心定めをする点である。先の橋本伊平先生の名古屋での布教について、夫婦の様子が書かれてあったが、夫婦の心定め、それも奥さんの定めがどれだけ大切であるかという事を感じるのである。
③助けて戴いたお礼に、明治16年におぢばへ向かうのであるが、おぢばで直接、教祖からお話を承り、力比べをされた後の、心に残るお言葉「道について来ても足場になるなよ。足場というものは、普請が出来上がれば取り払うてしまう。何でも国の柱となれ。」がとても気になった。
普請をするためには、足場も必要なのである。そのために寄せられる人もある。と悟る事も出来ると思う。その中で、諸井国三郎先生は足場になる人ではないが、そうなる可能性もあると言われているように感じた。これが、親神様の人間を見られる見方と思う。
④吉本八十次氏とは、この時に会うのが最後で、いくら探しても消息が分からないという事も不思議である。
以上が、先の第3節での私の感想である。
では、次の第4節を添付しておく。どうぞ読んでみてください。
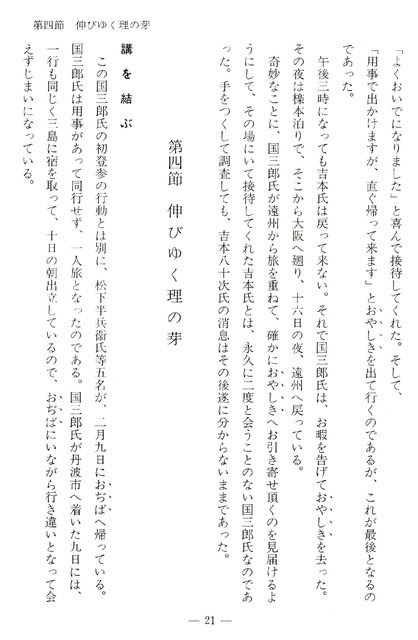







第5節は、次にします。
どうぞよろしくお願いいたします。










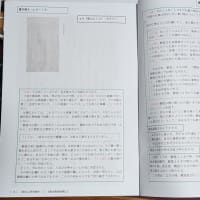















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます