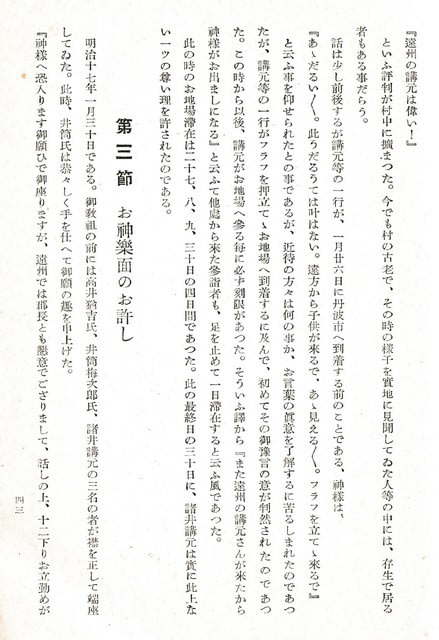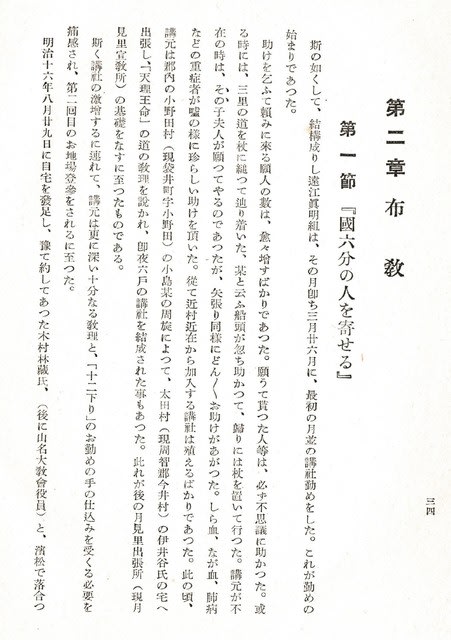これも、書き換えて見たいと思う。
この「神楽面のお許し」と言う題名を見ると、昔、ネットを始めた頃、「山名にはかぐらめんがあるから、かぐらづとめをつとめてもいいのだ!」という議論が盛んにされていたのを思い出す。
この節にもしっかりと、お許しを戴いたけれども、教会の設立の時には、「お面はぢば限り」とお許しを止められたことが書かれている。一度許されたのだから、それは永遠に許されたものと、思案する人もあるかと思うが、親神様は心次第にいつでも止められる。以前、断食の事から、針ケ別所の助蔵事件の事を書いた。また、ココでは書いたことはないが、扇のさづけなどを渡された事もあったが、これも止められて、今のおさづけになっている。さらに大きく言えば、神様の模様替えと当時は言われていたようだが、かんろだい没収から、おつとめのお歌を「あしきはらい」から「あしきをはろうて」に、「いちれつすます」を「いちれつすまして」に変えられている。
こうした親神様のお導きをしっかりと見据えて、思案をする必要があると思う。
最後に、おさしづについて書いておいた、最後まで読んで頂ければありがたいです。
第三節 お神楽面のお許し
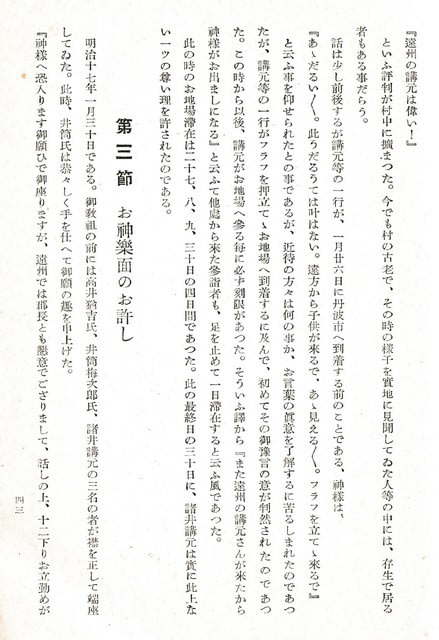
明治17年1月30日である。教祖の前には高井猶吉氏、井筒梅次郎氏、諸井講元の三名の者が襟を正して端座していた。この時、井筒氏は恭々(うやうや)しく手を仕えてお願いの趣きを申し上げた。
『神様へ恐れ入りますお願いでござりますが、遠州では郡長とも懇意でござりまして、話の上、12下り立ちづとめが出来ます故、お神楽道具のお許しを願いとうござります』

3人の方々は手を仕えたまま頭を下げていた。
稍々(やや)しばらくの間、教祖は静としてあらせられたがやがて、
『さあ/\許す/\。私が許すでない。神が許すのやで』
とのお言葉が下がったのであった。お願いの「お神楽道具及びお面お許し」の儀はかくして、鮮やかにお許しを戴いたのである。講元の歓喜は、いかばかり深いものであったろうか。井筒氏、高井氏も共々わが事のように喜ばれたのであった。
ここは実に破格の理であって、山名大教会の歴史上、特筆されるべき重要毎であると同時に、山名大教会末代に伝えて尊重され感激されべき、理の宝であらねばならぬ。重ねて記す。実に明治17年1月30日の事である。
早速にも「お面」及びお神楽道具一式を新調させて頂こうという事になり、翌31日講元は井筒氏と同道で大阪に出で、同氏方に一泊し、翌2月1日、井筒氏の外に周旋方2名の案内で、梅谷四郎兵衛氏方へ趣き、神様から結構に「お面」のお許しを戴いた事を話して「お面」とお神楽道具一式の調製方を同氏に依頼したところ、梅谷氏も『前例のない珍しいこと』と非常に喜ばれて早速快諾された。同氏の宅で一同昼食の御馳走になり、その夜7時7分発の汽車で、講元は京都へ発ち、同地に一泊、その翌日は大津へ出て、竹内方へ泊まられた。そこから東海道を歩いて、2月の8日に帰宅された。
こうして、おぢばへ参拝をして帰るごとに、講元の宅の方はお願い人は数を増して、日一日と忙しさを加えて行った。

その年の6月24日、さる2月1日に大阪の梅谷氏に依頼した、「お面」とお神楽道具の一式が講元の宅へ到着した(註、このお道具は船で遠州の福田港へ着いた)。その中には大阪真明講社より贈られた、三味線一挺も入っていた。
この日は朝から雨が降っていた。「雨あづけ」のお願いはしたが一寸には晴れそうな模様も見えなかった。講元は周旋方の田村権氏に、フラフを揚げるように言いつけたが、田村氏は依然として雨が降っているので、
『なんぼ講元さんが願ってもダメだ・・・』
とぶつ/\つぶやいているのを聞かれた講元は『小言を言わずと早く揚げよ』と言う。雨の中を田村氏が出て行き旗を結えてする/\紐を繰り上げる頃から、にわかに小雨となり見る/\晴れ始めて、田村氏が家の内に入るころには、全く空は晴天に晴れ渡っていた。講社の人らはこれを見て子供のように喜び勇んだ。この時掲げたフラフは、大幅2布の真ん中へ、日の丸を描き中に「天輪王講社」と記しその左下方へ「遠江国、真明組」と書いたもので、嘗(かつ)て豊橋で作らせたのと同様なものであった。これを門内の所へ高さ8間の旗竿を立てて掲揚したのである。
午前11時、今言ったお神楽道具の一式が到着した。酒1斗を買って講元及び講社の人々は、祝の宴を張って共々に喜び合った。
この「お神楽面」は翌明治22年正月の大祭まで、毎月おつとめに使用された。
この「お神楽面」を用いての「お面勤め」が山名の部下でたった1カ所だけ勤行された事実がある。
遠江国引佐郡都田村滝沢の講元、故山下丹蔵氏(現鹿玉分教会長山下長五郎氏の養父)は心にかけられて「お神楽面」を納める容器(唐櫃)の献納を思い立ち、見附町でこれを調製の上奉納した。この一事が機縁となって、明治19年旧3月4日に、丹蔵氏宅において勤行されたものである。この時は講元をはじめ主だちたる周旋の人々が出張された。勤められた役割の中で今日判明しいる者は左のごとくである。

国床立命(くにとこたち) 諸井講元
面足(おもたり)命 諸井茂三郎
国狹土(くにさづち)命 氏名不詳
月読(つきよみ)命 同上
雲読(くもよみ)命 同上
惶根(かしこね)命 同上
大食天(たいしょくてん)命 同上
大戸邉(おおとのべ)命 同上
伊弉諾(いざなぎ)命 山下多四郎
伊弉冊(いざなみ)命 山下小菊
なおこれは後の事であるが、明治21年4月天理教々会本部が認可され、翌22年3月18日、神道天理教会山名分教会所が許可となり、同年4月25日にその開延式を挙行するに当たり、当日この「お神楽面」を用いる事を、改めておぢばへお願いのため、役員伊藤源吉を登参せしめて、4月24日に神様にお願いすると、こういうおさしづであった。

明治22年4月24日(旧3月25日)
遠州山名郡分教会所に於て、お神楽面を開延式に付お許し伺い
『さあ/\たづねる処、たづねて一つ心の理があれば、たづね一つさしづしよう、どういう事であろう、さあさあとどまるじつさいたづねるまで一つ理、つとめ一条の理おおくの中、いくえ心得もだん/\はじめ、鳴物一切道具許そう、第一人間一つ始め、人数一つの理、だん/\話一つ/\、一時尋ねるまでの理であろう、めんはぢばかぎり、このお話しておこう。』※
と言うお言葉で「お神楽面」は「ぢばかぎり」という事に改まり、したがって開延式当日には「お面」は、神前におかざり申し上げたのみであった。
初代管長公よりも、
『これは山名の宝として大切にして、虫干しだけして大祭には飾らぬように』
とのお言葉があった。それ以来この「お神楽面」は山名大教会の宝物として秘蔵されてあったが、大正12年11月山名大教会から名京大教会が分割された際、前山名大教会長故諸井清磨氏によって、同教会へ分割して行かれた。したがって現在の山名大教会には、男神5柱様の「お神楽面」のみが保存されてある。
とにかく、たとえ一時の年限の間であったとは言え、このような重大な「お神楽面」のお許しを戴いた事は、実に「山名」に許された尊い理であって、特に前記のお言葉によって「お面」は「ぢば一つ」に限られるに至りて、この破格の理であった事を、より一層痛感せざるを得ないのである。
講元は後年、
-ーこうして特に「山名」に「お面」をお許し下されたというのは、われわれを励まして下さるための深い思し召しに相違ないーー
と心に悟られて、深くも感激されたのであった。
※このおさしづは、読みやすく書き換えた。以下に本部公刊のおさしづを記しておく。
No. :(1巻405頁9行)
明治22年4月24日 陰暦3月25日
『遠州山名郡分教会所に於て、御神楽面を開筵式に付御許し伺』
さあ/\尋ねる処、尋ねて一つ心の理があれば、尋ね一つさしづしよう。どういう事であろう。さあ/\止まる実際尋ねるまで一つ理、つとめ一条の理、多くの中、幾重心得もだん/\始め、鳴物一切道具許そう。第一人間一つ始め、人衆一つの理、だん/\話一つ/\、一時尋ねるまでの理であろう。面はぢば限り。このお話して置こう。
※※山名大教会史のおさしづと本部公刊のおさしづの違いに、不思議を感じる方もあると思う。
本部で公刊されたおさしづを「正とする事が重要」と言う点を示しておきたい。
おさしづは、数人の先生方によって書きとられたもので、その一枚が願い人に渡されたとの話を聞く。書きとられた先生の聞き方によって、漢字や言葉が違う事も予測できる。
つまり、山名では「第一人間一つ始め、人数一つの理」とあるが、本部公刊では「第一人間一つ始め、人衆一つの理」となっている点などを考える時に、良く分かると思う。
かぐらづとめは、人間創造の時の姿を現して勤められている。そこでつとめる人々は、その創造の時の神様の姿を現して、人衆として勤めているわけであり、人数よりも人衆が重要な点は明らかである。
おさしづを理解する上には、こうした点を知っておく必要があると思う。

いつもながら、私の文章は、読みにくいと思う。
申し訳ないですが、どうぞお許しいただきたい。
今日は、これまでにします。
人々に、親神様の思いが少しでも伝わり、陽気ぐらしへの心の建て替え、心の切り替えが進む一助となりますように。。。
親神様・教祖、新型コロナが、日本にまた広がり始めています。このままでは、せっかくおぢばがえりが出来ると楽しみにしている方々が、また帰られなくなります。
どうぞ、大難は小難にとお守りください。