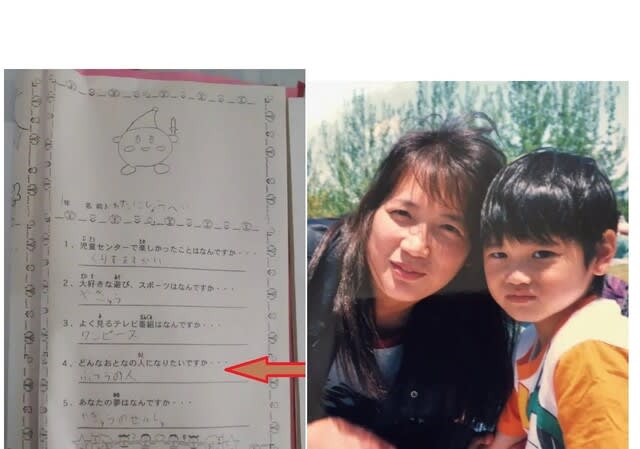「Brush up Oryo」
以前、「つぶやきの部屋61」で、若き日のお龍の容貌はかくあらんと紹介した鉛筆画ですが、
これまた臆面もなくブラッシュアップしてみました。
お良とするのが正しいのですが、便宜上ここでもお龍と称することにします。
髪型は、両輪髷(りょうわわげ)では無く、既婚女性のごくごく一般的な丸髷にしました。愛
嬌より度胸と侠気に富んだお龍のことですから、もう少し艶やかな髪型が相応しいように思う
のですが、「千里駒後日譚」(土佐新聞連載、川田雪山聞書、明治32年11月」の中で、
❝衣物なども余り奇麗にすると機嫌が悪るいので、自分も垢づいた物ばかり着て居りました。
(中略)長崎の小曾根で一日宿の主人等と花見に行く時お内儀(かみ)さんが、今日は
美(よ)いのを御召しなさいと云つたけれど、私は平生着(ふだんぎ)の次ぎのを被(き)て
行きましたが、龍馬が後で聞いてヨカツタヨカツタと云つて喜びました。十人行けば十人の中で
何処の誰やら分からぬ様にして居れと常に私に言い聞かせ(後略)❞
とお龍が語っているように、髪型も目立たぬ丸髷にしていた可能性は多分にあります。
小曾根とあるのは、龍馬ら海援隊同志と親交のあった質商小曾根英四郎のことで、お龍は
長崎にいたときにその夫妻(妻とは後に離婚)とも親しく交わっていた。
顔立ちについては、聞書きのためにお龍のもとを訪れていた安岡秀峰(重雄)は、当時57歳(亡
くなったのは66歳)のお龍のことを丸顔と語っていますが、お龍が龍馬亡き後に土佐の龍馬の実
家に身を寄せたときに、顔見知りになった仲子は、お龍のことを「どちらかといえば、小形の身
体に、渋好みの衣服がぴったり似合って、細面の瓜実顔は色あくまで白く、全く典型的の京美人
であった」
と回顧していますから、年を取ると歯を失ったり歯肉が落ちたりしますから、尺が縮んで見えた
のかも知れません。(少なくとも写真、明治33年お龍60歳のときのものからは丸顔には見えませ
ん。)
お龍は勤皇医の楢崎将作の長女ですが、『龍馬の妻 おりょう』(新人物往来社刊、前田愛子著)
によると、もとは町家の出で、西陣で誕生している(天保12年、1841年6月6日)ことから、西陣
織を生業にしていたものの、老中水野忠邦が行った天保の改革(天保12~14年)による奢侈禁止
令で生家が倒産。その時期は、お龍が10歳(数え、以下同様)のときに父が失踪し、母(縫)と
裏長屋で暮らすようになったとありますから、その歳のとき(嘉永3年、1850年)だったのでし
ょう。
楢崎将作との出会いは、お龍が12歳のときで、母の織った反物を井筒屋へ届けに通っていたとき
に、天然痘に罹った井筒屋の娘(幸)の治療のために往診に来ていた将作の目に留まったとあり
ます。
井筒屋は、縫の妹(シゲ)の嫁ぎ先で、その縁で出機(でばた)仕事をしていた。出機仕事は、
織屋から預かった糸を家で織る仕事で、その賃料は僅かであったとあります。
井筒屋は、御所での衣冠束帯を扱っていたともありますが、将作は、青蓮院宮の侍医を務めて
いたことから、御所繋がりで井筒屋との縁もできたのでしょうか。
最初から養女となったわけではなく、行儀見習いという名目で楢崎家に住み込むようになったと
あります。そして、13歳のときに、父母ともに亡くなったことから、楢崎家の養子になったとの
ことです。
龍馬が姉乙女に宛てた手紙(慶応2年12月4日付)では、将作亡き後には、❝老母一人、龍女、
いもと両人、男の子一人❞とあり、気の毒な身の上なので❝龍女と十二歳になる妹と九ツになる男
子❞を預かり、❝十二歳の妹きみへ、男子太一郎は摂州神戸海軍所の勝安房(*勝海舟)に頼みた
り。龍女事は伏見寺田や家内おとせに頼み候❞とありますが、その前年(慶応元年9月9日付)の
乙女宛の手紙では❝楢崎某と申医師、夫も近頃病死なりけるに、其妻とむすめ三人、男子二人、
其男子太郎はすこしさしきれなり。次郎は五歳、むすめ惣領は二十三、次は十六歳、次は十二❞
としていますが、このちょっと後の方では三女君江のことを❝十三歳❞としていたり、先の慶応2年
12月4日付の手紙ではお龍のことを❝今年廿六歳❞としていたり、と結構いい加減です。
慶応元年のときには男子二人だったのが、慶応2年で一人になっているのは、その間に次郎を
粟田口の寺(金蔵寺)に預けたためと思われます。
『龍馬の妻 おりょう』では、歳の順に光枝、健吉、君江、太一郎としていますが、健吉という名
は、明治32年から『文庫』に連載された安岡秀峰の手になる聞き書き「反魂香」にある将作と妻
貞は❝五人の子をまうけました(長女お良、次女光枝、三女君江、長男健吉、次男大一郎)❞を
参考にしているのだと思いますが、何故君江より長男とした健吉が年上になっているのかよく分
かりません。(大一郎は誤植ではなく、他でもそうなっているところをみると、秀峰が聞き間違
えたものと思えます。)
しかし、その秀峰が昭和6年の「坂本龍馬の未亡人」(『実話雑誌』、一ノ六所載)では、お龍に
は❝母と、弟と、二人の妹があった。弟の消息は忘れたが、次の妹光枝は中沢某に嫁ぎ、末の妹
君江は、菅野覚兵衛の妻となった。❞とあり、おそらく健吉の存在自体安岡にとっても曖昧なもの
であったのだろうと思います。(それゆえに長男太一郎と次男健吉が逆になったのでしょう。)
お龍が養子であったのか否か、その辺りのことを順を追ってみてみましょう。
お龍は天保12年(1842年)6月6日、光枝は嘉永3年(1850年)、君江は嘉永6年(1853年)、
太一郎は安政4年(1857年)、次郎は万延元年(1860年)の誕生とされていますので、慶応元年
(1865年)当時は、いずれも数えで、24歳、16歳、13歳、9歳、6歳でした。
それと、将作が50歳で病没したのが文久2年(1862年)7月16日ですから、そのときのそれぞれの
年齢は、21歳、13歳、10歳、6歳、3歳。
お龍が将作の所へ住み込みに入ったときには12歳ですから、光枝4歳、君江1歳、太一郎も次郎も
まだ生まれてはいません。
将作は文化10年(1813年)生まれですので、(お龍は養子として除くとして)光枝は38歳のとき
の、君江は41歳のときの、太一郎は45歳のときの、末子次郎は48歳のときの子となります。
妻である貞の年齢がどうであったか。「反魂香」によると、❝明治二十四年一月三十一日、当三浦
郡豊島村字深田で病死仕ました。(中楽)享年は七十三歳❞とあります。
明治24年(1891年)で勘定すると、お龍を除いて、光枝は31歳、君江は34歳、太一郎は38歳、末
子次郎に至っては41歳のときの子となります。今ならあり得ますが当時としては極めて不自然です。
お龍だけが養子で、あとは実子と考える方がおかしいのです。むしろお龍だけが実子(それなら、
将作30歳、貞23歳のときの子になる)といってよいくらいです。
全員が養子である可能性も考えられるのです。将作には財がありましたので、お龍と同じような境
遇の子を引き取っていたのかも知れません。そして年端の行かない子供を引き取ったときには、将
作夫妻が名前を付けることはあってもすでに名前のある者はそのままにしたのだろうと思います。
命名に一貫性が無いのでそのように思うだけですが。
安岡秀峰の「続反魂香」によると、お龍は横須賀へ向かう途中で東京に寄って身の振り方を頼んだ
とあります。おそらくそのときに弟の行く末を頼んだのでしょう。
「反魂香」では、お龍が一人で東海道を歩いて東京霞が関の吉井友実(吉井幸輔。龍馬が寺田屋
で負った深手養生のためお龍を伴って薩摩へ渡航したときにその世話をした)の元を訪ねたとき
に、折よく西郷が来合せていて、そこで❝大阪に居る母や、妹の光枝や太一郎の三人を養わなけれ
ば、なりませむから、如何か身の振方をお頼み申す事に、西郷も同情を表して、金子二十円をお
良にやり、私も此度征韓論の事で大久保と論が合はず、依つて一先づ薩摩へ帰つて百姓をするか
ら、再び上京した時には、きつと腕にかけても、御世話は仕ますからそれ迄、お待ちなさい❞と
あります。
ここでも健吉が省かれています。(君江はそれ以前の慶応4年4月に海援隊士の菅野覚兵衛と結婚
しているので除かれている。)
一次史料が手元に無いので確かなことは云えないのですが、次男健吉は警官、長男太一郎は海軍の軍
楽隊に奉職したと記憶しております。
金蔵寺へ預けられてから、それ以後の健吉の消息は明らかではありません。寺でなのかそこから移っ
た先でなのか、全くもって分かりませんが、そこで健吉と名付けられたのか、明治になってから改名
したのか。
いずれにせよ、お龍との縁がその後も繋がっていたからこそ、聞き書きで健吉という名がでてきたの
だろうと思います。(寺田屋のお登勢の関係先で養われていたのなら、すっきりするのですが。)
それにしても血のつながりのない母貞や妹や弟を親身になって、龍馬の援助もあったのですが、面倒
をしっかりとみたお龍は義理堅い女性であったように思います。
龍馬がお龍とともに下関に寓居(「自然堂」)を構えていたときに、土佐藩士佐々木三四郎(後の高行。
龍馬とは深い親交があった)は土佐須崎港から龍馬とともに長崎に戻る途中で下関に寄港するのですが、
そこで龍馬からお龍を紹介されています。
佐々木三四郎は、土佐商会(海援隊隊士の給与支給などを行っていた)の責任者として出向(慶応
3年8月)してきた。
そのときの印象を佐々木は日記「保古飛呂比」(ほごひろい)の慶応3年8月14日のところに、❝才谷
(*龍馬の変名)ノ案内ニテ稲荷町大坂屋ニ休息シ、才谷ノ妻ノ住家二才谷同伴。同妻ハ有名ナル美人
ナレ共、賢夫人ヤ否ハ知ラズ。善悪共為シ兼ヌル様二被㋹思タリ(*レ点を㋹としました。「思われた
り」となります)❞ と認めています。
武家の婦人(夫唱婦随で夫に傅くといったイメージ)と比較されるお龍が可哀そうですが、町家出の女
性としても龍馬が好む「はちきん」(男勝り)なところがあったことは、女郎屋に売られた妹光枝を単
身大坂に乗り込んでやくざから取り戻したり、裸同然の姿で風呂場から龍馬に急を知らせたり、湯治療
養先の薩摩では霧島山山頂の天の逆鉾を抜き取ったり、龍馬を援けるためと短銃の稽古をしたりと、事
欠かない逸話からも十二分に窺うことができます。
そういった侠気(目元、口元にでる)を描き出せているかはなはだ心もとないのですが、僕なりに苦心
惨憺、トライしてみました。(^^ゞ
ブログトップへ戻る