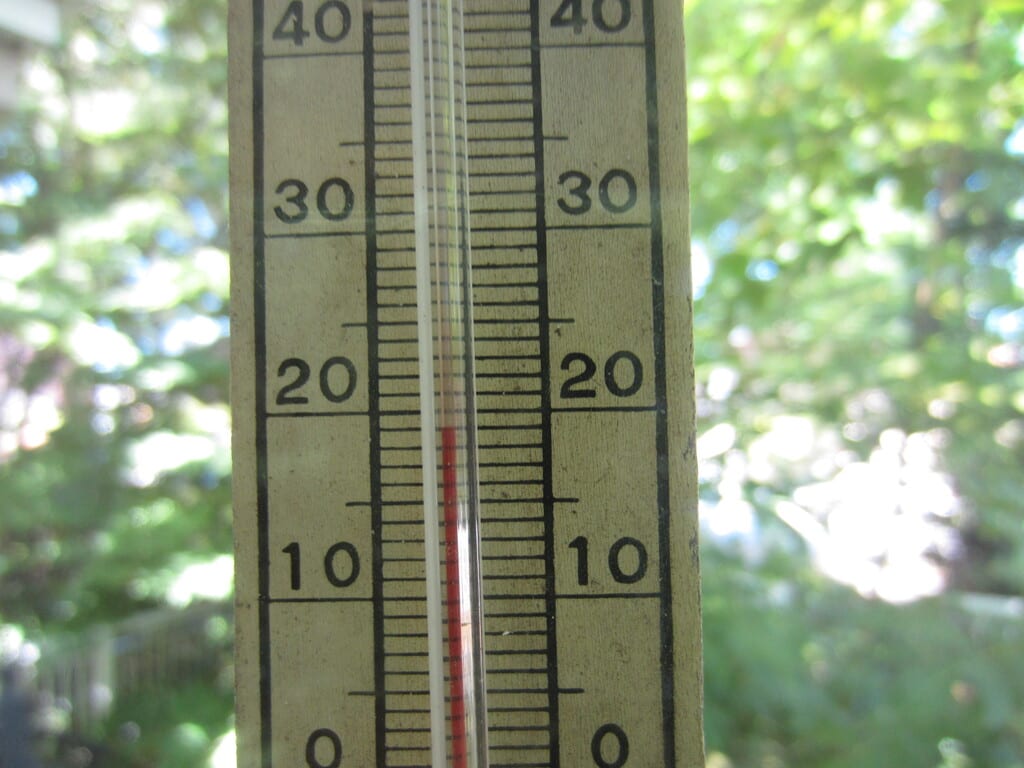イヌバラ(Rosa canina)の実(ローズヒップ)
2023.07.04撮影
(今日掲載の画像は、記事の内容に全く関係ありません。昨今、わたしの庭に成っている実と、その前に咲いていた花をお見せします。)
わたしは、ちょうど4年ほど前に、人口股関節置換術を受けていて、それ以来、右側の腰が弱めです。それで、こけると、どうしてもそちら側にこけてしまう。
手術してから2年して、やっと庭仕事ができるようになり、脚立にも登るようになりました。そして、この脚立から、何回落ちたことか、右側を下にして。そして、その後、どれだけ痛みに苦しんだか。
今回落下する時(また、落っこちた - カラスといちごとクロッカスと)、絶対に腰を下にして着地してはいけない、と思い、何かをつかもうとしたのですが、それがかなわず、そのまま、両足を真下にしてが〜〜んとコンクリートの上に落ちてしまいました。キウイのツルが弾けたときの反動と、全体重(大した重さじゃないが)と、3段目から落ちるときの重力と、が、面積としては小さいかかとにだけかかってしまったのです。勢いで、尻もちをつきました。
茫然としたわ。また、落っこちた。
そこに、何分、固まって座っていたのか知らないけど、このままではいけないと思い、その場はそのままにして、痛みをこらえながら、とにかく家に入りました。即、冷やすべき?
イヌバラ(Rosa canina)の花(白花)
2021.06.04撮影
家に入ると、痛みはますます増すばかり。痛みで歩けない。
救急に行くべきか考えたけど、車庫に家の鍵を置いたままなのに気づき、そのままでは用心が悪いから出かけられない。その鍵は、家の裏口のドアも開ける。自分で取りに行くのは、到底、ムリ。
つれあいはシアトルに所用で行っていていなかったので、お隣に電話かけるも、留守、そのお隣も、留守。力も尽きて、そのまま横たわっていたら、つれあいから電話が入り、何をしているんだ、すぐにタクシーで救急に行け、と。
で、わたしが、いや、鍵が車庫に置いたままで、ふにゃらふにゃら、とごねていると、分かった、分かった、帰るのは今晩遅くなるから、明日の朝、救急に行こう、ということで、朝、救急に乗りつけました。
コボウズオトギリ(Hypericum androsaemum)の若い実
2023.07.04撮影
救急入口で車を止め、つれあいが車椅子を取りに行き、わたしを車から降ろして椅子に乗せ、窓口へ行きました。なぜか職員が窓口に5人ぐらいたむろしていましたが、それぞれ役職はあるのかもしれません、患者にはわからないだけで。
病院や医院での受付は、健康保険証を見せるだけ。わたしは、この病院では、前に人口股関節の手術を受けたので、受付は初めての人より簡略化されていたのでしょう。
つれあい(白人)がいっしょだとみんな愛想がいいのよね。つれあいが「みんな優しいね〜〜、親切だね〜〜」って、「優しい人ばかりで良かったね〜〜」って。
あんなあ、あんたさんがいるから、みんな、あんななのよ、黄色いわたしだけだったら、みんながみんな、あそこまで愛想よくないわ、と思ったが、とにかく痛みで疲労困憊。思っただけで、何も言わなかった。
コボウズオトギリ(Hypericum androsaemum)の花とツボミ
2023.06.13撮影
つれあいが救急入口からよそへ車を移動させている間に、わたしはベッドをあてがわれ、医者が来て、その後、レントゲン写真を撮り、連れ返されて、わたしは疲れて眠ってしまいました。レントゲン写真には異常が見えない。
その次に、CTスキャンに送られ、それも異常が見えない。車椅子に乗せられてスキャンから帰ってくると、ベッドが取り上げられていた。そのころになると、つれあいは行かなくてはならないところがあり、後で迎えにくるから、と一旦退出。
看護師さんが出てきて、「おや? ひとりなの?」と言う。「そう、つれあいは用があるので帰ったけど、後で迎えにくる」と言うと、その看護師さんはわたしに向かって、「医師が言うには、あなたは、骨にも組織にも全く異常がない、もう帰りなさい、ただし、あなたが帰る前にあなたが歩けることを確認しよう」と言ったんだよ。
おいおい、痛くて歩けないからここ来たんだよ。異常が見つけられない、は検査には出てこない、だから、いいとしても、この状態で歩け、って?????????????
「あなたの体に悪いところは何もない、帰れ」と譲らないので、歩けないところを、ムリに数歩歩いて、「歩ける」ところを見せるしかなかった。これ、虐待じゃない?
せめて、つれあいと約束した正面出入り口の待合室(こちらは、ゆったりとしていて、いいソファが使われていて、救急の待合室のように混雑していない)まで車椅子で送ってもらえないか、と言うと、拒否された。エレベーターはどこ、と聞くと、あっち、で終わり。
エレベーターまで、泣く泣く、そろ〜りそろ〜り、いた〜いいた〜い、と移動しているとき、白人女性が空の車椅子を移動させていたが、一瞥もくれなかった。次にアジア人男性が同じく空の車椅子を移動させているのが見えたが、この人は、こちらが頼む前に、すっ飛んできて、乗せてくれた。ありがと、ありがと、ありがと・・・
スズラン(Convallaria majalis)のひとつ残った実(花びらがまだついている)
2023.08.02撮影
結局、骨や組織に異常がない、と分かっただけで、そして、それは良かったんだけど、痛みについては、鎮痛剤を飲め、というだけで、回復を早める指導はなかった。救急には、合計7時間ほどいました(つれあいが迎えにきてくれるまで、さらに1時間)。
友だちが、「結局、打ち身でしょう」と言う。なるほど、医者よりいいことを言ってくれる。打撲傷、全治2週間? 3週間?
落っこちたのが前の日曜日の夕方、救急に行ったのが月曜日、それから3日ほど、体がショック状態でソファの上でうつらうつらしていました(ブログ記事は、それより前に、予約投稿にしてあった)。
その後、目は覚めましたが、とにかく、足の裏が痛いので、歩けない。それで、脚に車輪のついた椅子(机に向かって使うような椅子)に乗って、人口股関節の手術をしたときに買った杖で壁を押して、椅子を動かして、移動しています。
這えるところは這っていますよ〜〜、その方が素早く移動できるので。
スズラン(Convallaria majalis)の花
2021.05.17撮影
病院からの請求はいくらだったでしょう。
カナダは公費医療制で、特定のものは除き、個人に医療費はかかりません。よって、0(ゼロ)です。
このことについては、次回。