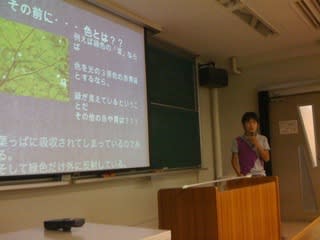科学技術というが,本来科学と技術は別ものである。
技術は徒弟制度の中のものであり,排他的であり,門外不出であった。18世紀の産業革命以降,フランス革命以降,技術教育は学校の中に設けられ,技術が広く大衆に開かれるようになった。技術教育の始まりである。
一方,科学はリベラルアーツのうち,自然を解き明かすものであった。神は,聖書と自然の中に教えをといた。ガリレオは,神様は自然を数学で表現したとし,自然界を数学で解き明かすことが科学の役割であるとした。
従って,科学はあくまでも神様の秘密を解き明かすものであった。仕事や産業,技術とは無縁のものである。教養の一部なのである。本来,科学を学んで,仕事を得るということは稀であったのである。
しかし,その流れがかわったのは第一世界大戦以降である。爆薬や肥料等が化学の知識によって開発されるようになった。
ドイツは毒ガスを大量に作成することに成功した。また,第2次世界大戦で,アメリカの原子爆弾の成功によって,科学は国の発展に貢献することが広く,理解されるようになった。この頃から,科学と技術が合体し始めた。アメリカは,対戦を契機に,1950年に全米科学財団を設立して,潤沢な研究費を研究者に配分する制度を作った。と同時に,研究者を育成するための科学教育支援のための施設を作ったのである。科学を発展させるための礎ができたのである。
そして,大量生産や新技術開発と豊かな生活とがオーバーラップされ,科学の発展は人間生活の発展に寄与するものであると誰もが疑わなかった。
しかし,最近になって科学の発展には限界がある,ということが分かり始めた。地球温暖化という形で我々の生活を脅かしている。これをどう対処するか,という時代になった。その対処のためには,単純な科学の発展だけでは難しいという結論だ。
できるだけ無駄をなくし,できるだけ後世に禍根を残さないようなライフスタイルが求められている。その結論として,現代人にとって,科学とはなんであるかを理解する,機会を与えることであるといわれるようになった。科学技術のユーザーである一般市民が,科学の功罪を知り,責任ある行動をとることによって,すなわち科学リテラシーを持つことによって現代の諸問題を解決していくのである。
一方水産業はどうなのか,科学技術の発展によって,漁獲率の向上,品質向上が図られるようになった。流通も発達し,冷凍技術の発達,新しい食品の開発,有効利用,豊かな食生活を満喫できるようになった。科学技術の発展は我々の魚食文化,食生活の発展に寄与している。
しかし,水産業では様々な問題を抱えている。魚離れ,魚価安,後継者不足,経営問題。このような状況はどうとらえればいいのであろうか?科学技術の発展と方向性から考えると,一般市民が水圏環境(水産)リテラシーを持つことによって,個別の利益追求の形としての水産業から,地域を核にした産業,地域産業を,消費地である大都市が支える仕組み。おそらく,これまで個別の対応をやめ,いろいろな業界が一体となった対応が必要になると考える。それらを解決していくのが大学の一つの大切な使命ではないだろうか?
技術は徒弟制度の中のものであり,排他的であり,門外不出であった。18世紀の産業革命以降,フランス革命以降,技術教育は学校の中に設けられ,技術が広く大衆に開かれるようになった。技術教育の始まりである。
一方,科学はリベラルアーツのうち,自然を解き明かすものであった。神は,聖書と自然の中に教えをといた。ガリレオは,神様は自然を数学で表現したとし,自然界を数学で解き明かすことが科学の役割であるとした。
従って,科学はあくまでも神様の秘密を解き明かすものであった。仕事や産業,技術とは無縁のものである。教養の一部なのである。本来,科学を学んで,仕事を得るということは稀であったのである。
しかし,その流れがかわったのは第一世界大戦以降である。爆薬や肥料等が化学の知識によって開発されるようになった。
ドイツは毒ガスを大量に作成することに成功した。また,第2次世界大戦で,アメリカの原子爆弾の成功によって,科学は国の発展に貢献することが広く,理解されるようになった。この頃から,科学と技術が合体し始めた。アメリカは,対戦を契機に,1950年に全米科学財団を設立して,潤沢な研究費を研究者に配分する制度を作った。と同時に,研究者を育成するための科学教育支援のための施設を作ったのである。科学を発展させるための礎ができたのである。
そして,大量生産や新技術開発と豊かな生活とがオーバーラップされ,科学の発展は人間生活の発展に寄与するものであると誰もが疑わなかった。
しかし,最近になって科学の発展には限界がある,ということが分かり始めた。地球温暖化という形で我々の生活を脅かしている。これをどう対処するか,という時代になった。その対処のためには,単純な科学の発展だけでは難しいという結論だ。
できるだけ無駄をなくし,できるだけ後世に禍根を残さないようなライフスタイルが求められている。その結論として,現代人にとって,科学とはなんであるかを理解する,機会を与えることであるといわれるようになった。科学技術のユーザーである一般市民が,科学の功罪を知り,責任ある行動をとることによって,すなわち科学リテラシーを持つことによって現代の諸問題を解決していくのである。
一方水産業はどうなのか,科学技術の発展によって,漁獲率の向上,品質向上が図られるようになった。流通も発達し,冷凍技術の発達,新しい食品の開発,有効利用,豊かな食生活を満喫できるようになった。科学技術の発展は我々の魚食文化,食生活の発展に寄与している。
しかし,水産業では様々な問題を抱えている。魚離れ,魚価安,後継者不足,経営問題。このような状況はどうとらえればいいのであろうか?科学技術の発展と方向性から考えると,一般市民が水圏環境(水産)リテラシーを持つことによって,個別の利益追求の形としての水産業から,地域を核にした産業,地域産業を,消費地である大都市が支える仕組み。おそらく,これまで個別の対応をやめ,いろいろな業界が一体となった対応が必要になると考える。それらを解決していくのが大学の一つの大切な使命ではないだろうか?