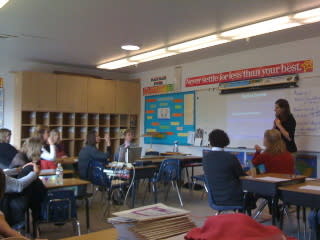ナショナルアクアリウム in DCを訪問した。
この建物は商務省の地下にあり,1800年代に設置された歴史のある水族館である。本来は,水産資源の減少を危惧した研究者たちにより飼育施設として始まった。設立当初は,MBL(ウッズホール海洋生物学研究所)とも関わりもあるようだ。1 educator, 4 aquarist, 1 exbitary , 1 directorである。100年以上の歴史を感じさせる展示である。今はやりの巨大水槽はないが,入館者数は1000/day summertime, 500/day wintertmeであるという。
NPOが経営をしている。こちらのNPOは国からの支援を受けている他,ドーネーションによって成り立っている。アメリカン自然史博物館もNPOの経営である。(寄付活動は普通であり,生前に寄附するのをPlaned giving といい,遺産を寄附するのをEstate givinngという。知り合いによると聞,生前に寄附することで生きているうちにその効果を確かめることが出来るのでいいのだ,という。アメリカは支え合って成り立っているともいっていた。国からの支援がほとんどなく,寄付行為の習慣もない日本とは大きな違いである。)
アクアリストの一人にインタビューをした。
-why do you select aquarist?
--My major is biology, but marine science class taking,diving, aquarium loving.In Us Marine science getting popular,
-why?
-- Marine issue, aqua problem will be becoming important.
NOAAとの関わりを聞くと,NOAAに所属するNational Marine SanctuaryやNational Marine Sanctuaryから情報を提供してもらい,環境保護について最新の情報を提供しているという。
この建物は商務省の地下にあり,1800年代に設置された歴史のある水族館である。本来は,水産資源の減少を危惧した研究者たちにより飼育施設として始まった。設立当初は,MBL(ウッズホール海洋生物学研究所)とも関わりもあるようだ。1 educator, 4 aquarist, 1 exbitary , 1 directorである。100年以上の歴史を感じさせる展示である。今はやりの巨大水槽はないが,入館者数は1000/day summertime, 500/day wintertmeであるという。
NPOが経営をしている。こちらのNPOは国からの支援を受けている他,ドーネーションによって成り立っている。アメリカン自然史博物館もNPOの経営である。(寄付活動は普通であり,生前に寄附するのをPlaned giving といい,遺産を寄附するのをEstate givinngという。知り合いによると聞,生前に寄附することで生きているうちにその効果を確かめることが出来るのでいいのだ,という。アメリカは支え合って成り立っているともいっていた。国からの支援がほとんどなく,寄付行為の習慣もない日本とは大きな違いである。)
アクアリストの一人にインタビューをした。
-why do you select aquarist?
--My major is biology, but marine science class taking,diving, aquarium loving.In Us Marine science getting popular,
-why?
-- Marine issue, aqua problem will be becoming important.
NOAAとの関わりを聞くと,NOAAに所属するNational Marine SanctuaryやNational Marine Sanctuaryから情報を提供してもらい,環境保護について最新の情報を提供しているという。