古いキャブレター。
今日は実油面の調整をいたしました。

実油面。。。
キャブレターの中にガソリンがどれだけ入ってきて、オーバーフローしないで溜まっているのか?を実際に目で見て確かめるんです。
キャブレターはよく 霧吹き なんて言われますが、実際の油面が低すぎたり、高くてオーバーフローしたりでは、霧の出方、、、ガソリンの供給に変化が出ますね。
という事は、キャブレターのセッティングがメーカー設計時とは違ってくるって事だと思います。
とりあえず、実油面を決めないと調子が出ない事がありそうですよね。

一国の図書館を探してみたら、、、ありました!
初期型のマニュアルが。
緑の表紙のマニュアルが 昭和53年4月 ですので初期モデルのマニュアルになります。
中を覗くと、、、

油面の調整はフロートの高さ H寸法 の調整が出ています。

油面高さ(H寸法) 23.5±1mm
としか書いてありません。
23.5mmは実際の油面の高さではありません。
キャブレターの合わせ面からの高さになります。
H寸法を組み立ての時に調整しておけば、、、OK!って事?
このマニュアルには実油面の事は書いてありませんでした。
なので、、、もう一冊のマニュアルを、、、
こちらはフロントがドラムになった2型?って言うかな、のマニュアルです。
こちらには実油面の点検の仕方が書いてありました。


こうやって実際にキャブの中の油面を確認いたします。
ではでは組み上がったキャブレターにホースをセットして、ガソリンを入れます。
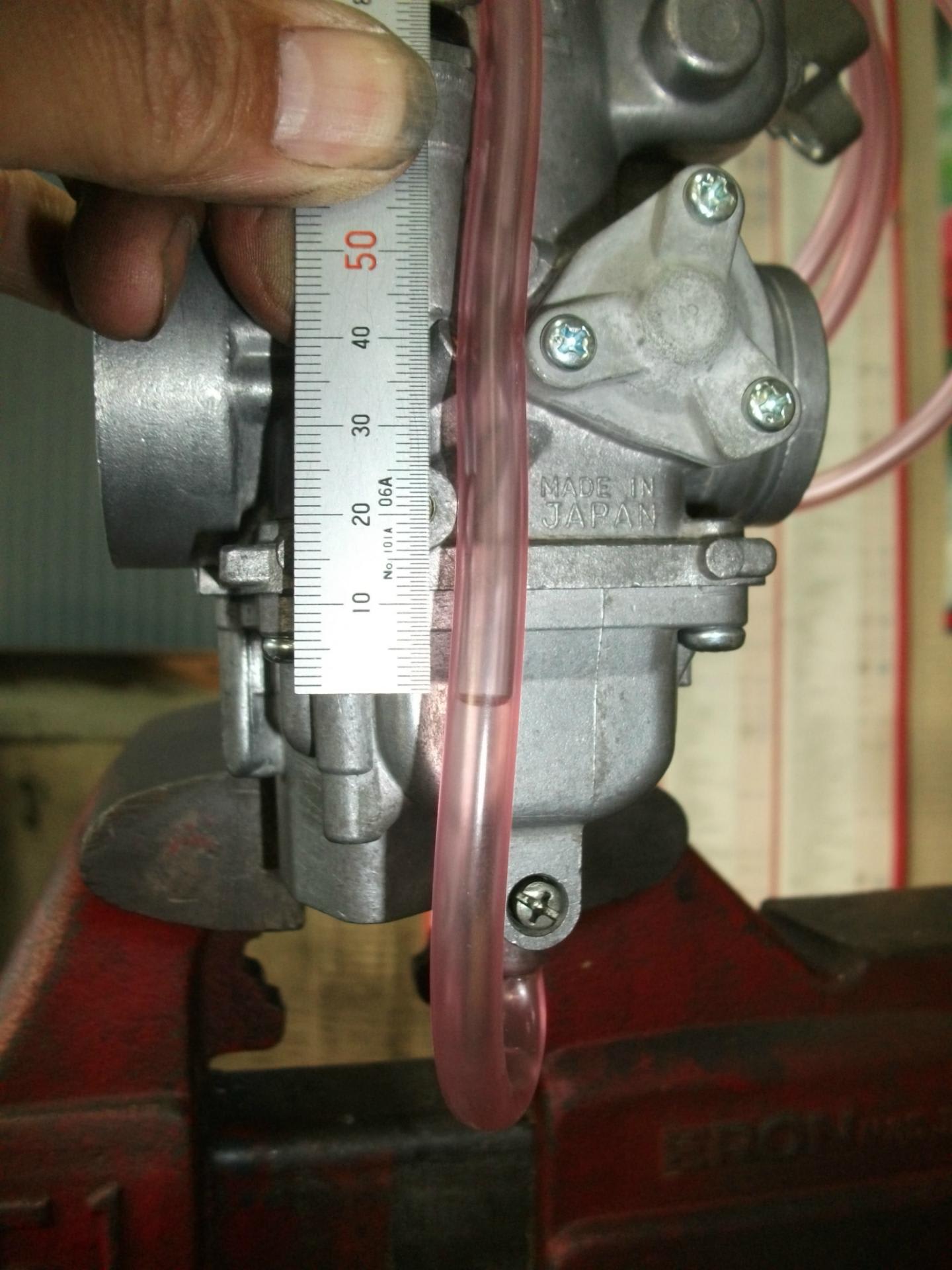
フロートは再使用、H寸法は調整せずに、フロートバルブは新品で組みたてました。
結果は、、、実油面12mmです。
基準実油面は4.5±1mmです。
この結果から見ると、オーバーホールをして部品の交換をすると、微妙な寸法誤差で実油面が変化してしまう!って事になります。
セッティングは、、、各ジェットやニードルのクリップ位置、パイロットスクリューの戻し回転数などに狂いが出るのかと。。。
だからここを決めておかないと、先に進めないと思いますね。
多気筒などのキャブだと各気筒でバラつきが出る?
なのでH寸法は目安でしかなく、実油面を点検しないとダメなんだと思いますね。
さあ、調整をいたします。

調整はフロートバルブを押しているリップを曲げて行います。
ほんのちょっと、微妙に、、、曲げるとH寸法が変わってきます。
そして組み上げて、また測定です。

まだ足りません。。。
やり直しです。


ちょっと行き過ぎ。。。
こんな事を繰り返して、、、

範囲に入りました。
このときのH寸法は、、、
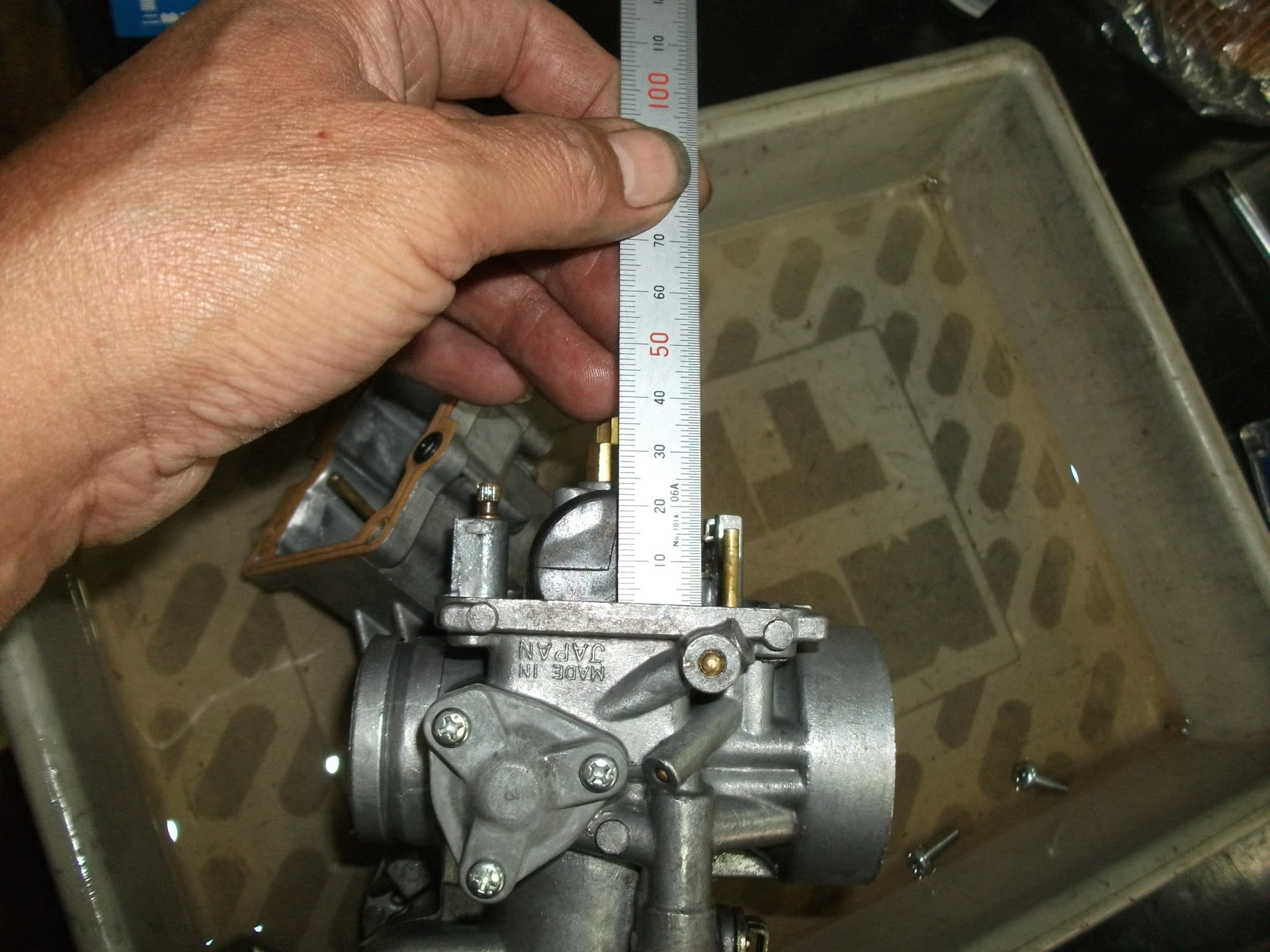
23mmでした。
さて、、、エンジン始動かな。。。



























一国の図書館は当店の倉庫ですので、未公開になっています。
SRのサービスマニュアルは古い年式のものでも、現在ヤマハに在庫が有りますので、入手可能ですよ。