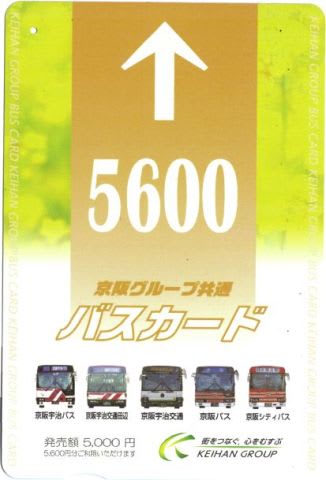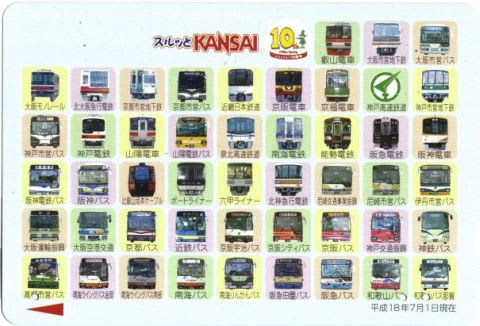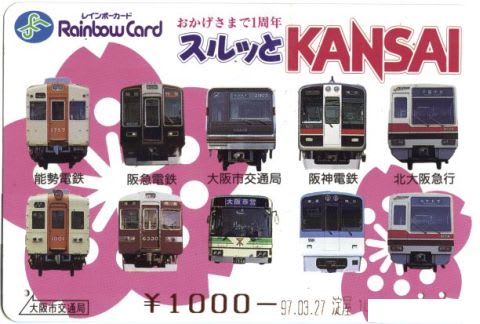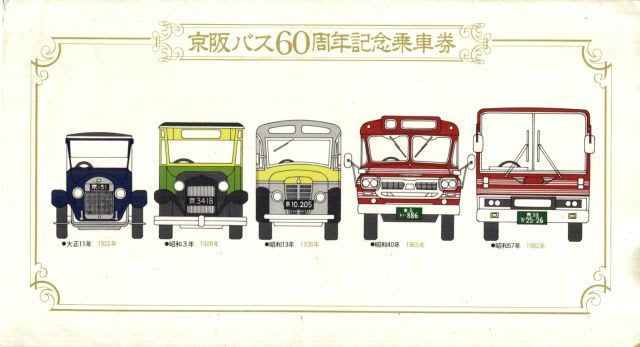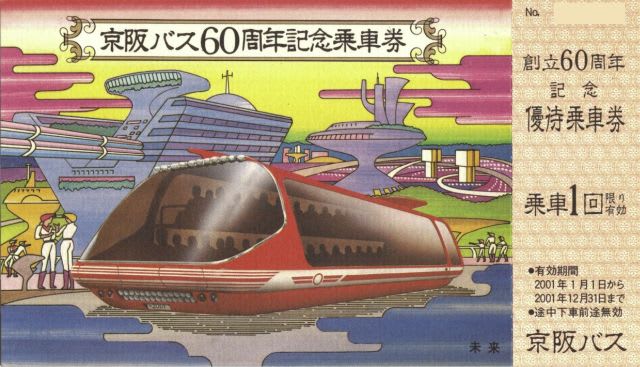e-kenet PiTaPaカードです。e-kenet VISAカード(京阪カード)の子カードとして発行されるものです。以前は、クレジット機能無しのe-kenetカードがあったのですが、今はクレジットカードを持たないとこのPiTaPaカードを持つことはできません。PiTaPaを使っていても、e-kenet VISAカードを1年間利用がないとe-kenet VISAカードの年会費を取られてしまいます。
今は、e-kenet VISAとe-kenet PiTaPaの口座引落しは一本化されていますが、私が申し込んだときには完全に2つに分かれていました。e-kenet VISAは毎月27日引落しですが、e-kenet PiTaPaは三井住友カードに委託している関係で毎月10日引落しとなっていました。
こんな面倒くさいe-kenet PiTaPaですが、京阪電車利用分に関してはポンイトが貯まり、京阪カード加盟店で使用できるクーポンに交換できます。京阪カード加盟店ではe-kenet VISAカード提示によるショッピングでも同じポイントが貯まりますので、京阪グループの商業施設をよく利用する人にとってはそれなりに使い道があります。一方、京阪沿線に住んでいても京阪グループの商業施設を利用しない人にとっては、e-kenet PiTaPaを持つメリットはありません。