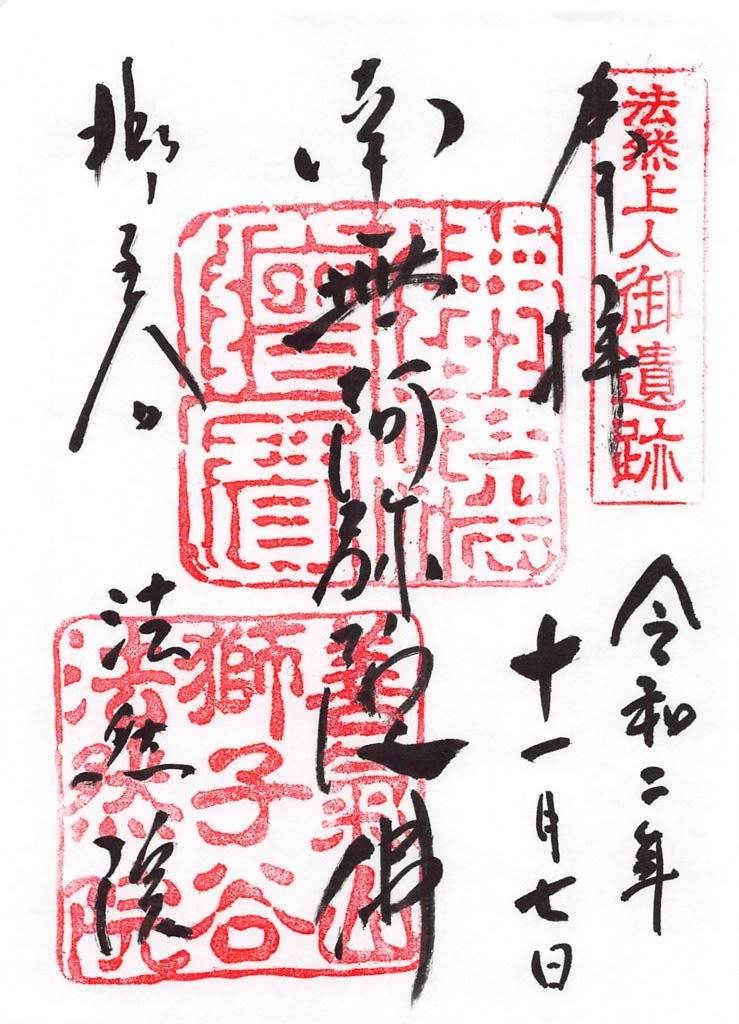11月13日は「瓢亭x無鄰菴 秋の南禅寺界隈を味わう 和ろうそく茶会」に参加しました。































先ずは瓢亭別館で点心を頂きます。
(本館ならばなぁ、、、とは思いますがミシュラン三つ星の名店、、、無理ですね)




鯛のお刺身には天然クロカワと菊の花を塩漬けにしたものを戻したものが添えられてらいます。





松花堂弁当を彷彿とさせる八寸です。
季節感たっぷり、京料理(和食)の王道ですね。
海老芋に湯葉、海老、モロコの山椒焼に焼栗、銀杏、鯛と海老の菊花寿司。
シャインマスカットに千枚漬け、には豆腐ベースのごまクリームがかけられています。
鰆の柚庵焼に名物"瓢亭玉子"、、充実の内容です。



ご飯は栗ご飯、、、もち米が何割か入っているのでしょうか?もちもち感たっぷりです。
香の物は小かぶらの漬物にじゃこえのき。


腕物は紅ズワイガニの真薯です。
真薯と言っても殆どは蟹の身です。甘味と言い、食感と言い、ぶぐとともに冬の味覚の王様ですね。
若い頃には毎冬に城崎温泉に蟹のフルコース、温泉巡りをするのが恒例の行事でしたがもう何十年もご無沙汰です。


最後に水物です。
渋柿の大城柿にシロップ漬けにしたラ・フランスに洋酒のジュレと一緒に頂きます。
柿をここまで完熟に出来るのですね?葉と皮以外食べる事ができ濃厚な甘さでした。
食事が終わり無鄰菴へと移動します。
主屋二階で無鄰菴の指定管理者植彌加藤造園の山田プログラムディレクターより名勝無鄰菴庭園のガイドがありました。
詳細は省略しますが日本庭園の特徴のひと「飛泉障り(ひせんさわり」の解説もありました。
この庭園の主山は背後に連なる東山であり、そこから水が流れるの光景がメインとなっています。最も東にある三段の滝に「飛泉障り」の手法が用いられています。
つまり、滝の流れ出るところをかえでなどの植栽で一部を隠し、見る者の想像を掻き立てる手法です。
最も分かりやすい例が南禅寺本坊の「滝の間」(お抹茶席)です。
無鄰菴の水は琵琶湖疏水の一次水を使っていて、蹴上との高低差を利用し自噴しています。無鄰菴を流れた水はお隣りの瓢亭さんへ、、、と言うように二次、三次とネットワークを形成し活用されています。

しばし二階からの紅葉を眺めます。



次に主屋一階で「和ろうそく」茶会です。



風情ある和ろうそくの中、お抹茶と主菓子を頂きます。
贅沢なひと時を感じます。
今や和ろうそくを製造しているのも二件になり、そのひとつ"中村ろうそく"さんの物が使われています。




わずか10名のアットホームな雰囲気の中、心和む"和ろうそく茶会"でした。
茶会の時の座布団が小さく、すぐに脚が痛くなりました。改善をお願いしたい点です。