7月25日 (月曜日) 曇り
記事を載せる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
「俺たちはバカなのかもしれない」。
記事には2010年3月に共同通信社が行った世論調査
「次の首相にふさわしい人」の順位が載っていた.
▲「俺たち」が選んだ
3位は菅直人(かんなおと)氏(7・4%)、
2位が鳩山由紀夫(はとやまゆきお)氏(8・3%)、
1位は舛添要一(ますぞえよういち)氏(23・7%)。
★今にして思えば世論調査なんて当てにならないもんだ!
--------------------
いずれもリーダーとしての評価は芳しくなかった。
東京都知事選が31日に投票日を迎える。
今度こそふさわしい人をと思うが、
有力候補の演説は耳に心地よい内容がほとんどだ。
明確な争点も見えてこない。
▲そんな時に哲学者、鷲田清一(わしだきよかず)さんの著書「しんがりの思想」を読んだ。
強い指導者を待望して政治を「お任せ」することを戒めたうえでこう説く。

=======
やかましいほどにリーダー論、リーダーシップ論がにぎやかである。
いまの日本社会に閉塞感を感じている人はとくに、大きく社会を変えてくれるような強いリーダーを求めている。
しかし、右肩下がりの縮小社会へと歩み出した日本で本当に必要とされているのは、
登山でしんがりを務めるように後ろから皆を支えていける、または互いに助け合えるような、
フォロアーシップ精神にあふれた人である。
そしてもっとも大切なことは、いつでもリーダーの代わりが 担えるように、
誰もが準備を怠らないようにすることであると著者は説く。
人口減少と高齢化社会という日本の課題に立ち向かうためには、
市民としてどのような心もちであるべきかについて考察した一冊である。
ーーーーーーーーーーーー
鷲田清一(わしだ・きよかず)1949年、京都生まれ。
哲学者。京都市立芸術大学学長。
大阪大学名誉教授。せんだいメディアテーク館長。
専門は臨床哲学・倫理学。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。
監査委大学文学部教授、大阪大学教授、同大学文学部長、総長、大谷大学教授をへて現職。
著書に『分散する理性』『モードの迷宮』(以上2冊でサントリー学芸賞)、
『「聴く」ことの力』(桑原武夫学芸賞)、『「ぐずぐず」の理由』(読売文学賞)、
『「待つ」ということ』、『哲学の使い方』など多数。2004年、紫綬褒章受章。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
右肩上がりの時代ではない今は、
先頭に立って道を切り開いていくよりも
最後尾で社会全体へ目配りする役割が重要ではないか。
登山に例えれば、みんなの安否を確認しつつ最後を歩く「しんがり」だ.
===================
▲鷲田さんはさらにパナソニックの創業者、
松下幸之助がリーダーに必要な条件の一つに挙げた
「後ろ姿」の魅力について解釈を加えている。
思い浮かべたのは任〓映画の高倉健だという.
▲多くは語らぬが、後ろ姿で人を引きつける。
この人は何を思い、行動しようとしているのか。
周囲の人は健さん任せではなく自分でも考えるようになる。
組織は一人一人が指示を待つのではなく、
自ら能力を発揮する時に活力にあふれる、と
▲大声で旗を振るばかりがリーダーではない。
都知事候補の後ろ姿はどうか。
至難の業かもしれないが残り1週間で何とか見極めたい。
=====================================
遺族と登る 7月25日
夫婦は20年間登山を欠かさなかった。墓標はいつも手入れが行き届いている。
「お供えものをして少し休んで…。この一時が、私たち二人にとってあの子のそばで一番幸せ」。
▼「『また来るからネ』と墓標の頭をポンとたたき、後ろ髪引かれる思いで、
涙ながら下山したものでした」。
日航ジャンボ機墜落事故の遺族らの組織「8・12連絡会」が編集した
文集『茜雲(あかねぐも)』から引用した。
筆者は、26歳の息子を失った母親である。
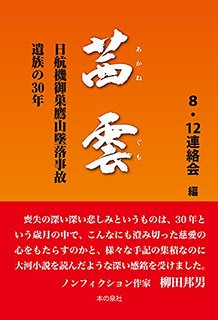
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼昨年の8月12日は、520人の命が奪われた事故から30年にあたっていた。
現場となった「御巣鷹の尾根」(群馬県上野村)への慰霊登山には、
過去最多の106家族406人が参加した。
最近は遺族でない人の姿も目立つ。広く安全を祈る「聖地」として
とらえられているようだ。
=====================
▼もともと現場までは、けわしい獣道があるだけで、
機動隊員でも3時間以上かかっていた。
突貫工事で、登山道を造ったのは地元の上野村である。
もっとも当初から応急の修理などは、日航の社員が行ってきた。
23日朝、尾根から滑落して亡くなった相馬裕さん(59)も、
今年の慰霊登山に向けて丸太のくいを打っていた。
▼10年ほど前の小紙に、遺族のサポート役を長く務めた日航社員の
インタビュー記事が載っている。
4月の山開きから11月の閉山まで登山道の整備や草刈りに励む。
1週間以上泊まり込むこともあった。
遺族の登山に同行するときは、
足元に咲く花や植物の話をして気持ちを和らげたという。
▼相馬さんは、遺族対応にあたる「ご被災者相談室長」だった。
「8・12連絡会」の美谷島(みやじま)邦子事務局長の信頼も厚かった。
9歳の次男を事故で亡くした美谷島さんは、
今年5月にも相馬さんと登ったばかりだった。・・と
====================
20年目の時に一人で走って、ようやく
慰霊の碑に手を合わせられたが・・・あれから随分と時が経つが
鮮明さは変わらない。
記事を載せる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
「俺たちはバカなのかもしれない」。
記事には2010年3月に共同通信社が行った世論調査
「次の首相にふさわしい人」の順位が載っていた.

▲「俺たち」が選んだ
3位は菅直人(かんなおと)氏(7・4%)、
2位が鳩山由紀夫(はとやまゆきお)氏(8・3%)、
1位は舛添要一(ますぞえよういち)氏(23・7%)。
★今にして思えば世論調査なんて当てにならないもんだ!
--------------------
いずれもリーダーとしての評価は芳しくなかった。
東京都知事選が31日に投票日を迎える。
今度こそふさわしい人をと思うが、
有力候補の演説は耳に心地よい内容がほとんどだ。
明確な争点も見えてこない。
▲そんな時に哲学者、鷲田清一(わしだきよかず)さんの著書「しんがりの思想」を読んだ。
強い指導者を待望して政治を「お任せ」することを戒めたうえでこう説く。

=======
やかましいほどにリーダー論、リーダーシップ論がにぎやかである。
いまの日本社会に閉塞感を感じている人はとくに、大きく社会を変えてくれるような強いリーダーを求めている。
しかし、右肩下がりの縮小社会へと歩み出した日本で本当に必要とされているのは、
登山でしんがりを務めるように後ろから皆を支えていける、または互いに助け合えるような、
フォロアーシップ精神にあふれた人である。
そしてもっとも大切なことは、いつでもリーダーの代わりが 担えるように、
誰もが準備を怠らないようにすることであると著者は説く。
人口減少と高齢化社会という日本の課題に立ち向かうためには、
市民としてどのような心もちであるべきかについて考察した一冊である。
ーーーーーーーーーーーー
鷲田清一(わしだ・きよかず)1949年、京都生まれ。
哲学者。京都市立芸術大学学長。
大阪大学名誉教授。せんだいメディアテーク館長。
専門は臨床哲学・倫理学。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。
監査委大学文学部教授、大阪大学教授、同大学文学部長、総長、大谷大学教授をへて現職。
著書に『分散する理性』『モードの迷宮』(以上2冊でサントリー学芸賞)、
『「聴く」ことの力』(桑原武夫学芸賞)、『「ぐずぐず」の理由』(読売文学賞)、
『「待つ」ということ』、『哲学の使い方』など多数。2004年、紫綬褒章受章。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
右肩上がりの時代ではない今は、
先頭に立って道を切り開いていくよりも
最後尾で社会全体へ目配りする役割が重要ではないか。
登山に例えれば、みんなの安否を確認しつつ最後を歩く「しんがり」だ.
===================
▲鷲田さんはさらにパナソニックの創業者、
松下幸之助がリーダーに必要な条件の一つに挙げた
「後ろ姿」の魅力について解釈を加えている。
思い浮かべたのは任〓映画の高倉健だという.
▲多くは語らぬが、後ろ姿で人を引きつける。
この人は何を思い、行動しようとしているのか。
周囲の人は健さん任せではなく自分でも考えるようになる。
組織は一人一人が指示を待つのではなく、
自ら能力を発揮する時に活力にあふれる、と
▲大声で旗を振るばかりがリーダーではない。
都知事候補の後ろ姿はどうか。
至難の業かもしれないが残り1週間で何とか見極めたい。

=====================================
遺族と登る 7月25日
夫婦は20年間登山を欠かさなかった。墓標はいつも手入れが行き届いている。
「お供えものをして少し休んで…。この一時が、私たち二人にとってあの子のそばで一番幸せ」。
▼「『また来るからネ』と墓標の頭をポンとたたき、後ろ髪引かれる思いで、
涙ながら下山したものでした」。
日航ジャンボ機墜落事故の遺族らの組織「8・12連絡会」が編集した
文集『茜雲(あかねぐも)』から引用した。
筆者は、26歳の息子を失った母親である。

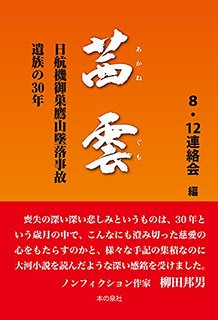
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼昨年の8月12日は、520人の命が奪われた事故から30年にあたっていた。
現場となった「御巣鷹の尾根」(群馬県上野村)への慰霊登山には、
過去最多の106家族406人が参加した。
最近は遺族でない人の姿も目立つ。広く安全を祈る「聖地」として
とらえられているようだ。
=====================
▼もともと現場までは、けわしい獣道があるだけで、
機動隊員でも3時間以上かかっていた。
突貫工事で、登山道を造ったのは地元の上野村である。
もっとも当初から応急の修理などは、日航の社員が行ってきた。
23日朝、尾根から滑落して亡くなった相馬裕さん(59)も、
今年の慰霊登山に向けて丸太のくいを打っていた。
▼10年ほど前の小紙に、遺族のサポート役を長く務めた日航社員の
インタビュー記事が載っている。
4月の山開きから11月の閉山まで登山道の整備や草刈りに励む。
1週間以上泊まり込むこともあった。
遺族の登山に同行するときは、
足元に咲く花や植物の話をして気持ちを和らげたという。
▼相馬さんは、遺族対応にあたる「ご被災者相談室長」だった。
「8・12連絡会」の美谷島(みやじま)邦子事務局長の信頼も厚かった。
9歳の次男を事故で亡くした美谷島さんは、
今年5月にも相馬さんと登ったばかりだった。・・と
====================
20年目の時に一人で走って、ようやく
慰霊の碑に手を合わせられたが・・・あれから随分と時が経つが
鮮明さは変わらない。




























