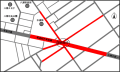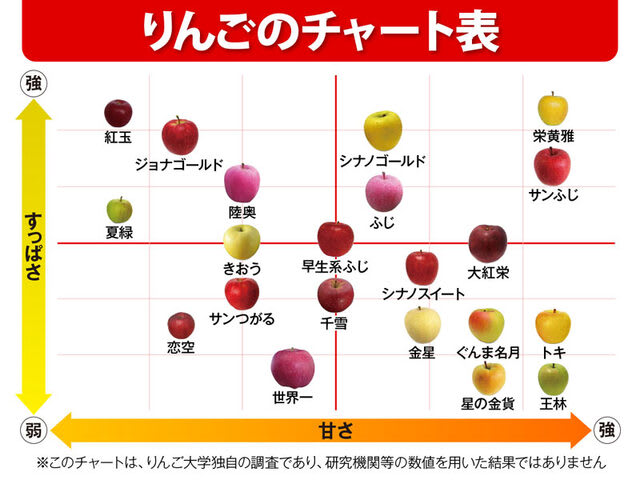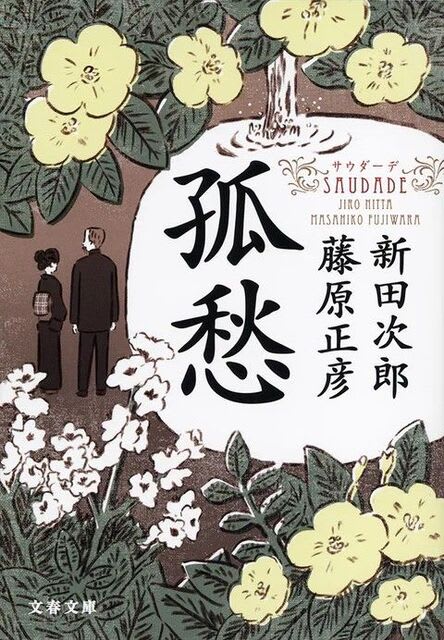2025 1月31日 (金曜日) ②
足慣らしで行田の古墳公園と古代蓮の里を歩いて来た。

丸墓山の上から富士山を望む。

忍城も拡大してみると

随分遠くに見える。・・
===============
古代蓮の里には10時半頃には着いて
今が盛りの蝋梅の花を撮る。

良い匂いがしている。



本当に蝋細工だなあ~
~~~~~~~~~~~~~~
梅の花は蕾がまだ固い。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
帰宅前に精米を済ませ、郵便局に寄ってお年玉記念切手をいただいてきた。

絵柄が単調な気がする。
==============
忙しくお昼を済ませて
東小学校の感謝の集いに出かける。

”通学時の子供を見守る隊や防犯で青色パトロール”の
ボランティア活動に対しての学校側の感謝のイベントである。
年々の高齢化で人手も不足気味だ。
全校生徒が体育館に集まって挨拶をしてくれた。

校長が”子供の挨拶の出来具合”についてデータをとったのを発表していた。
子供は60%以上がしているというデータ。
父兄から見ると30%ほどがしていると・・
恥ずかしさもあるのか声が小さいと挨拶が伝わらないよ・・・と
==================
社会に出てから顧問の先生から教えてもらった!
”挨拶は人生の通行手形”
足慣らしで行田の古墳公園と古代蓮の里を歩いて来た。


丸墓山の上から富士山を望む。

忍城も拡大してみると

随分遠くに見える。・・
===============
古代蓮の里には10時半頃には着いて
今が盛りの蝋梅の花を撮る。


良い匂いがしている。




本当に蝋細工だなあ~

~~~~~~~~~~~~~~
梅の花は蕾がまだ固い。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
帰宅前に精米を済ませ、郵便局に寄ってお年玉記念切手をいただいてきた。

絵柄が単調な気がする。
==============
忙しくお昼を済ませて
東小学校の感謝の集いに出かける。

”通学時の子供を見守る隊や防犯で青色パトロール”の
ボランティア活動に対しての学校側の感謝のイベントである。
年々の高齢化で人手も不足気味だ。
全校生徒が体育館に集まって挨拶をしてくれた。

校長が”子供の挨拶の出来具合”についてデータをとったのを発表していた。
子供は60%以上がしているというデータ。
父兄から見ると30%ほどがしていると・・
恥ずかしさもあるのか声が小さいと挨拶が伝わらないよ・・・と
==================
社会に出てから顧問の先生から教えてもらった!
”挨拶は人生の通行手形”