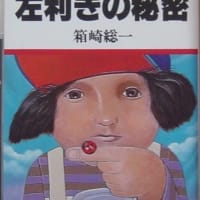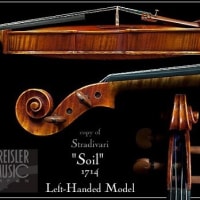いつも左利き関連の話題を提供してくださるガボちゃんのブログで見た情報から。
2014年版利き手テストだそうです
日本語版FLANDERS利き手テスト
「日本語版FLANDERS 利き手テスト―信頼性と妥当性の検討―」
(大久保 街亜 鈴木 玄 専修大学 Nicholls, Michael E. R. Flinders University)
↑の論文によりますと、なぜ利き手の検査が必要か、といいますと、心理学や神経科学の研究において必要だから、といいます。
それらの研究において、なぜ必要になるのか、その理由は、といいますと、第一に《利き手が脳の機能や構造と関連するため》であり、第二に《利き手は多くの心理機能に関連する》ためでもあります。
また、第三に《手の運動に関わる現象や心理機能(例えば,リーチング)に興味がある場合,実験状況の統制のため》あらかじめ調べる必要がある、といいます。
利き手の検査には様々な種類があり、そのなかで比較的少数の項目からなる質問紙形式のものが最も利用されていて、それは、《相対的に見て,高い正確さと簡便さを兼ね備える》ものだから。
従来最もよく利用され、文献に引用されてきたものとしては、《Oldfield(1971)によるEdinburgh 利き手テスト》がある。
しかし、この利き手テストには、不都合な点が見られる。
たとえば、使われる項目の中に現在はあまり使われない動作があったり、そもそもの利き手因子の解釈に問題があったり、等。
そこで、新たに、このエディンバラEdinburgh 利き手テストの問題点を考慮した、利き手テストが考案された。
それが、Nicholls et al.(2013)による「FLANDERS 利き手テスト」で、今回その日本語版ができたというのです。
《字を書く,絵を描くなど片手で行う熟達化した動作を問う項目が含まれてい》て、
《FLANDERS 利き手テストの成績はタッピング課題成績の左右差と高い正の相関があ》り、《また,目,足,耳の機能における左右差とも正の相関があった。これらの高い相関が示す左右差の一致は,FLANDERS 利き手テストに高い基準関連妥当性があることを示す》という。
しかしこれはオーストラリアで開発されたものであり、文化の異なる日本人の利き手測定に適切かどうか、という疑問があった。
日本人向けには、八田・中塚(1975)による「H・N 利き手テスト」がよく使用されている。
けれども、このテストは海外での認知度が低く、国際的な比較において問題点がある。
そこで、この新しく開発された「FLANDERS 利き手テスト」の日本語版を作成することにしたという。
この翻訳版を基に現代の日本人大学生を調査対象者に実施。
既存の上記二つのテストと比較する、再テストを実施する等《信頼性と妥当性について新たな検討を行った》結果、日本語版ができ上がったと言います。
難しい話は割愛し、付録として紹介されている「フランダース利き手テスト」の概要を転載しておきます。
フランダース利き手テスト(FLANDERS)
一つ弱いと感じるところは、項目の中に《たとえ経験がなくとも,その場面や課題を想像し回答》しろ、というくだりでしょうか。
過去のデータとの比較するために必要なのかもしれませんが、弱点の一つではあるように思います。
まあ、そもそもこの手の質問紙による調査の場合、本人の意識と実際の動作との整合性に疑問が感じられるケースも少なくありません。
特に、弱い左利き傾向を持つ人の場合、意識とのずれが見られることが多々あります。
自分では右利きのつもりでいるため、なんにでも右と答えてしまう傾向が。
もちろん、それらも統計学的な計算の内に入っているのでしょうけれど。
--
※本稿は、ココログ版『レフティやすおのお茶でっせ』より
「2014年版利き手テスト:日本語版フランダースFLANDERS利き手テスト」を転載したものです。
(この記事へのコメント・トラックバックは、転載元『お茶でっせ』のほうにお願い致します。ただし承認制になっていますので、ただちに反映されません。ご了承ください。)
--
2014年版利き手テストだそうです
日本語版FLANDERS利き手テスト
「日本語版FLANDERS 利き手テスト―信頼性と妥当性の検討―」
(大久保 街亜 鈴木 玄 専修大学 Nicholls, Michael E. R. Flinders University)
↑の論文によりますと、なぜ利き手の検査が必要か、といいますと、心理学や神経科学の研究において必要だから、といいます。
それらの研究において、なぜ必要になるのか、その理由は、といいますと、第一に《利き手が脳の機能や構造と関連するため》であり、第二に《利き手は多くの心理機能に関連する》ためでもあります。
また、第三に《手の運動に関わる現象や心理機能(例えば,リーチング)に興味がある場合,実験状況の統制のため》あらかじめ調べる必要がある、といいます。
利き手の検査には様々な種類があり、そのなかで比較的少数の項目からなる質問紙形式のものが最も利用されていて、それは、《相対的に見て,高い正確さと簡便さを兼ね備える》ものだから。
従来最もよく利用され、文献に引用されてきたものとしては、《Oldfield(1971)によるEdinburgh 利き手テスト》がある。
しかし、この利き手テストには、不都合な点が見られる。
たとえば、使われる項目の中に現在はあまり使われない動作があったり、そもそもの利き手因子の解釈に問題があったり、等。
そこで、新たに、このエディンバラEdinburgh 利き手テストの問題点を考慮した、利き手テストが考案された。
それが、Nicholls et al.(2013)による「FLANDERS 利き手テスト」で、今回その日本語版ができたというのです。
《字を書く,絵を描くなど片手で行う熟達化した動作を問う項目が含まれてい》て、
《FLANDERS 利き手テストの成績はタッピング課題成績の左右差と高い正の相関があ》り、《また,目,足,耳の機能における左右差とも正の相関があった。これらの高い相関が示す左右差の一致は,FLANDERS 利き手テストに高い基準関連妥当性があることを示す》という。
しかしこれはオーストラリアで開発されたものであり、文化の異なる日本人の利き手測定に適切かどうか、という疑問があった。
日本人向けには、八田・中塚(1975)による「H・N 利き手テスト」がよく使用されている。
けれども、このテストは海外での認知度が低く、国際的な比較において問題点がある。
そこで、この新しく開発された「FLANDERS 利き手テスト」の日本語版を作成することにしたという。
この翻訳版を基に現代の日本人大学生を調査対象者に実施。
既存の上記二つのテストと比較する、再テストを実施する等《信頼性と妥当性について新たな検討を行った》結果、日本語版ができ上がったと言います。
難しい話は割愛し、付録として紹介されている「フランダース利き手テスト」の概要を転載しておきます。
フランダース利き手テスト(FLANDERS)
《これからさまざまな場面で,あなたが左右どちらの手を使うか質問します。下に示した10 項目のそれぞれについて表の右はしにある選択肢「左」,「どちらも」,「右」の一つにマル(○)をつけて回答してください。「どちらも」の選択肢は,左右の手を全く同じくらい使う場合のみ選択してください。すべての項目に回答してください。10 項目のなかには,あなたにとってほとんど経験がないことがあるかもしれません。たとえ経験がなくとも,その場面や課題を想像し回答してください。
1 文字を書くとき,ペンをどちらの手で持ちますか?
2 食事のとき,スプーンをどちらの手で持ちますか?
3 歯をみがくとき,歯ブラシをどちらの手で持ちますか?
4 マッチをするとき,マッチの軸をどちらの手で持ちます
か?
5 消しゴムで文字を消すとき,消しゴムをどちらの手で持って消しますか?
6 縫いものをするとき,針をどちらの手で持って使いますか?
7 パンにバターをぬるとき,ナイフをどちらの手で持ちますか?
8 クギを打つとき,カナヅチをどちらの手で持ちますか?
9 リンゴの皮をむくとき,皮むき器をどちらの手で持ちますか?
10 絵を描くとき,ペンや筆をどちらの手で持ちますか?》
一つ弱いと感じるところは、項目の中に《たとえ経験がなくとも,その場面や課題を想像し回答》しろ、というくだりでしょうか。
過去のデータとの比較するために必要なのかもしれませんが、弱点の一つではあるように思います。
まあ、そもそもこの手の質問紙による調査の場合、本人の意識と実際の動作との整合性に疑問が感じられるケースも少なくありません。
特に、弱い左利き傾向を持つ人の場合、意識とのずれが見られることが多々あります。
自分では右利きのつもりでいるため、なんにでも右と答えてしまう傾向が。
もちろん、それらも統計学的な計算の内に入っているのでしょうけれど。
--
※本稿は、ココログ版『レフティやすおのお茶でっせ』より
「2014年版利き手テスト:日本語版フランダースFLANDERS利き手テスト」を転載したものです。
(この記事へのコメント・トラックバックは、転載元『お茶でっせ』のほうにお願い致します。ただし承認制になっていますので、ただちに反映されません。ご了承ください。)
--