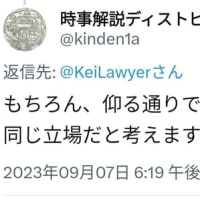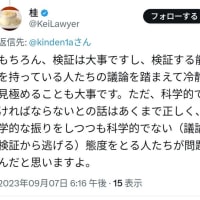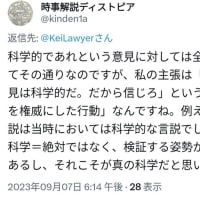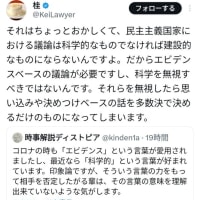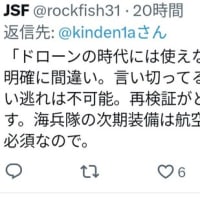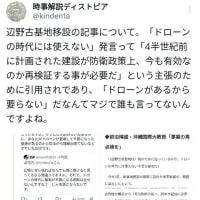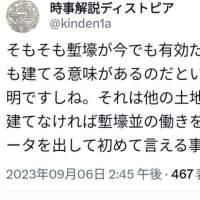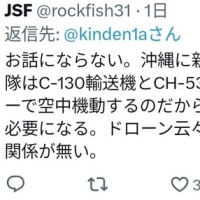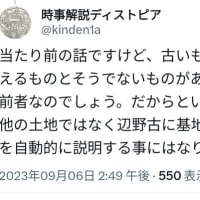作家のヴァレンチン・ラスプーチン氏が、モスクワで死去した。77歳だった。
孫のアントニーナさんが、リア・ノーヴォスチ通信に伝えた。
ラスプーチン氏は、「マチョーラとの別れ」、
「フランス語の授業」、「最終期限」など、その他数多くの作品で知られている。
ラスプーチン氏は1937年3月15日にイルクーツク州ウスチ・ウジンスキー地区アタランカで生まれた。
ラスプーチン氏は社会主義労働英雄で、2012年には国家賞授与された。
続きを読む: http://japanese.ruvr.ru/news/2015_03_15/283339251/
----------------------------------------------------------------
アフリカ文学や朝鮮文学がポスト・コロニアリズム研究の材料として利用される一方で、
ロシア文学は、逆に反共・反ソの材料としてしか紹介されない傾向がある。
私が知る限り、日本語で読めるソ連文学の多くは、反体制派の作家の作品ばかりだ。
そこには、したり顔で文学者がソ連批判をするだけのつまらない解説が添えられている。
結局そのような言説は列強の冷戦史観(悪のソ連が滅び正義の時代が訪れる歴史)
を正当化させるだけのものであり、実にいい加減な内容になっている。
現に、市民も参加する研究会によって、その解説・翻訳の胡散臭さを暴露されている人間もいる。
亀山郁夫著『謎とき『悪霊』』の虚偽を問う
― テクストの軽視と隠蔽、あるいは、詐術と談合 ―
(または、「マトリョーシャ=マゾヒスト説」の崩壊)
商品としてのドストエフスキー
-商業出版とマスメディアとにおける作家像-
亀山教授は日本のロシア文学業界で中心となって活躍している方で、
彼の言説を知ることで日本のロシア文学研究の水準を見極める指標にもなる。
ゴーゴリの新訳に対して私は以前、「ロシア文学の洗浄作業」といって酷評した。
ゴーゴリに限らず、最近の文学者は新訳と称して手前勝手な解釈を刷り込ませており、
正直、その翻訳のレベルも神西清氏や中村融氏といった過去の名訳者に遠く及ばない。
ここで、イギリス文学やフランス文学の翻訳状況に目を向けてみると、
植民地支配や戦後の独立運動に対する弾圧を批判する小説はなぜかメジャーになっていない。
ドイツ・イタリア文学でもナチスやファシスト政権を批判する文学はなぜか傍流だ。
アメリカ文学に至ってもキング牧師のような融和的活動家の翻訳書は岩波にはあるが、
マーカス・ガーヴェイやマルコムXのような対決的な運動家の本はなぜか翻訳されていない。
欧米の文学はむしろ、大衆文学の翻訳がメジャーで、
向こうの価値観が知らず知らずのうちに読者の脳にしみとおる様に作られている。
他方、ソ連や東欧、中国の小説は反体制派の本ばかりが翻訳され、
いかにこの国がろくでもない国であるかを読者に説明するものになっている。
真のプロパガンダとは、「本当は正しかった日本」だとか
「薄汚い国韓国」とかいった威勢のいい負け犬の遠吠え書籍ではなく、
むしろそれがプロパガンダとは決して思わせない透明感のあるものなのだと言えよう。
そういう中で、ワレンチン・ラスプーチンの作品は
プロパガンダ翻訳活動の波の中で珍しく発掘されたポスト冷戦を描いたものである。
そこでは冷戦が終わり、ソ連が否定された後に、時代に馴染めず翻弄される人間を描かれている。
実際、ソ連崩壊後のロシアは国の財産を新興財閥が収奪し、
そこからさらに欧米に資本が流出されるという非道い有様に陥った。
新興財閥の個人的利益と引き換えに、国や社会は疲弊し、多くの人間が貧窮したのである。
この時期、西側諸国は悪の帝国を葬り去ったことに小躍りし、
西側の左翼は、そそくさと手のひらを返し、反共主義者たちの犬となり餌をねだった。
抵抗者たちが自発的に解散を宣言し、権力者に服従し、弱体化した結果、
新自由主義が浸透し、中東・アフリカに軍が侵攻し、国内の貧困者が増大した。
その癌は、冷戦終結後、20年が経った現在になり、いよいよ勢いを増すばかりだ。
当然ながら、敵に降伏するだけでは飽き足らず、
味方を売り、時にはかつての仲間の虐殺作戦に参加したこの人殺しどもは、
現状の責任は自分たちにもあるという反省をしていない。しようともしない。
私は、常々ポストコロニアリズム研究はソ連や中国を対象にされるべきものだと思う。
冷戦時、ソ連は西側の敵としてありとあらゆる悪魔化がされてきた。ちょうど今の北朝鮮のように。
しかし、振り返ってみると、ペレストロイカは果たして本当に手放しに礼賛できるものだったのか?
冷戦終結は、新しい春をもたらしたのか?冷戦後20年たった今をみると、とてもそうは思えない。
どちらの事件も西側にとっては非常に喜ばしいものだったが、
東側にとって、それは必ずしも良いものだけではなかったのではないか?
ラスプーチンの小説を読むと、ペレストロイカを当初は喜びながらも、
やがてそれがもたらすものに悩まされる農民や町民の姿が描かれている。
私たちは今こそ、ラスプーチンのような本を読み、
西側の都合のよい歴史観から脱却すべきではないだろうか?
孫のアントニーナさんが、リア・ノーヴォスチ通信に伝えた。
ラスプーチン氏は、「マチョーラとの別れ」、
「フランス語の授業」、「最終期限」など、その他数多くの作品で知られている。
ラスプーチン氏は1937年3月15日にイルクーツク州ウスチ・ウジンスキー地区アタランカで生まれた。
ラスプーチン氏は社会主義労働英雄で、2012年には国家賞授与された。
続きを読む: http://japanese.ruvr.ru/news/2015_03_15/283339251/
----------------------------------------------------------------
アフリカ文学や朝鮮文学がポスト・コロニアリズム研究の材料として利用される一方で、
ロシア文学は、逆に反共・反ソの材料としてしか紹介されない傾向がある。
私が知る限り、日本語で読めるソ連文学の多くは、反体制派の作家の作品ばかりだ。
そこには、したり顔で文学者がソ連批判をするだけのつまらない解説が添えられている。
結局そのような言説は列強の冷戦史観(悪のソ連が滅び正義の時代が訪れる歴史)
を正当化させるだけのものであり、実にいい加減な内容になっている。
現に、市民も参加する研究会によって、その解説・翻訳の胡散臭さを暴露されている人間もいる。
亀山郁夫著『謎とき『悪霊』』の虚偽を問う
― テクストの軽視と隠蔽、あるいは、詐術と談合 ―
(または、「マトリョーシャ=マゾヒスト説」の崩壊)
商品としてのドストエフスキー
-商業出版とマスメディアとにおける作家像-
亀山教授は日本のロシア文学業界で中心となって活躍している方で、
彼の言説を知ることで日本のロシア文学研究の水準を見極める指標にもなる。
ゴーゴリの新訳に対して私は以前、「ロシア文学の洗浄作業」といって酷評した。
ゴーゴリに限らず、最近の文学者は新訳と称して手前勝手な解釈を刷り込ませており、
正直、その翻訳のレベルも神西清氏や中村融氏といった過去の名訳者に遠く及ばない。
ここで、イギリス文学やフランス文学の翻訳状況に目を向けてみると、
植民地支配や戦後の独立運動に対する弾圧を批判する小説はなぜかメジャーになっていない。
ドイツ・イタリア文学でもナチスやファシスト政権を批判する文学はなぜか傍流だ。
アメリカ文学に至ってもキング牧師のような融和的活動家の翻訳書は岩波にはあるが、
マーカス・ガーヴェイやマルコムXのような対決的な運動家の本はなぜか翻訳されていない。
欧米の文学はむしろ、大衆文学の翻訳がメジャーで、
向こうの価値観が知らず知らずのうちに読者の脳にしみとおる様に作られている。
他方、ソ連や東欧、中国の小説は反体制派の本ばかりが翻訳され、
いかにこの国がろくでもない国であるかを読者に説明するものになっている。
真のプロパガンダとは、「本当は正しかった日本」だとか
「薄汚い国韓国」とかいった威勢のいい負け犬の遠吠え書籍ではなく、
むしろそれがプロパガンダとは決して思わせない透明感のあるものなのだと言えよう。
そういう中で、ワレンチン・ラスプーチンの作品は
プロパガンダ翻訳活動の波の中で珍しく発掘されたポスト冷戦を描いたものである。
そこでは冷戦が終わり、ソ連が否定された後に、時代に馴染めず翻弄される人間を描かれている。
実際、ソ連崩壊後のロシアは国の財産を新興財閥が収奪し、
そこからさらに欧米に資本が流出されるという非道い有様に陥った。
新興財閥の個人的利益と引き換えに、国や社会は疲弊し、多くの人間が貧窮したのである。
この時期、西側諸国は悪の帝国を葬り去ったことに小躍りし、
西側の左翼は、そそくさと手のひらを返し、反共主義者たちの犬となり餌をねだった。
抵抗者たちが自発的に解散を宣言し、権力者に服従し、弱体化した結果、
新自由主義が浸透し、中東・アフリカに軍が侵攻し、国内の貧困者が増大した。
その癌は、冷戦終結後、20年が経った現在になり、いよいよ勢いを増すばかりだ。
当然ながら、敵に降伏するだけでは飽き足らず、
味方を売り、時にはかつての仲間の虐殺作戦に参加したこの人殺しどもは、
現状の責任は自分たちにもあるという反省をしていない。しようともしない。
私は、常々ポストコロニアリズム研究はソ連や中国を対象にされるべきものだと思う。
冷戦時、ソ連は西側の敵としてありとあらゆる悪魔化がされてきた。ちょうど今の北朝鮮のように。
しかし、振り返ってみると、ペレストロイカは果たして本当に手放しに礼賛できるものだったのか?
冷戦終結は、新しい春をもたらしたのか?冷戦後20年たった今をみると、とてもそうは思えない。
どちらの事件も西側にとっては非常に喜ばしいものだったが、
東側にとって、それは必ずしも良いものだけではなかったのではないか?
ラスプーチンの小説を読むと、ペレストロイカを当初は喜びながらも、
やがてそれがもたらすものに悩まされる農民や町民の姿が描かれている。
私たちは今こそ、ラスプーチンのような本を読み、
西側の都合のよい歴史観から脱却すべきではないだろうか?