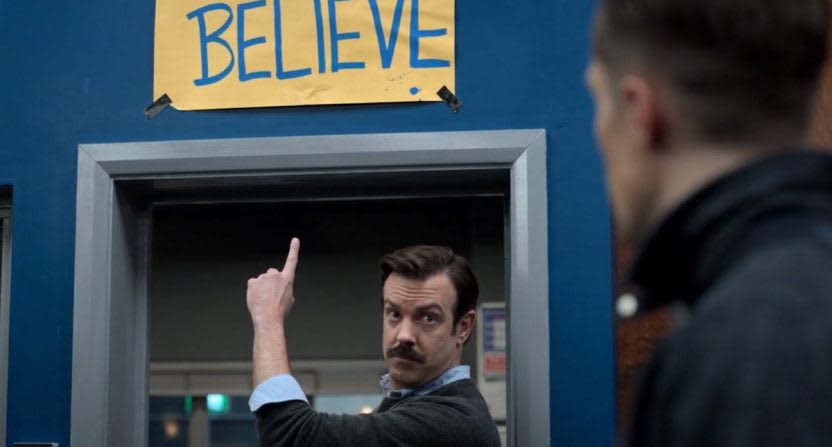【MOVIE】
監督 デヴィッド・フィンチャー
監督 ダリウス・マーダー
監督 ピート・ドクター
監督 スパイク・リー
監督 黒沢清
監督 アーロン・ソーキン
監督 セリーヌ・シアマ
監督 チャーリー・カウフマン
監督 荒木伸二
監督 クリストファー・ノーラン
監督 パティ・ジェンキンス
今年も原則、同年ワールドリリースを基準に選出した。2020年はコロナショックによって世界中の映画ファンがほぼ同条件で新作を視聴できた年ではないだろうか。上半期に日本でも大ヒットを記録したアカデミー作品賞受賞作『パラサイト』については2019年中に鑑賞しているため2019年ベスト10の項を、その他上半期公開の2019年傑作群については2020年上半期ベスト10を参照してもらいたい。
【TV SHOW】
監督 スコット・フランク
監督 デレク・シアンフランス
4、『ウォッチメン』
製作 デイモン・リンデロフ
製作 ジョン・ファヴロー
製作 ピーター・モーガン
監督 マリア・シュラーダー
監督 マーク・マイロッド、他
監督 トーマス・ケイル
製作 ノア・ホーリー
2020年中のシーズン完走を基準に選出しているため、スターチャンネルでリアタイ視聴中の『ラヴクラフトカントリー』は見送った。トランプ支持者による米連邦議会占拠の光景を見た今、『ウォッチメン』に順位をつけたことはナンセンスだったと思っている。実に予見的であり、時代を象徴する傑作だ。
TVシリーズは力強いナラティヴの作品に魅せられた。『ベター・コール・ソウル』は映画も含めた2020年最高の1本。ストリーミング作品を中心にハイコンテクスト化が進む中、『クイーンズ・ギャンビット』の王道的ストーリーテリングがここ日本も含め、世界を制したことは重要だろう(もっとも原作ウォルター・テヴィスの作家性は見過ごされがちではある)。映画監督のTVシリーズ進出は続き、デレク・シアンフランスは『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』でキャリアを更新した。
【アートフォームの激変・海外映画が入ってこない】
上半期ベスト10の項でも触れたように、新型コロナウィルスの影響によってハリウッドはほぼ全ての作品が公開延期を余儀なくされ、今なお多くの映画館が休業状態にある。
この状況を打破すべく、クリストファー・ノーラン監督が長年のホームグラウンドであるワーナーブラザースを説得し、新作『テネット』を劇場公開。日本を含む感染状況が収束傾向にあった地域で公開され、久々の大作アクション映画としてヒットを記録した。しかし、それでも製作費を補填できるほどの成功には至らなかった。
この結果を受け、ワーナーは年末公開となった『ワンダーウーマン1984』から2021年の新作全てを、自社のストリーミングサービスHBOMaxで劇場公開日と同日、追加料金なしでストリーミング配信すると発表した。未だ終わりが見えないコロナ禍において苦肉の策と言えなくもないが、ワーナーがノーランはじめとするクリエイター陣に何の相談もしていなかった事がさらなる波紋を拡げている。クリエイターの多くが興行収益の数パーセントから報酬を得る契約をしていること、何より大スクリーンと良質な音響(今年、ストリーミング視聴で一番困ったのは我が家の貧弱なオーディオと住宅環境だ)で見ることを前提に作られた映画が、スマートフォンの画面に送られることの反感は察して余りある。そして映画は劇場で多くの観客が同時に見る共有体験、文化だ。アメリカの大手劇場チェーンAMCは経営危機を発表しており今後、多くの劇場が倒産、閉鎖を余儀なくされるだろう。これが1年間の緊急措置だとしても、もう後戻りはできないのだ。
HBOMaxは日本未上陸だが(上陸間近という噂はまことしやかに流れている)、アメリカの現状は決して対岸の火事ではない。ディズニーは『ムーラン』、『ソウルフル・ワールド』を自社サービス“ディズニープラス”へスルーした。いずれも1年以上前から劇場で予告編が公開され、夏冬興行の目玉作品と目されていただけに市場には大きな穴が開いた格好だ(20年に1本級のヒット作である“鬼滅”がなければ日本の映画興行も悲惨なことになっていただろう)。
こんな事が続けば日本に入ってくる海外映画は少なくなる一方だ。シネコンのスケジュールをチェックしてみてほしい。既に海外映画はほとんどかかっていない。例年、アカデミー賞をにらんだ傑作群で渋滞する春の公開スケジュールも何とも閑散としたものだ。
そしてこれを書いている今、東京都をはじめとする首都圏には緊急事態宣言が発せられており、劇場には夜8時以降の営業自粛が無補償で求められている。
【ハイコンテクスト化とガイドの不在】
劇場公開作がない年にベスト10を挙げる意味はあるのか?もちろん、ある。ネットの海は広大で、積極的に情報収集をしなければ作品と出会うことはままならない。何より“ハイコンテクスト化”した現代の作品には手引きが必要だ。今年からストリーミングサービスに手を出し始めた人は少なくないだろう。複雑で、知的好奇心を刺激する作品群に興奮を覚えたのではないだろうか。
ベスト1にはデヴィッド・フィンチャー監督『マンク』を挙げる。前述のワーナー騒動に対して既にフィンチャーは背を向け、Netflixと4年間の独占契約を結んでいた。『マンク』は『市民ケーン』の脚本家マンクを通じたハリウッドシステムへのアンチテーゼであり、幾重ものコンテクストが張り巡らされた重層的な作品だ。このストーリーテリングはフィンチャー自身が『ハウス・オブ・カード』で起爆させた現在のPeakTVから継承したものである。2010年代後半、フェミニズムやBlack Lives Matterなど、あらゆる社会的イシューを包括したTVシリーズは“わかりやすさ”だけを良しとせず、従来のワンクール10数話、1話60分という連続TVのフォーマットも解体。ついには物語の連続性を無視し、コンテクストのために構築された『ラヴクラフトカントリー』に到達する。
2020年、アメリカは歴史的大統領選挙を迎え、トランプへのカウンターとして隆盛したアメリカ映画の気迫は極まった。スパイク・リーの怒りみなぎる『ザ・ファイブ・ブラッズ』を皮切りに長年、製作が噂されていた『シカゴ7裁判』が投票時期に照準を定めて登場。この作品に出演したサシャ・バロン・コーエンは2016年の大ヒット作『ボラット』の続編を発表し、コロナもトランプ支持者も陰謀論者も徹底的に笑い飛ばしてオルタナティブを再証明した。
シーズン4に突入したTVドラマ『ザ・クラウン』は80年代のサッチャー政権をモチーフに、現代の規範なき政治を批評。政治が自助を掲げるここ日本には特に痛烈なシーズンであった。当の日本では『スパイの妻』『人数の町』が窒息寸前の社会の空気を捉え、いよいよこの国は危険水域にあるのかと戦慄させられた。
ネオウーマンリヴ映画も1つの区切りを迎えている。男性登場人物を排し、男女の対立軸から脱した『燃ゆる女の肖像』は2010年代後半、Me tooを皮切りにした一連の流れに一旦の終止符を打ち、新たなフェーズへと導いた。ソフィア・コッポラは盟友でもあるビル・マーレイにリスペクトを捧げながら、『オン・ザ・ロック』で“チョイワル親父”をたしなめた。FX製作のドラマ『フォッシー&ヴァードン』は伝説的巨匠ボブ・フォッシーが、妻でありミュージカル女優のグウェン・バードンを搾取したかのようにも見えるが、ドラマの本質は偉大なアーティスト2人の共鳴であり、ドラマはキャンセルカルチャーを回避することに成功している(傑作にも係わらず、日本ではWOWOWでひっそりと吹き替え版だけが放映された)。女性が自己承認を確立するまでを描いたハードボイルド『アイム・ユア・ウーマン』はあまり話題にならず、寂しい限り。古典ホラーを蘇らせた『透明人間』は、コロナショック直前にメガヒットを記録した最後のフェミニズムホラーである。
昨年、お通夜のようなフィナーレを迎えたスター・ウォーズシリーズは『マンダロリアン』でフォースのバランスを取り戻し、トキシックファンダムの暗黒面から脱した。『ブレイキング・バッド』『ゲーム・オブ・スローンズ』らTVシリーズのニュースタンダードを経由し、2020年代のポップカルチャーとしての再創造が始まった。元来、スターウォーズとは日本の時代劇や西部劇、戦争映画ら多くのジャンル映画にオマージュを捧げ、ベトナム戦争やイラク戦争、ジョージ・ルーカス自身の父子問題を絡めたハイコンテクストなポップカルチャーだった。 同時に今のディズニーからは20世紀フォックスの買収により傘下となったFX製作、マーベル『レギオン』のような大胆で、奇妙奇天烈な作品は出てくる余地はないだろうと思っている。間もなく配信されるMCUオリジナルドラマ『ワンダヴィジョン』に微かな“レギオン味”を感じはするのだが…。
コロナが終息した後、おそらくハリウッドは今まで以上にブロックバスターの製作に偏重し、一方でクリエイターの創造性が優先されるオリジナルストリーミング作品はよりハイコンテクスト化する二極化に至るだろう。そういう意味でもここで『マンク』を記録することは重要なのだ。
【ベストアクト】
2020年は日本で『ミッドサマー』が大ヒット、『ストーリー・オブ・マイライフ』がアカデミー賞にノミネートされたフローレンス・ピューのブレイク元年となった。これでスカーレット・ヨハンソンの後を継ぐと噂されている『ブラック・ウィドウ』が公開されていれば、その人気は決定的なものとなっただろう。10月には実質デビュー作の『レディ・マクベス』がわずか1週間の限定上映ながらようやく日本初お披露目。1日1回上映のレイトショーには女性客を中心に多くのファンが集まっていた。 映画ファンにとっては今やすっかり怪優扱いのロバート・パティンソンが『テネット』で再びイケメン枠に戻ってきたことも嬉しい驚きだった。ほぼ同時期にNetflixでリリースされた『悪魔はいつもそこに』ではド外道牧師を相変わらず怪演しており、安定のキャリアコントロールである。この快進撃はバットマンを演じる最新作で1つのピークに到達するだろう。
何度も言ってきたことだが、今や監督・俳優のベストワークはTVシリーズやストリーミング作品にあり、ここにも映画と配信の二極化がある。アクション俳優を卒業したヒュー・ジャックマンはHBO映画『バッド・エデュケーション』で新境地を開拓。10年弱、マーベルにキャリアを費やしたマーク・ラファロは『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』で最高の名演を披露し、男女の賃金格差問題でその不当な扱いが明らかになったミシェル・ウィリアムズは『フォッシー&ヴァードン』で大女優への階段をまた1つ上がった。
2020年を象徴するのが、アニャ・テイラー・ジョイの大ブレイクだろう。これまで『ウィッチ』や『スプリット』など代表作はあったものの、若手スター予備軍の域を出なかった彼女がNetflixの主演ドラマ『クイーンズ・ギャンビット』の世界的大ヒットにより、ついにスターダムへと上り詰めた。TVシリーズを経由してスターが生まれるのもストリーミングがメインストリームとなった2020年ならではだろう。今後、この現象はさらに加速していくのではないか 。
そう、新たな才能はストリーミングから発見される時代だ。『ブックスマート』が話題になったケイトリン・デヴァーは同年、Netflixのミニシリーズ『アンビリーバブル』でシリアス演技を披露。キュートなルックスと体当たりの演技が注目のヴィクトリア・ペドレッティは怪作『YOU』シーズン2を牽引し、出世作のシリーズ第2弾『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』で堂々の主演を果たした。『オザークへようこそ』シーズン3の立役者とも言えるトム・ペルフリーはさっそく『マンク』に出演。マンクの弟で、後の巨匠ジョゼフ・L・マンキーウィッツを演じている。いずれも名前を覚えておきたい若手だ。 ここで筆を置こう。2020年はコロナショックによって筆者も本業の舞台が休業となり、人生で最も多く映画やTVシリーズを見た1年だった。見ていて当然、とも言える名作クラシックにも多く触れることができたし、そういう意味で映画ファンは一生分の宿題がある。
今年は感染終息後をにらんで創作に打ち込みたいので、本数を少し控えたいと思っているのだが…(毎年言ってますね、ハイ)。