
詳しく調べてみると赤い靴の女の子みきの北海道(函館)に上陸後、次のような
諸説があるということがわかった・・・
ひとつは、母と子がそろって留寿都の農場に入植したものの、留寿都での農場生活が
あまりにも過酷だった。そのため、「食いぶち」を減らすため娘のきみは函館の宣教師
ヒュエット夫妻の養女として託された・・という説
もうひとつは、わずか3歳の女の子が、当時の交通事情で静岡から北上、それは、
あまりにも過酷なものであり、案の定、函館に上陸した時点で体力がかなり衰弱、
娘の衰弱した姿を見た母親は、きみを留寿都まで同行させることを断念・・・
函館の教会に奉仕していたアメリカ人宣教師ヒュエット夫妻に託したという説
このように、当時3歳のきみが留寿都までたどり着くことができたのか?
それとも、上陸した函館で母子の別れがあったのかは不明である
いずれにせよ、母の「かよ」は、後ろ髪を引かれる思いでやむなく娘を函館在住の
アメリカ人宣教師ヒュエット夫妻の養女として託し、その後も母は、幼い娘のことを
1日たりとも忘れたことはなかったという・・・
さて、夫の志郎と共に希望に燃えて入植したものの秋の実りは少なく、仲間の病死や
火災による被害などが相次ぎ、僅か2年で開拓村は解散する
失意の「かよ」は志郎との間に生まれた娘と共に札幌に出る。志郎は札幌の新聞社に
入社、そこで知り合ったのが若き放浪詩人野口雨情であった。両家は親しくなり
一つ屋根の下で共同生活を始めることになる
そして「かよ」は、親しくなった雨情に 片時も忘れることのない「きみ」のことを
打ち明ける。可愛いきみを厳しい開拓村に連れて来なくてよかったと思う気持ちと
幼子を手放したという後悔‥‥そして新しい養父母のもとで幸せになってほしい!
そう願う気持ちの交錯‥‥‥‥この母の強い愛が雨情の心を激しくゆさぶった
雨情は、その感動を即座に詩に綴り、この詩に本居長世が曲をつけたのが『赤い靴』
さて、その後、志郎とかよは、樺太をはじめ、北海道の各地を転々とし、終の棲家は
小樽だった。その間、多くの子宝にも恵まれという志郎とかよは小樽に眠る
これにより、「小樽は赤い靴の物語の終着駅」となった・・・
画像は、小樽の「赤い靴をはいた女の子」
留寿都、そして函館とは大きく異なり、家族3人、楽しそうな表情を浮かべている
これは、「親子は天国で必ず再会できたはず。その時の光景を思い描いた」という













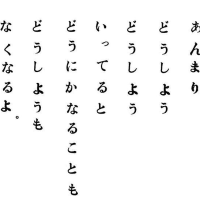




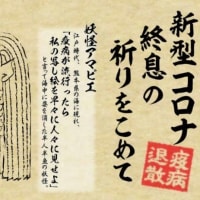
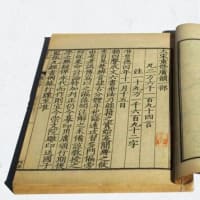
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます