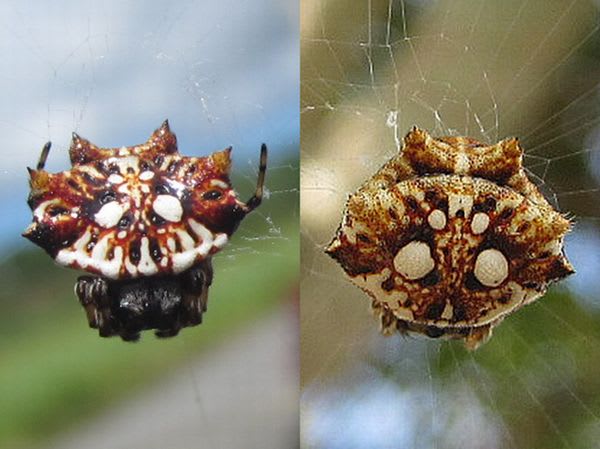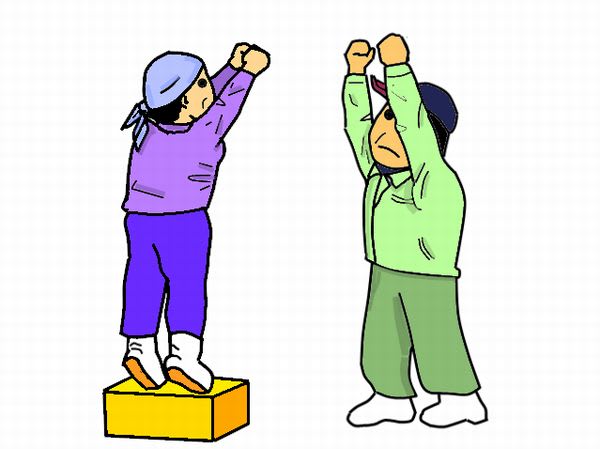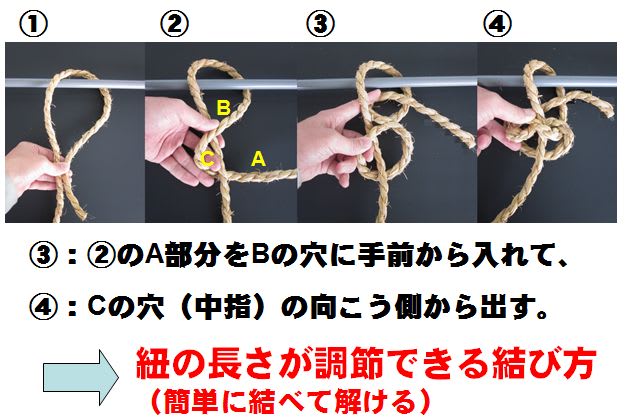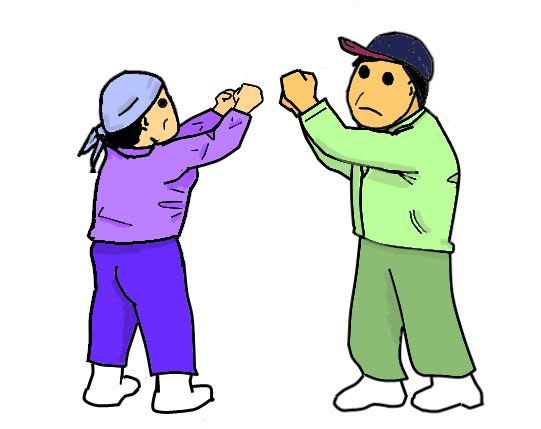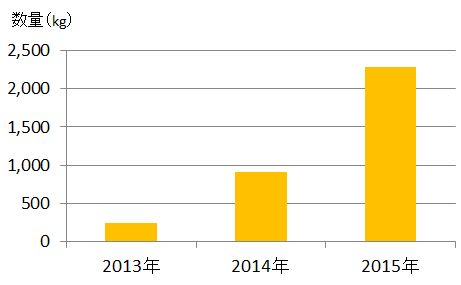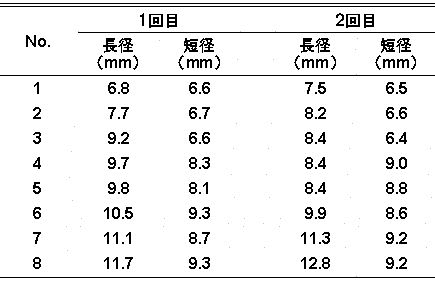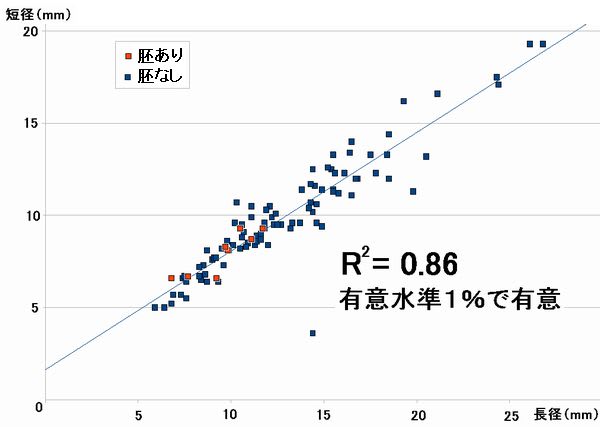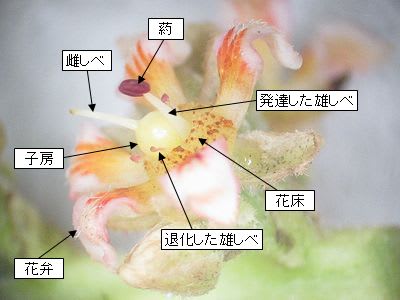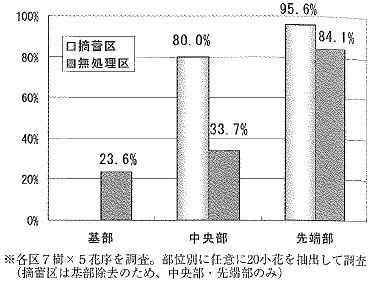日本国内で栽培されているマンゴーの95%以上は「アーウィン(Irwin)」と云う果皮が真っ赤な品種です。
2番目に栽培されている品種は「キーツ(Keitt)」と云う果皮が緑色の品種です。
「キーツ」は沖縄県で30年以上も栽培されているにも関わらず、不動の生産量2位、しかも品種占有率5%以下と云う境遇を維持しています。
「アーウィン」と「キーツ」は、いずれも米国フロリダ州で育成された品種です。
フロリダで栽培されているマンゴー80品種を紹介している「A Guide To Mango In Florida」と云うカタログでは、各品種の食味評価が「優(excellnet)」、「とても良い(very good)」、「良(good)」、「普通(fair)」、「劣る(poor)」の5段階評価で示されています。そこでは「アーウィン」の食味が「良(Good)」であるのに対し、「キーツ」の食味は「良~優(good to excellent)」とより高く評価されています。
「キーツ」が美味しいのに伸び悩んでいる理由は大きく2つです。
1つめの理由は「収穫時期の判定が難しいから」、2つめの理由は「食べ頃の判定が難しいから」です。
「キーツ」の収穫時期は、果皮色の微妙な変化や果形の変化、果梗部(ヘタ)付近のシワの発生程度等が収穫の目安とした上で「果実長径が5cm程度(仕上げ摘果時期の果実サイズ)から110~130日後が収穫の目安」という(比嘉ら.2007)研究成果により凡その目安はつきます。
また食べ頃も「収穫後に室温で8日間程度保管すると食べ頃になる」ことも報告されています(比嘉ら.2007a)。
因みにここで云う室温は29℃とされています(比嘉ら.2007b)。
しかし、果実を流通させる段階になると、これらの情報が十分活用されているとは云いがたく、結果として販売者や消費者にとっては「食べ頃がわかりにくい品種」という評価が定着しています。
そこで、今回は「キーツ」の生産者や産地が消費者に伝えたい『食べ頃の判断方法』をどの様に表現しているかを複数事例をもって紹介します。
〇レベル1=外観等で果実から食べ頃を判断してください!
事例1-1:JAおきなわ(リーフレット)

「食べ頃の目安」として2つの見極めポイントが記されています。
☆ 玉全体に柔らかみが出た頃
☆ 香りがします
この他に「食べ頃」として「 月 日頃」を記す欄が設けられていますが、市場流通している果実を見る限り、この欄は空白であることが多い様です。
事例1-2:宮古島産「キーツ」マンゴー(リーフレット)

「おいしい食べ頃 チェック表」と題し、4つのチェック項目が設けられています。
□ 果実表面に付着する白い粉が見えない
□ 果実全体がやわらかくなっている
□ 果実の皮の色が、緑色から黄緑色に変化している
□ 甘い香りがする
加えて、注意書きが3つ追記されています。
※1:常温で追熟させ、食べ頃になりましたら冷やしてお召し上がりください。
※2:キーツマンゴーは追熟型の果物です。果実が固いうちは食べ頃ではありません。
※ :20℃を下回る部屋では完熟しない恐れがあり、室温が高い所でゆっくりと追熟させて下さい。
事例1-3:個人生産者①(注意書き)

個人出荷されている生産者さんが消費者の場合に注意書きを箱内に入れている事例もありました。
「キーツマンゴーの食べ頃」
・キーツマンゴーは、追熟型の果実ですので常温で追熟させてください
・果実全体がやわらかく甘い香りがして地肌が黄色みを帯びてきたら食べ頃です。
〇レベル2=追加情報として収穫日も書いておきます!
事例2:JAおきなわ(スタンプ)

一部の生産者ではありますが、JAおきなわの出荷箱の外部側面に収穫日をスタンプしてくださっている方がいました。
これだと「室温で8日程度追熟させると食べ頃」と云う情報やレベル1の情報と合わせて、より食べ頃の判断がつきやすくなります。
〇レベル3=食べ頃の日付(目安)を表記しました!
事例3:個人生産者②(注意書き)

レベル1~3を全て備えた注意書きを箱に添付されている生産者がいました。
♪キーツの食べ頃♪
レベル1:常温で実が多少柔らかくなるまで保存し、その後冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。
レベル2:収穫日8月28日
レベル3:食べ頃のめやす9月4日~9月12日頃
※注意:保管環境で多少のずれがあります
この方の注意書きについて、市場に品物を確認に来られていたデパート仕入れ担当の方と意見交換しました。
その方は、
・ 「キーツ」の取扱い方法や食べ頃の表記はとても助かる。
・ 一緒に商品を作っていこうと云う生産者(産地)の思いが伝わる。
・ 収穫日や食べ頃の表記が直ちに価格に反映されることはないかもしれないが、まずは現況よりも「売れる商品」にすることが大切。
・需要が高まれば、価格にも反映される。
と高く評価されていました。
マンゴー生産者(産地)に「キーツの食べ頃の日付を表記してください」とお願いすると「不確かなことは言えないし・・」と尻込みをされる気持ちはよくわかります。
しかし、「まずはキーツをもっと売りやすい(買いやすい)商品にしよう」と云うところに意識を向けていただければ、生産者(産地)にならできる取り組みがあると思います。
〇参考文献
・「熱帯果樹マンゴー(キーツ種)の熟度判定技術の開発 第2報収穫後の食べ頃表示技術の開発(PDFファイル:292KB)」.2007a.比嘉淳・砂川喜信・貴島ちあき・屋良利次・伊山和彦・伊志嶺弘勝・與座一文.沖縄農業研究会;平成19年度(第46回)大会 講演要旨.
・「マンゴー「キーツ」の取り頃・食べ頃の判定(PDFファイル:272KB)」.2007b.比嘉淳・砂川喜信・貴島ちあき・屋良利次・伊山和彦・伊志嶺弘勝・與座一文.平成18年度 普及に移す技術の概要;p.65-66.沖縄県農林水産部.
【お知らせ】熱帯果樹に関心のある方は「Facebook」「Twitter」もご覧ください。
 | リアルで面識がなくても気軽に「ともだちになる!」とリクエストしてください。 その際、メッセージも付けて頂けるとスパムではないことが確認でき助かります。 |
 | 気に入ったら「フォロー」してください。 |