えっと、本当に久しぶりです。
冒頭だけが随分前に落ちてきたまま、あとは手つかずのまま放っておかれたものです。
理由は自分でも良く分からないまま言葉が止まってしまって、
ようやく昨日、不意に動きだしました。
リハビリに近い出来です。
立ちあがって、よろけて、壁の手すりをつかんでようやく進んでるカンジ。
興味がある方だけ、続きからお願いします。
今回もモデルとなった人物はいますが、実名は登場しません。
よろしくお願いします。
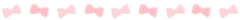
STORY.38 男と女
「大丈夫よ」と、それが彼女の口癖だった。
急な仕事のたび、
終わりそうで終わらない仕事のたび、
仲間との急な約束のたび、
電話の向こうで、いつも彼女は微笑い混じりに、そう言った。
ただの一回だって、
自分勝手なわがままを言わなかった。
勝手なのは、いつだって俺の方で、
なのに、
だから、
そんな日がくることだって、予測できなかったわけじゃない。
せやけど・・・
「もう、あかんって、なんで?」
「普通が欲しかったの」
「は?なに? どういうこと」
「それだけ、の意味だわ」
「それだけ、って。いやいや、待てや」
「もう、充分、待ったわ」
「あ・・・、いや、そうやなくて」
きまずい時間が、二人の上を覆い尽くす。
「俺に選択肢は、ない?」
黙ったまま、俺を見返してくる彼女の瞳が、その答えやった。
「そうか・・・」
そうして、俺は、
大事なもんをひとつ、手の中から逃してしまった。
いつだって、そんなことの繰り返しで。
去っていくものを追うこともせずに、
ただ、去っていくものへの未練を断ち切るためにだけ、
言葉を紡いでは、
それを音に乗せ続けてた。
言葉って、難しいやんな。
気持ちのすべてを言い表すことなんて出来んし、
ましてや、伝わるもんは、その幾千分の1にすぎんことやってある。
今、俺がしてることに、一体どれだけの意味があるんやろう。
「また、考えてる。あの彼女に、未練、あるの?」
そう言って、俺の顔を覗き込んだ。
手にしたグラスを、こつんと俺の額にあてる。
「冷たいな、やめろや」
ぼんやり眺めていた夜景から、視線を移す。
濡れたような赤いルージュが、目の前にある。
ひとつ恋が終わるたび、逢いたくなる赤いルージュ。
俺を拒否するでもなく、求めるでもなく、
ただ受け入れてくれる、赤い、イマドキにしては赤いルージュ。
ロックグラスのひんやりした冷たさが、突き刺すように顔の表面をすべっていく。
「また難しいこと考えてる表情してる。分かりやすいんだから」
グラスの中身を口に含んだ彼女の顔が近くなり、唇に重なった。
柔らかな感触と、
体温であたたまった、冷たかったはずの液体。
馴染みのない、琥珀の蒸留水の香りが鼻にぬける。
唇の端から、受け損ねたしずくが落ちる。
「あかん、こいつは飲み慣れんわ」
のどを下りてゆく香りに、むせかえるようだ。
俺から離れた彼女が、片頬で苦笑う。
「いつまでも、子供ね」
俺の髪先を指でもてあそぶ。
「子供ちゃうよ、もう30になったで。十分オトナや」
「ほら、ムキになる。そういうとこ、変わらないから子供っていうのよ」
彼女に初めて会ったんは。
あれは、まだ俺がこの仕事始めて間もない頃で。
その頃でも、もう十分にオトナだった彼女に、俺は憧れて、追いかけて。
でもいっつも子供扱いされて。
いや、実際のとこ、ガキやったんは確かなことで。
せやから、人の愛し方なんて、なにひとつ知らへんくて。
精一杯、大人ぶってた俺に、
『身の丈に合った恋愛』を教えてくれた。
つかず、離れず。
俺にやって、恋バナのひとつやふたつ、
傷ついたことかて、傷つけたことかて、
そらまあ、いろいろあったけど。
未練、か。
言うたら、そうかもしらん。
あれだけ俺のそばにいながら、俺の手を必要とせずにいて、
なんや気になって放っとかれへん女は、後にも先にもあの女だけやったかもしれへん。
あのまま。
あのままやったら。
俺はふと、今日の、後輩の幸せそうな笑顔を思い出していた。
「なあ、結婚て、どんなん?」
鳩が豆鉄砲くらったような表情して、彼女が俺を見降ろす。
「いきなり、ね」
「今日、結婚式やった、後輩の」
「ああ、そんなこと言ってたわね」
「これ以上はないくらい幸せって顔で、めっちゃ笑ってた」
「よかったじゃない。で?なあに?結婚したくなったの?」
「したなった・・・けど、」
「けど、なに?」
「結婚式のあとも、幸せなんやろか」
「は?またおかしなこと言いだしたわね」
「せやって、貴女やってダンナがおるのに、俺とこうしてるやん。それってどうなん」
「まったく、どの口がそう言うんだろ」
俺の口元を軽くつまんで、彼女が苦笑う。
「痛いって」
「可もなく不可もなく、普通に幸せよ」
「それが分からへんねん。普通、ってなに?」
「いやぁね、普通は普通。日常だわ」
「そこに愛はあるん?」
「あるわよ、あたりまえでしょ」
「ほな、俺とこうしてるんは、なに?」
「・・・・・・どうしたの、今夜は」
「普通が欲しかったんやて・・・」
「なに、それ」
彼女がゆっくりと俺の隣に腰を下ろす。
「彼女が言うた。別れ際・・・」
「ふうぅん、それで?」
「それで、って。それで終わり」
「皮肉ね」
「何がや」
「口癖じゃない、あなたの。普通でいたいって」
「あ・・・ああ、そやな。それが一番むずかしいってことも、知ってたはずやねん、俺は」
「普通を知るために、普通じゃないことが必要なのよ」
「なあ、それが、これ?」
俺は彼女が持ってたグラスを手からはずし、テーブルに置く。
透明なカケラが、揺れて小さな音を出した。
「俺がいちばん欲しかったもの、知ってる?」
彼女を抱きよせ、額を近付ける。
髪から香る匂いが俺を包む。
いつも。
そうだ、いつも、この香りだ。
この香りを自分のものにしたかったんだ、俺は。
いろんな香りと交わって、
いろんな香りを手放して、
たったひとつ、この香りだけが欲しかったんだ。
追いかけても願っても、手を伸ばしても。
決して、俺だけのものにはならない香り。
このひととは、「普通」を望めない。
望めない・・・のに。
・・・・・・望めない「普通」を、それでもまだ望んでる。
俺に身体をあずけてくる、その重みも温もりも弾力も。
恋焦がれて愛しくて。
今、この腕の中にある身体ごと、奪い去ってどこかへ逃げ出したいのに。
「私も、あなたが欲しかったわ」
彼女が耳元で、消え入るような声でささやく。
「何度も何度も、あなたを欲して。でも諦めて、諦めきれなくて」
細くてしなやかな指先が、俺のりんかくをなぞり始める。
「結婚という形に頼りたくなる時期もあるわ。結婚という制度が助けになるときだって。
でも・・・」
彼女が俺を見上げた。
「それは両刃の剣だわ」
「両刃か・・・」
触れては離れ、離れては触れる彼女の指先が、強く優しく、俺を翻弄しはじめる。
熱いかたまりが俺の中を上昇していくのが分かる。
行きつく先を求めて、徐々に渦を巻く。
男と、
女と。
それがありきたりの「普通」。
それがあたりまえの「普通」。
俺と彼女が望める「普通」なんだ、と。
Fin.
冒頭だけが随分前に落ちてきたまま、あとは手つかずのまま放っておかれたものです。
理由は自分でも良く分からないまま言葉が止まってしまって、
ようやく昨日、不意に動きだしました。
リハビリに近い出来です。
立ちあがって、よろけて、壁の手すりをつかんでようやく進んでるカンジ。
興味がある方だけ、続きからお願いします。
今回もモデルとなった人物はいますが、実名は登場しません。
よろしくお願いします。
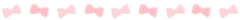
STORY.38 男と女
「大丈夫よ」と、それが彼女の口癖だった。
急な仕事のたび、
終わりそうで終わらない仕事のたび、
仲間との急な約束のたび、
電話の向こうで、いつも彼女は微笑い混じりに、そう言った。
ただの一回だって、
自分勝手なわがままを言わなかった。
勝手なのは、いつだって俺の方で、
なのに、
だから、
そんな日がくることだって、予測できなかったわけじゃない。
せやけど・・・
「もう、あかんって、なんで?」
「普通が欲しかったの」
「は?なに? どういうこと」
「それだけ、の意味だわ」
「それだけ、って。いやいや、待てや」
「もう、充分、待ったわ」
「あ・・・、いや、そうやなくて」
きまずい時間が、二人の上を覆い尽くす。
「俺に選択肢は、ない?」
黙ったまま、俺を見返してくる彼女の瞳が、その答えやった。
「そうか・・・」
そうして、俺は、
大事なもんをひとつ、手の中から逃してしまった。
いつだって、そんなことの繰り返しで。
去っていくものを追うこともせずに、
ただ、去っていくものへの未練を断ち切るためにだけ、
言葉を紡いでは、
それを音に乗せ続けてた。
言葉って、難しいやんな。
気持ちのすべてを言い表すことなんて出来んし、
ましてや、伝わるもんは、その幾千分の1にすぎんことやってある。
今、俺がしてることに、一体どれだけの意味があるんやろう。
「また、考えてる。あの彼女に、未練、あるの?」
そう言って、俺の顔を覗き込んだ。
手にしたグラスを、こつんと俺の額にあてる。
「冷たいな、やめろや」
ぼんやり眺めていた夜景から、視線を移す。
濡れたような赤いルージュが、目の前にある。
ひとつ恋が終わるたび、逢いたくなる赤いルージュ。
俺を拒否するでもなく、求めるでもなく、
ただ受け入れてくれる、赤い、イマドキにしては赤いルージュ。
ロックグラスのひんやりした冷たさが、突き刺すように顔の表面をすべっていく。
「また難しいこと考えてる表情してる。分かりやすいんだから」
グラスの中身を口に含んだ彼女の顔が近くなり、唇に重なった。
柔らかな感触と、
体温であたたまった、冷たかったはずの液体。
馴染みのない、琥珀の蒸留水の香りが鼻にぬける。
唇の端から、受け損ねたしずくが落ちる。
「あかん、こいつは飲み慣れんわ」
のどを下りてゆく香りに、むせかえるようだ。
俺から離れた彼女が、片頬で苦笑う。
「いつまでも、子供ね」
俺の髪先を指でもてあそぶ。
「子供ちゃうよ、もう30になったで。十分オトナや」
「ほら、ムキになる。そういうとこ、変わらないから子供っていうのよ」
彼女に初めて会ったんは。
あれは、まだ俺がこの仕事始めて間もない頃で。
その頃でも、もう十分にオトナだった彼女に、俺は憧れて、追いかけて。
でもいっつも子供扱いされて。
いや、実際のとこ、ガキやったんは確かなことで。
せやから、人の愛し方なんて、なにひとつ知らへんくて。
精一杯、大人ぶってた俺に、
『身の丈に合った恋愛』を教えてくれた。
つかず、離れず。
俺にやって、恋バナのひとつやふたつ、
傷ついたことかて、傷つけたことかて、
そらまあ、いろいろあったけど。
未練、か。
言うたら、そうかもしらん。
あれだけ俺のそばにいながら、俺の手を必要とせずにいて、
なんや気になって放っとかれへん女は、後にも先にもあの女だけやったかもしれへん。
あのまま。
あのままやったら。
俺はふと、今日の、後輩の幸せそうな笑顔を思い出していた。
「なあ、結婚て、どんなん?」
鳩が豆鉄砲くらったような表情して、彼女が俺を見降ろす。
「いきなり、ね」
「今日、結婚式やった、後輩の」
「ああ、そんなこと言ってたわね」
「これ以上はないくらい幸せって顔で、めっちゃ笑ってた」
「よかったじゃない。で?なあに?結婚したくなったの?」
「したなった・・・けど、」
「けど、なに?」
「結婚式のあとも、幸せなんやろか」
「は?またおかしなこと言いだしたわね」
「せやって、貴女やってダンナがおるのに、俺とこうしてるやん。それってどうなん」
「まったく、どの口がそう言うんだろ」
俺の口元を軽くつまんで、彼女が苦笑う。
「痛いって」
「可もなく不可もなく、普通に幸せよ」
「それが分からへんねん。普通、ってなに?」
「いやぁね、普通は普通。日常だわ」
「そこに愛はあるん?」
「あるわよ、あたりまえでしょ」
「ほな、俺とこうしてるんは、なに?」
「・・・・・・どうしたの、今夜は」
「普通が欲しかったんやて・・・」
「なに、それ」
彼女がゆっくりと俺の隣に腰を下ろす。
「彼女が言うた。別れ際・・・」
「ふうぅん、それで?」
「それで、って。それで終わり」
「皮肉ね」
「何がや」
「口癖じゃない、あなたの。普通でいたいって」
「あ・・・ああ、そやな。それが一番むずかしいってことも、知ってたはずやねん、俺は」
「普通を知るために、普通じゃないことが必要なのよ」
「なあ、それが、これ?」
俺は彼女が持ってたグラスを手からはずし、テーブルに置く。
透明なカケラが、揺れて小さな音を出した。
「俺がいちばん欲しかったもの、知ってる?」
彼女を抱きよせ、額を近付ける。
髪から香る匂いが俺を包む。
いつも。
そうだ、いつも、この香りだ。
この香りを自分のものにしたかったんだ、俺は。
いろんな香りと交わって、
いろんな香りを手放して、
たったひとつ、この香りだけが欲しかったんだ。
追いかけても願っても、手を伸ばしても。
決して、俺だけのものにはならない香り。
このひととは、「普通」を望めない。
望めない・・・のに。
・・・・・・望めない「普通」を、それでもまだ望んでる。
俺に身体をあずけてくる、その重みも温もりも弾力も。
恋焦がれて愛しくて。
今、この腕の中にある身体ごと、奪い去ってどこかへ逃げ出したいのに。
「私も、あなたが欲しかったわ」
彼女が耳元で、消え入るような声でささやく。
「何度も何度も、あなたを欲して。でも諦めて、諦めきれなくて」
細くてしなやかな指先が、俺のりんかくをなぞり始める。
「結婚という形に頼りたくなる時期もあるわ。結婚という制度が助けになるときだって。
でも・・・」
彼女が俺を見上げた。
「それは両刃の剣だわ」
「両刃か・・・」
触れては離れ、離れては触れる彼女の指先が、強く優しく、俺を翻弄しはじめる。
熱いかたまりが俺の中を上昇していくのが分かる。
行きつく先を求めて、徐々に渦を巻く。
男と、
女と。
それがありきたりの「普通」。
それがあたりまえの「普通」。
俺と彼女が望める「普通」なんだ、と。
Fin.









