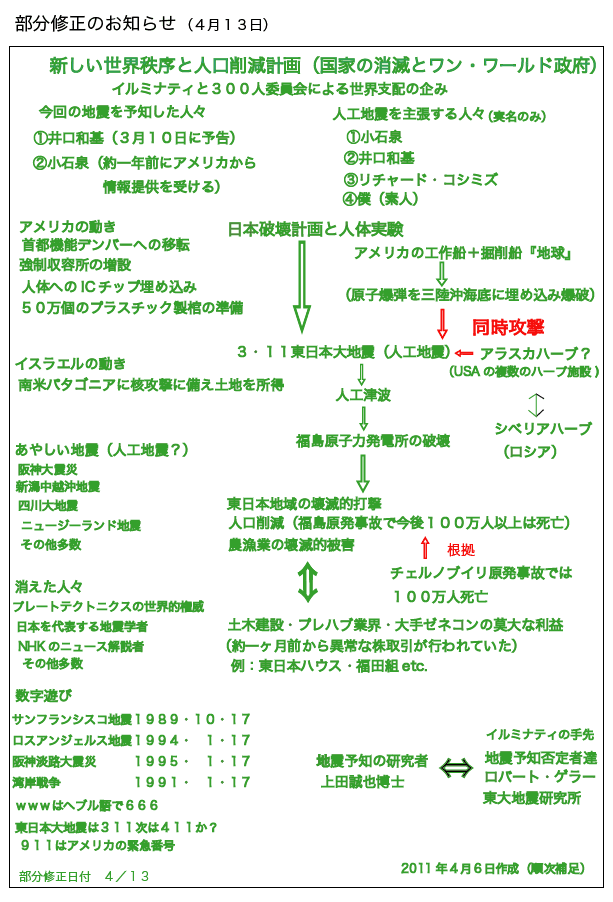今朝イルミナティの手先であるロバート・ゲラーがついに珍論文を発表しました。密かに尊敬している井口和基さんもロバート・ゲラーの正体を午前中のブログで告発しています。東大地震研究所も放射能汚染とイルミナティによる洗脳教育で完全に脳死状態だと僕は思っています。笑い話ですね。
今日は一日忙しかったのでこの辺でやめておきますが、いずれじっくりとロバート・ゲラーと東大地震研究所に関しては後日論じたいと思います。
地震予知への疑問
Posted on 14 April 2011 (ビジネス・ジャパンより)
Tags: 地震予知, 疑問
イギリスの科学雑誌『ネイチャー』に、「地震の長期予測や予知は不可能で、東海地震の予知研究はやめるべきだ」などを論じたロバート・ゲラー東京大教授(地震学)の論文が掲載されました。
同論文です。
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10105.html
論文の中では、日本政府が毎年発表している地震危険地域の地図と、実際の最近の主要な地震の発生地点とが大きくずれていることが一目でわかるように示しています。
「地震予知、即刻中止を」 東大教授、英誌に掲載 2011年4月14日 08時10分 中日新聞より
ロバート・ゲラー東京大教授
「日本政府は不毛な地震予知を即刻やめるべき」などとする、ロバート・ゲラー東京大教授(地震学)の論文が14日付の英科学誌ネイチャー電子版に掲載された。
「(常に)日本全土が地震の危険にさらされており、特定の地域のリスクを評価できない」とし、国民や政府に「想定外」に備えるよう求めた。
「今こそ(政府は)地震を予知できないことを国民に率直に伝えるとき」とも提言しており、世界的な学術誌への掲載は地震多発国・日本の予知政策に影響を与える可能性もある。
論文では、予知の根拠とされる地震の前兆現象について「近代的な測定技術では見つかっていない」と指摘し、「国内で1979年以降10人以上の死者が出た地震は、予知では確率が低いとされていた地域で発生」と分析。マグニチュード8クラスの東海・東南海・南海地震を想定した地震予知は、方法論に欠陥がある、としている。
教授は「地震研究は官僚主導ではなく、科学的根拠に基づいて研究者主導で進められるべきだ」として、政府の地震予知政策の根拠法令となっている大規模地震対策特別措置法の廃止を求めた。
また、福島第1原発事故についても「最大38メートルの津波が東北地方を襲ったとされる1896年の明治三陸地震は世界的によく知られている」とし、「当然、原発も対策されているべきで、『想定外』は論外だ」とした。
(共同)
Shake-up time for Japanese seismology
Robert J. Geller
Nature (2011) doi:10.1038/nature10105
Published online 13 April 2011
Robert J. Geller calls on Japan to stop using flawed methods for long-term forecasts and to scrap its system for trying to predict the 'Tokai earthquake'.
Article tools
print
email
download pdf
download citation
order reprints
rights and permissions
share/bookmark
Summary
The Japanese government should admit to the public that earthquakes cannot be reliably predicted.
Use of the misleading term 'Tokai earthquake' should cease.
The 1978 Large-Scale Earthquake Countermeasures Act should be repealed.
For the past 20 years or so, some seismologists in Japan have warned of the seismic and tsunami hazards to the safety of nuclear power plants, most notably Katsuhiko Ishibashi, now professor emeritus at Kobe University. Their warnings went unheeded. Yet in the immediate aftermath of the magnitude-9.1 earthquake that struck Tohoku on 11 March, pundits could be found on many Japanese TV stations saying that it was “unforeseeable”.
KYODO/NEWSCOM
Emergency drills such as this mislead the public into believing that the Tokai district is due a magnitude-8 quake soon.
The 'foreseen' earthquakes were presumably the hypothetical future earthquakes used by the Japanese government to produce national seismic hazard maps for Japan1. The modellers assume that 'characteristic earthquakes' exist for various zones, choose the fault parameters for each zone as the input to their model, and then produce probabilistic hazard maps.
Online collection
Although such maps may seem authoritative, a model is just a model until the methods used to produce it have been verified. The regions assessed as most dangerous are the zones of three hypothetical 'scenario earthquakes' (Tokai, Tonankai and Nankai; see map). However, since 1979, earthquakes that caused 10 or more fatalities in Japan actually occurred in places assigned a relatively low probability. This discrepancy ― the latest in a string of negative results for the characteristic earthquake model and its cousin, the seismic-gap model2, 3, 4 ― strongly suggests that the hazard map and the methods used to produce it are flawed and should be discarded.
Globally, in the past 100 years, there have been five subduction-zone earthquakes of magnitude 9 or greater (Kamchatka 1952, Chile 1960, Alaska 1964, Sumatra 2004, Tohoku 2011), which suggests that the upper limit on the possible size of a subduction-zone earthquake may not much depend on the details of the subduction modality5. Large tsunamis have frequently struck the Pacific coast of the Tohoku district. The well-documented 1896 Sanriku tsunami had a maximum height of 38 metres and caused more than 22,000 deaths. The 869 Jogan tsunami is documented to have had a height roughly comparable to, or perhaps slightly less than, that of the 11 March tsunami.

SOURCE: JAPAN HEADQUARTERS FOR EARTHQUAKE RESEARCH PROMOTION
If global seismicity and the historical record in Tohoku had been used as the basis for estimating seismic hazards, the 11 March Tohoku earthquake could easily have been 'foreseen' in a general way, although not of course its particular time, epicentre or magnitude. Countermeasures for dealing with such events could and should have been incorporated in the initial design of the Fukushima nuclear power plants.
The 'Tokai earthquake'
In the 1960s, plate tectonics became generally accepted as the fundamental paradigm of solid-Earth geoscience. Researchers in several countries made efforts to combine plate tectonics with seismicity data to make long-term forecasts of large earthquakes. The idea was very simple. It was hypothesized that zones where no large earthquakes had occurred for a while, dubbed 'seismic gaps', were ripe for imminent large events. However, the seismic-gap hypothesis failed the test of reality2. Over tens of thousands of years or longer, the net slip released by earthquakes and aseismic slip must match net inter-plate motion. But we now know that this catching-up process does not occur regularly or cyclically, as is further underscored by the 11 March earthquake.
In the mid-1970s, when enthusiasm for the seismic-gap model was still widespread in the global geoscience community, several researchers in Japan proposed that the plate boundary off the Tokai district was a seismic gap where a magnitude-8 earthquake could be expected6. The neighbouring Tonankai and Nankai districts were also labelled as being seismic gaps7. No large earthquake has occurred in any of these districts since 1975, but they are still classified as the most hazardous regions in the country by the Japanese government (see map).
Over the past 30 years or so, government spokesmen and university scientists associated with the government's Headquarters for Earthquake Research Promotion (or its various predecessors) have used the term 'Tokai earthquake' so often that the public and news media have come to view it as a 'real earthquake' rather than merely an arbitrary scenario (1.78 million hits in a Japanese-language Google search). This misleads the public into believing that the clock is ticking down inexorably on a magnitude-8 earthquake that is certain to strike the Tokai district in the near future. Use of the term 'Tokai earthquake' (and its companions 'Tonankai earthquake' and 'Nankai earthquake') should therefore cease.
Unpredictable earthquakes
“We should instead tell the public and the government to 'prepare for the unexpected'.”
Throughout most of seismological history, the prediction of earthquakes hours or days in advance has, for good reason, been regarded with great scepticism8 (see http://go.nature.com/ahc6nx). However, in the late 1960s and early 1970s, several studies, initially by researchers in the Soviet Union, and followed by similarly positive studies from major US institutions, led to a burst of optimism. The editors of Nature wrote in 1973 that the “situation is in some ways similar to that in 1939 when nuclear fission suddenly became a reality”9. Positive results were also published at roughly the same time in Science and some leading speciality journals.
The positive reports were based on claims to have observed 'precursors' of earthquakes. For example, some studies of the type discussed in Nature's 1973 article claimed to have observed decreases of 10–20% in crustal seismic velocities before earthquakes, with the return of the velocities to their normal values being the sign that an earthquake was imminent. But the 1976 earthquake in Tangshan, China, which caused a reported 240,000 fatalities, was not predicted, and by the late 1970s it had become clear to most researchers that the supposed precursors were artefacts. The prediction boom then largely died out, but like many similar examples (such as polywater and cold fusion), die-hard holdouts in several countries continue to make precursor claims.
Baseless prediction law
By the mid-1970s, public discussion of the supposedly imminent Tokai earthquake reached quasi-panic levels. This was exploited by the Japan Meteorological Agency (JMA) and university scientists, who persuaded the Japanese parliament to enact the Large-Scale Earthquake Countermeasures Act (LECA) in 1978. This law in effect requires the JMA to operate a 24/7 monitoring system to detect precursors indicating that the 'Tokai earthquake' (see map) will occur within up to three days. If and when signals thought to be precursors are ever observed, a panel of five geophysicists will review the data, the JMA director will inform the prime minister, and the cabinet will then declare a state of emergency, which will stop almost all activity in a wide area around the Tokai district.
JMA
The Japan Meteorological Agency control room conducts monitoring to predict the 'Tokai earthquake'.
This law, which has no precedent in any other country, presumes of course that reliable precursors exist. In particular, on the basis of one report of a geodetic precursor of an earthquake in Japan in 1944 (see Fig. 2 in ref. 6), geodetic slip is the main target of the JMA observations. The 1944 data, taken far from the epicentral region, were interpreted as possibly suggesting uplift of a few centimetres due to slow slip on a deep part of the fault shortly before the main shock. Unfortunately, the data were measured using antiquated surveying techniques, and are subject to considerable uncertainty. Nothing of this type has ever been observed using Global Positioning System devices or other modern measurement techniques. A famous report of a supposed geodetic precursor, the 'Palmdale Bulge', in the United States in the 1970s was later shown to be an artefact8.
Basing even a large-scale programme of observational research on the 1944 data would be uncalled for. It beggars belief, then, that the Japanese government operates a legally binding earthquake-prediction system on this basis. The JMA's official home page says (author's translation): “At present the only place a system for predicting earthquakes exists is for a magnitude-8 earthquake with an epicenter offshore Suruga Bay, i.e. the 'Tokai earthquake'. Science and technology have not progressed sufficiently to allow other earthquakes to be predicted.” But there are many more observatories now than in 1978. If it really were possible to predict the 'Tokai earthquake' then, surely it would be possible to predict all magnitude-8 earthquakes now.
Time for openness
How is it that the Tokai prediction system has been in place for more than 30 years, with barely a whimper from most mainstream Japanese seismologists? The reasons for this silence are complex. First, many researchers have been co-opted in various ways (such as with funding and committee memberships). Second, government decisions are nominally reviewed, but review panels are chosen by bureaucrats of the agency being reviewed. Third, cogent criticisms do get reported by print media, but are usually ignored by broadcasters, so critics don't get much traction. Fourth, through the 'press club' system, the government pipes its views directly into the media, often through reporters lacking in scientific knowledge. Finally, as long as the LECA stays on the books, the government can claim that it is obligated by law to try to predict the Tokai earthquake.
It is time to tell the public frankly that earthquakes cannot be predicted, to scrap the Tokai prediction system and to repeal the LECA. All of Japan is at risk from earthquakes, and the present state of seismological science does not allow us to reliably differentiate the risk level in particular geographic areas. We should instead tell the public and the government to 'prepare for the unexpected'10 and do our best to communicate both what we know and what we do not. And future basic research in seismology must be soundly based on physics, impartially reviewed, and be led by Japan's top scientists rather than by faceless bureaucrats.
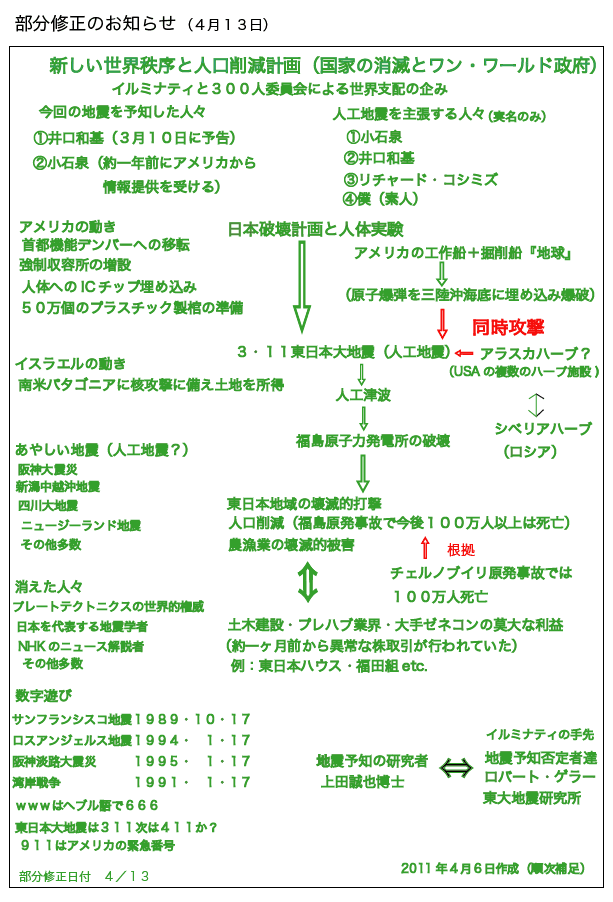
今日は一日忙しかったのでこの辺でやめておきますが、いずれじっくりとロバート・ゲラーと東大地震研究所に関しては後日論じたいと思います。
地震予知への疑問
Posted on 14 April 2011 (ビジネス・ジャパンより)
Tags: 地震予知, 疑問
イギリスの科学雑誌『ネイチャー』に、「地震の長期予測や予知は不可能で、東海地震の予知研究はやめるべきだ」などを論じたロバート・ゲラー東京大教授(地震学)の論文が掲載されました。
同論文です。
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10105.html
論文の中では、日本政府が毎年発表している地震危険地域の地図と、実際の最近の主要な地震の発生地点とが大きくずれていることが一目でわかるように示しています。
「地震予知、即刻中止を」 東大教授、英誌に掲載 2011年4月14日 08時10分 中日新聞より
ロバート・ゲラー東京大教授
「日本政府は不毛な地震予知を即刻やめるべき」などとする、ロバート・ゲラー東京大教授(地震学)の論文が14日付の英科学誌ネイチャー電子版に掲載された。
「(常に)日本全土が地震の危険にさらされており、特定の地域のリスクを評価できない」とし、国民や政府に「想定外」に備えるよう求めた。
「今こそ(政府は)地震を予知できないことを国民に率直に伝えるとき」とも提言しており、世界的な学術誌への掲載は地震多発国・日本の予知政策に影響を与える可能性もある。
論文では、予知の根拠とされる地震の前兆現象について「近代的な測定技術では見つかっていない」と指摘し、「国内で1979年以降10人以上の死者が出た地震は、予知では確率が低いとされていた地域で発生」と分析。マグニチュード8クラスの東海・東南海・南海地震を想定した地震予知は、方法論に欠陥がある、としている。
教授は「地震研究は官僚主導ではなく、科学的根拠に基づいて研究者主導で進められるべきだ」として、政府の地震予知政策の根拠法令となっている大規模地震対策特別措置法の廃止を求めた。
また、福島第1原発事故についても「最大38メートルの津波が東北地方を襲ったとされる1896年の明治三陸地震は世界的によく知られている」とし、「当然、原発も対策されているべきで、『想定外』は論外だ」とした。
(共同)
Shake-up time for Japanese seismology
Robert J. Geller
Nature (2011) doi:10.1038/nature10105
Published online 13 April 2011
Robert J. Geller calls on Japan to stop using flawed methods for long-term forecasts and to scrap its system for trying to predict the 'Tokai earthquake'.
Article tools
download pdf
download citation
order reprints
rights and permissions
share/bookmark
Summary
The Japanese government should admit to the public that earthquakes cannot be reliably predicted.
Use of the misleading term 'Tokai earthquake' should cease.
The 1978 Large-Scale Earthquake Countermeasures Act should be repealed.
For the past 20 years or so, some seismologists in Japan have warned of the seismic and tsunami hazards to the safety of nuclear power plants, most notably Katsuhiko Ishibashi, now professor emeritus at Kobe University. Their warnings went unheeded. Yet in the immediate aftermath of the magnitude-9.1 earthquake that struck Tohoku on 11 March, pundits could be found on many Japanese TV stations saying that it was “unforeseeable”.
KYODO/NEWSCOM
Emergency drills such as this mislead the public into believing that the Tokai district is due a magnitude-8 quake soon.
The 'foreseen' earthquakes were presumably the hypothetical future earthquakes used by the Japanese government to produce national seismic hazard maps for Japan1. The modellers assume that 'characteristic earthquakes' exist for various zones, choose the fault parameters for each zone as the input to their model, and then produce probabilistic hazard maps.
Online collection
Although such maps may seem authoritative, a model is just a model until the methods used to produce it have been verified. The regions assessed as most dangerous are the zones of three hypothetical 'scenario earthquakes' (Tokai, Tonankai and Nankai; see map). However, since 1979, earthquakes that caused 10 or more fatalities in Japan actually occurred in places assigned a relatively low probability. This discrepancy ― the latest in a string of negative results for the characteristic earthquake model and its cousin, the seismic-gap model2, 3, 4 ― strongly suggests that the hazard map and the methods used to produce it are flawed and should be discarded.
Globally, in the past 100 years, there have been five subduction-zone earthquakes of magnitude 9 or greater (Kamchatka 1952, Chile 1960, Alaska 1964, Sumatra 2004, Tohoku 2011), which suggests that the upper limit on the possible size of a subduction-zone earthquake may not much depend on the details of the subduction modality5. Large tsunamis have frequently struck the Pacific coast of the Tohoku district. The well-documented 1896 Sanriku tsunami had a maximum height of 38 metres and caused more than 22,000 deaths. The 869 Jogan tsunami is documented to have had a height roughly comparable to, or perhaps slightly less than, that of the 11 March tsunami.

SOURCE: JAPAN HEADQUARTERS FOR EARTHQUAKE RESEARCH PROMOTION
If global seismicity and the historical record in Tohoku had been used as the basis for estimating seismic hazards, the 11 March Tohoku earthquake could easily have been 'foreseen' in a general way, although not of course its particular time, epicentre or magnitude. Countermeasures for dealing with such events could and should have been incorporated in the initial design of the Fukushima nuclear power plants.
The 'Tokai earthquake'
In the 1960s, plate tectonics became generally accepted as the fundamental paradigm of solid-Earth geoscience. Researchers in several countries made efforts to combine plate tectonics with seismicity data to make long-term forecasts of large earthquakes. The idea was very simple. It was hypothesized that zones where no large earthquakes had occurred for a while, dubbed 'seismic gaps', were ripe for imminent large events. However, the seismic-gap hypothesis failed the test of reality2. Over tens of thousands of years or longer, the net slip released by earthquakes and aseismic slip must match net inter-plate motion. But we now know that this catching-up process does not occur regularly or cyclically, as is further underscored by the 11 March earthquake.
In the mid-1970s, when enthusiasm for the seismic-gap model was still widespread in the global geoscience community, several researchers in Japan proposed that the plate boundary off the Tokai district was a seismic gap where a magnitude-8 earthquake could be expected6. The neighbouring Tonankai and Nankai districts were also labelled as being seismic gaps7. No large earthquake has occurred in any of these districts since 1975, but they are still classified as the most hazardous regions in the country by the Japanese government (see map).
Over the past 30 years or so, government spokesmen and university scientists associated with the government's Headquarters for Earthquake Research Promotion (or its various predecessors) have used the term 'Tokai earthquake' so often that the public and news media have come to view it as a 'real earthquake' rather than merely an arbitrary scenario (1.78 million hits in a Japanese-language Google search). This misleads the public into believing that the clock is ticking down inexorably on a magnitude-8 earthquake that is certain to strike the Tokai district in the near future. Use of the term 'Tokai earthquake' (and its companions 'Tonankai earthquake' and 'Nankai earthquake') should therefore cease.
Unpredictable earthquakes
“We should instead tell the public and the government to 'prepare for the unexpected'.”
Throughout most of seismological history, the prediction of earthquakes hours or days in advance has, for good reason, been regarded with great scepticism8 (see http://go.nature.com/ahc6nx). However, in the late 1960s and early 1970s, several studies, initially by researchers in the Soviet Union, and followed by similarly positive studies from major US institutions, led to a burst of optimism. The editors of Nature wrote in 1973 that the “situation is in some ways similar to that in 1939 when nuclear fission suddenly became a reality”9. Positive results were also published at roughly the same time in Science and some leading speciality journals.
The positive reports were based on claims to have observed 'precursors' of earthquakes. For example, some studies of the type discussed in Nature's 1973 article claimed to have observed decreases of 10–20% in crustal seismic velocities before earthquakes, with the return of the velocities to their normal values being the sign that an earthquake was imminent. But the 1976 earthquake in Tangshan, China, which caused a reported 240,000 fatalities, was not predicted, and by the late 1970s it had become clear to most researchers that the supposed precursors were artefacts. The prediction boom then largely died out, but like many similar examples (such as polywater and cold fusion), die-hard holdouts in several countries continue to make precursor claims.
Baseless prediction law
By the mid-1970s, public discussion of the supposedly imminent Tokai earthquake reached quasi-panic levels. This was exploited by the Japan Meteorological Agency (JMA) and university scientists, who persuaded the Japanese parliament to enact the Large-Scale Earthquake Countermeasures Act (LECA) in 1978. This law in effect requires the JMA to operate a 24/7 monitoring system to detect precursors indicating that the 'Tokai earthquake' (see map) will occur within up to three days. If and when signals thought to be precursors are ever observed, a panel of five geophysicists will review the data, the JMA director will inform the prime minister, and the cabinet will then declare a state of emergency, which will stop almost all activity in a wide area around the Tokai district.
JMA
The Japan Meteorological Agency control room conducts monitoring to predict the 'Tokai earthquake'.
This law, which has no precedent in any other country, presumes of course that reliable precursors exist. In particular, on the basis of one report of a geodetic precursor of an earthquake in Japan in 1944 (see Fig. 2 in ref. 6), geodetic slip is the main target of the JMA observations. The 1944 data, taken far from the epicentral region, were interpreted as possibly suggesting uplift of a few centimetres due to slow slip on a deep part of the fault shortly before the main shock. Unfortunately, the data were measured using antiquated surveying techniques, and are subject to considerable uncertainty. Nothing of this type has ever been observed using Global Positioning System devices or other modern measurement techniques. A famous report of a supposed geodetic precursor, the 'Palmdale Bulge', in the United States in the 1970s was later shown to be an artefact8.
Basing even a large-scale programme of observational research on the 1944 data would be uncalled for. It beggars belief, then, that the Japanese government operates a legally binding earthquake-prediction system on this basis. The JMA's official home page says (author's translation): “At present the only place a system for predicting earthquakes exists is for a magnitude-8 earthquake with an epicenter offshore Suruga Bay, i.e. the 'Tokai earthquake'. Science and technology have not progressed sufficiently to allow other earthquakes to be predicted.” But there are many more observatories now than in 1978. If it really were possible to predict the 'Tokai earthquake' then, surely it would be possible to predict all magnitude-8 earthquakes now.
Time for openness
How is it that the Tokai prediction system has been in place for more than 30 years, with barely a whimper from most mainstream Japanese seismologists? The reasons for this silence are complex. First, many researchers have been co-opted in various ways (such as with funding and committee memberships). Second, government decisions are nominally reviewed, but review panels are chosen by bureaucrats of the agency being reviewed. Third, cogent criticisms do get reported by print media, but are usually ignored by broadcasters, so critics don't get much traction. Fourth, through the 'press club' system, the government pipes its views directly into the media, often through reporters lacking in scientific knowledge. Finally, as long as the LECA stays on the books, the government can claim that it is obligated by law to try to predict the Tokai earthquake.
It is time to tell the public frankly that earthquakes cannot be predicted, to scrap the Tokai prediction system and to repeal the LECA. All of Japan is at risk from earthquakes, and the present state of seismological science does not allow us to reliably differentiate the risk level in particular geographic areas. We should instead tell the public and the government to 'prepare for the unexpected'10 and do our best to communicate both what we know and what we do not. And future basic research in seismology must be soundly based on physics, impartially reviewed, and be led by Japan's top scientists rather than by faceless bureaucrats.