脳味噌の老化現象で読解力が衰えて、読む本を替えたことは以前お話しました。登場人物が少なく、人脈が複雑でなく、内容が比較的まとまっている、短編のものにしました。
先日来、「ちくま日本文学・幸田文」を読んでいます。ご存じのことと思いますが、彼女は幸田露伴の娘です。高校の現代国語に、露伴から家事一般をこなす心得を教え込まれる様子や、露伴が亡くなって葬儀を終えて、「別れすら」終わった、と書いた文を習ったことを思い出したのでした。
大好きなM先生の、この「すら」の表現についての名講義で私は大学でも国文を専攻したのでした。必ずしもこれがよい選択だった、自分に合っていたとは思わないのですが。
昨日前述の本の「雛」と題した文(エッセイ(?)小説(?))を読み、感じ入った箇所がありましたので、書いてみます。私の拙い文でお伝えできるものではありませんが。要所だけ書きます。
娘の初節句にお雛様をと思った。揃えるならいいものを・・・の気持ちが、だんだん高揚してきた。お雛様も最高のもの、ひな壇と天井の高さの間の空間も幕をおろしたかった。部屋全体を春の雰囲気に、廊下も桃の生け花と菜の花の生け花とで飾った。招待客は夫の母、私の両親二人の三人だけ。
市場で食事の新鮮な魚も吟味した。完璧に準備して待った。
三人の年寄りは大いに喜んだ(と思った)
翌日、父から寄ってくれと言伝があった。あ、叱られると思った。
穏やかにではあるけれどこんなことを言われた。
「至れり尽くせりにやったな。でもあれは尽くし過ぎではないか。尽くして後、なにが残ったか、お前は子どものためというけれど、子供に何が残ったか。しゃにむに子供に分不相応に使い果たしていいものか、お前が子供の福分を薄くしたようなものと思わんか」。浪費と言わずに福分を使い果たす、と注意した。
それだけ言って、言外に姑の所にもよって行けとにおわせた。
姑は
「実はね、あの日帰ってからいろんな気持ちがしてね、言うにも言われず、言いたくもあるしという変な気持ちでした。あちらのお父様はし過ぎたとおっしゃいましたか。私はまた、残しておいてもらいたかったと思ったのですよ」
「ああ全てをやってしまったら、祖母のこころの入り込む隙がありません。何か足りないものがあれば、来年、買い足して孫に贈る楽しみもあるのに、と味気なく思ったのよ」。
言われてみて納得した。欠けたところがないのは寂しさに通じるのか。
父は労わりの中で、ずけずけと叱った。姑は「いたりつくす嫁」にいうに言えない寂しさを感じていたという。
難しいものですね。


















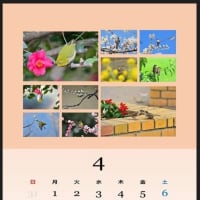


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます