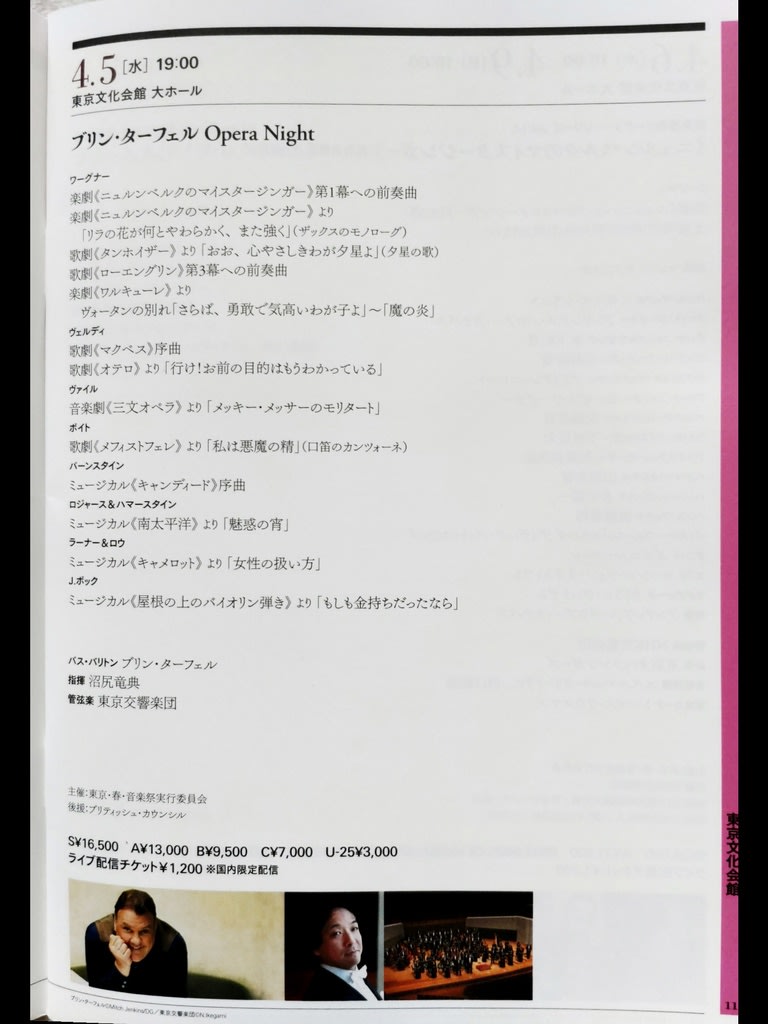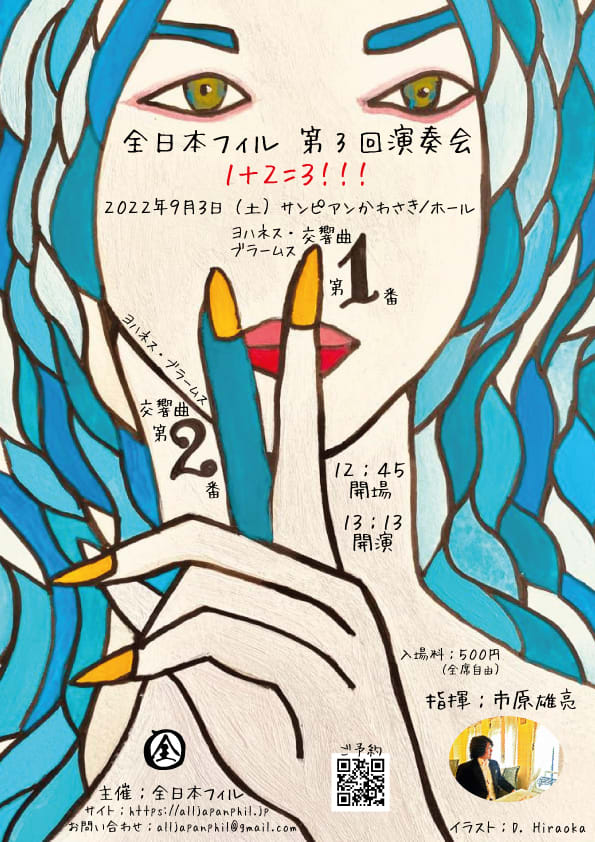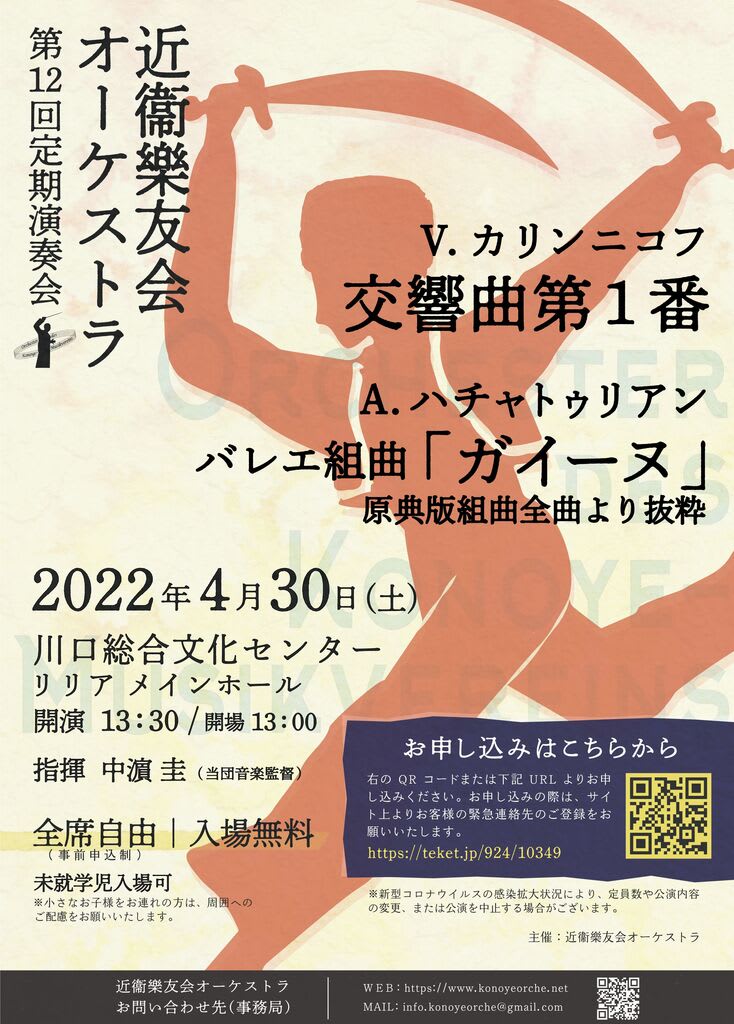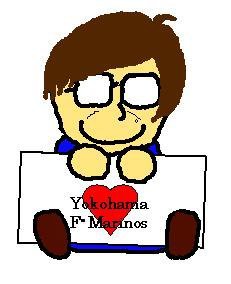昨日、「指揮者なんて誰がやっても同じじゃね?」 ってテーマで書いた記事はオーケストラの演奏が中心だったんだけど、その流れで、今日はコーラスを題材にしてもう少し書いてみようと思う。
一つは、畑中良輔が指揮した、慶應大学ワグネル・ソサィエティー男声合唱団の演奏。
もう一つは、小林研一郎が指揮した、早稲田大学グリークラブOB会の演奏。
両方聞いていただければおわかりのように、違いは歴然。この曲は、言葉を語るように歌う部分が多いし、音楽的にも解釈の幅が広いから、指揮者や合唱団のカラーが出やすいと思う(そのためにはそれなりの技術も必要だけどw)。つまりいろいろな演奏ができるから違いも出やすい。慶應の方は、まあまあスタンダードな演奏(この言い方はあまり本意じゃないけど)っていう範疇かな。ただし、終曲「海よ」の最後のピアノを鳴らさずに第一曲の「雨」に戻ったのはちょっとびっくり。それも中間部を抜いて「静かにふりしきる雨」の部分だけ。海から天に昇った「水のいのち」が再び「ふりしきる雨」に戻るって、さすが畑中亮輔だなと感心。もちろんこれはスタンダードの範疇を大きくはみ出してるけどw。
そして、早稲田の方は、最初からいかにもコバケンっていう感じの演奏www。スタンダードの範疇は相当超えてるかなw。この曲は普通に歌っても、指揮するのも指揮に合わせるのも大変だから、これだけコバケン節が炸裂すると歌う方は大変だったと思うし、それが随所に表れてるw。でも、多分、歌ってる方はめちゃくちゃ気持ちが良かったんじゃないかな~。
畑中亮輔と小林研一郎の演奏を比較するのもどうかと思ったけど、わかりやすいことはわかりやすいので、思ったことを書いてみた。いかがでしょうか?
儂個人的にはコバケンの指揮で歌いたいw。
ちなみに、儂、小林先生の方の第三曲「川」の「よどむふち」の出だしを聴く度に笑ってしまう。いや、決して悪い意味じゃなくて。あの指揮で歌い出すのはかなりの勇気がいるだろうなと思うw。でも、そこがまたいいな~。
ついでに、これは作曲自身が指揮した演奏。合唱は神戸中央合唱団。ただし混声版で、第一曲「雨」と第三曲「川」のみ。
混声版なので音色や響きが全く違うけど、前2つの演奏のいずれとも明らかに違う。そして作曲者自身の指揮が一番かと言うと、これまた必ずしもそうとも言えない不思議w。
と、昨日よりももっとマイナーなことを書いてしまったけど、ね、指揮者って仕事してるんですよw。
【ぼあちゃん】
2020年9月6日の3枚。



【はちゅメモ】
9月5日(火)
まあまあいろいろ気になることはあったけど、特別心配っていうほどのことはなかった。
きょろちゃん@1:43 P.M.
一度出て来たんだけどほとんど寝てる? この後、またすぐに引っ込んだ。

きょろちゃん@5:41 P.M.
やっと目が覚めて「出して~」。

この後、別荘に出て来て今日も冒険。
きょろちゃんとらぷちゃんのことは先の記事に書いた通り。2人(2トカゲ)ともあれだけ冒険できたんだから元気なんだろう。
ただ、きょろちゃんはケージから出て来るのが遅かったし、またちょっとおかし気な尿酸を出してた。らぷちゃんは落下事故の影響をもう少し見ないとダメだな。しおちゃんはまったく出て来ず。どうしたのかな? オリハちゃんはとりあえずあの時以来下痢はしてないみたい。あまり変わらずかなとは思うんだけど、今日はまたちょっと鳴いてた。