

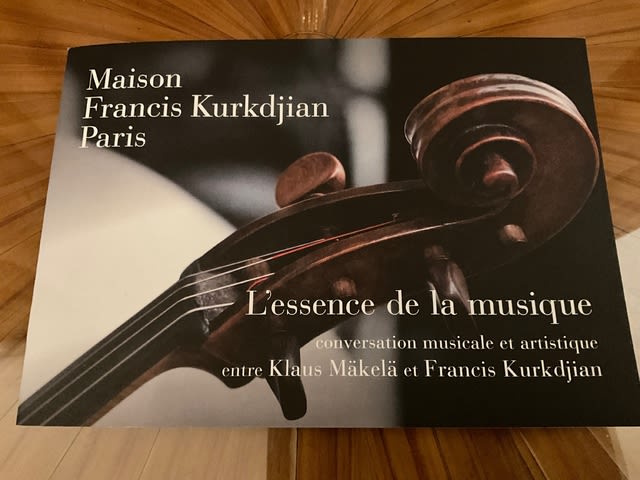
2022年11月30日、12月1日

クラウス・マケラ パリ管来日演奏会 プログラムB
ドビュッシー:交響詩「海」
ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調
ストラヴィンスキー:火の鳥(全曲)
18日のサントリーホールの状況を聴いて、帰りの新幹線に間に合うのか?などと思っていたが、実は開演時間が18:50であった。新幹線の都合上少し早めに着いていたからよかったものの、危ない、危ない。
本当はサントリーホールで聴きたかったのだが、予定があり名古屋へ伺った。先日反田さんの演奏会で、音響が悪くないように思われたので。
しかし、結局音響はサントリーホールの方が良い、少なくともオーケストラに関しては、サントリーの方が好みの音であることは理解した。
アンコールで演奏されたルスランとリュドミラ序曲がこの日の中では最も良い出来のように思われた。すごいスピード、ムラビンスキーも真っ青?フランス人もやる時はやる、休み前や締め切り前に、きっちり合わせてくるフランス人の底力を見たような気がした。素晴らしい。
クラウス・マケラ パリ管来日演奏会 プログラムA
ドビュッシー:交響詩「海」
ラヴェル:ボレロ
ストラヴィンスキー:春の祭典
ラヴェルは妖艶な、というよりは、若々しく爽やかなボレロであった。
春の祭典は、基準がザルツブルグで聴いたウィーンフィル&Gustavoの演奏なので、まあ、比べてはいけなかったのだろう。あの丁々発止な春の祭典、いつかもう一度聴いてみたい。
S席32000円という高額チケット。そのためか、席に着くと、かなり空席があった。こんなに空席の多いサントリーホール初めて見た。チケット代を値上げせずに満席にするのと(満席になったかは微妙?)、値上げして今回の入りと、どちらが収支上良かったのだろう。 アンコール前のスピーチでSuntory hall is my favourite hallって言っていただいたし、満席でお迎えしたかった。
(後から知ったが、助成金が出ていたらしい。それは本当に正しい税金の使い方だったのだろうか?)









