(1)財政史の中で「経費膨張の法則」ということが出てきます。これは、19・20Cあたりからの各国の財政を見ると、どの国の財政も次第に規模が大きくなってくるが、なぜ財政規模は大きくなるのかという疑問です。
(2)いくつか学説がありますが、その中の代表的なものの一つに「ドイツ財政学」があります。ドイツ財政学の代業者アドルフ・ワグナーは「社会が発展し、文明が進化すると経費が膨張する」と言いました。しかし、これはごまかしです。意味が分かりません。簡単に言うと、社会・経済に変化が生じてくるからです。
(3)当時のドイツは(ロシアや日本も)まだ経済の後進国でした。
ドイツでは国内産業を保護し、同時に、イギリスやアメリカの先進資本主義に対抗して、国家財政を通じて経済発展を図ろうとしました。日本の殖産興業も同様です。
かつての英米先進国(や現在の日本)などでは、経済の発展が政治を抱え込んで動かしていくのが特徴ですが、当時のドイツは遅れを国家の政策を通じて解消していく政策をとったということです。
一方、経済が小規模企業の時代から大企業体が国内産業を支配する時代に入りましたから、中小企業との格差・労働者の貧困化などが表面化し、国家が財政資金を通じて政策をとる(社会政策)必要が拡大してきました。
1800年前後に産業革命が進むと、1840年代には経済恐慌も現われ、郎度運動が激化し、やがて1917年にはロシア革命も起こりますから、その政策を国家がとることが求められたわけです。
(4)つまり、経費が膨張する理由は、社会経済の「国家への依存」が増したこと、逆に、社会経済への「国家の干渉・介入」の場面が増えたことです。
現在では、国内問題だけでなく、国際的にも国家が果たす役割が大きくなっています。やっていることの是非は別にして、プーチン・習近平・トランプなどの各氏の動きを見ているとよくわかります。とくに軍事費。
(5)日本では、成長とか景気対策のためといって公共投資をやって大盤振る舞いし、憲法に違反して防衛費をどんどん増額して無駄使いを続けてきたことが経費膨張の大きな理由であり、赤字財政の原因です。
ちなみに、福祉や高齢化が原因だという人もいますが、それは政府の政策を弁護するものです。実際、この30~40年ほどの期間でも、大手の法人税減税や高額職者の所得税減税をやり、その穴埋めを消費税の増税でやりました。
そうしておいて、中小企業対策費や農業対策費、教育費、社会保障費などは本来の憲法で唱えているようにはなっていないのですから、知らないか、知っていての責任転嫁です。
今のコメの価格高騰、埼玉の陥没などがこれまでの政策の是非を問うています。

【コレクション 159 協調会 最近の社会運動】
日本の社会保障や福祉が立ち遅れている理由の一つは、戦前の治安維持法にあると言われています。
社会保障や医療・福祉、中小企業対策・農業政策、教育政策には膨大な財政資金が必要です。政府や与党は、裏金問題で暴露されたように、献金をしてくれる方にはいい顔をしますが、そうでない方には財政資金を使うのを渋ります。ましてや社会保障などには膨大な資金がかかります。政府に対して圧力となる強い国民の意思表明がないとやりたがりません。
治安維持法によって、労働者政党や自由主義的な思想をいち早く弾圧したことがその後に大きく影響しているのです。
今日は、戦前の社会運動を知ることのできる資料です。
これは、大きさは、B5判6㌻です。B5判3枚分の横長の用紙を、最初に左から3分の1を折り込み、ついで右から3分の1を折り込むと出きます。
全体は、
1・2・4(一部)㌻を下に載せましたから、ここは内容説明を略します。
1㌻ 見て楽しいというものではありませんが、格調があります。
2㌻ 協調会の説明と、本書の特色・観光案内が出ています。
3・4(一部)㌻は、推薦文と内容目次です。
推薦文
隅谷三喜男 東京大学名誉教授 包括的に把握するのに最適
岩井 章 総評元事務局長 大変参考になること
松尾尊兊 京都大学教授 形成期日本社会運動の百科全書 *下に掲載
5㌻ 組見本
6㌻ 関連宣伝
1㌻
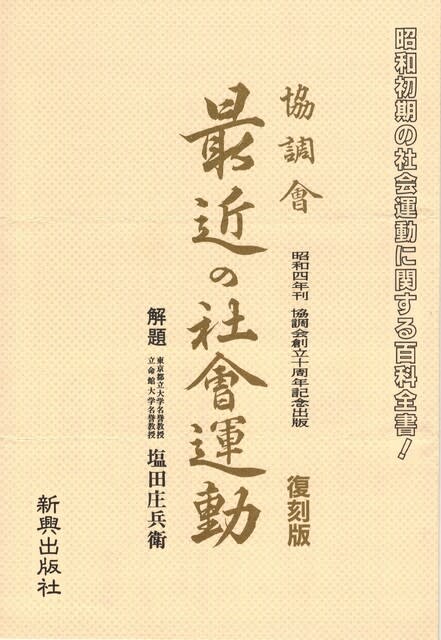
2㌻
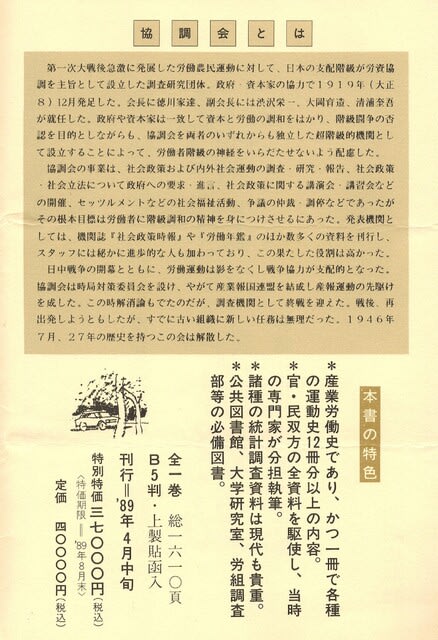
3㌻
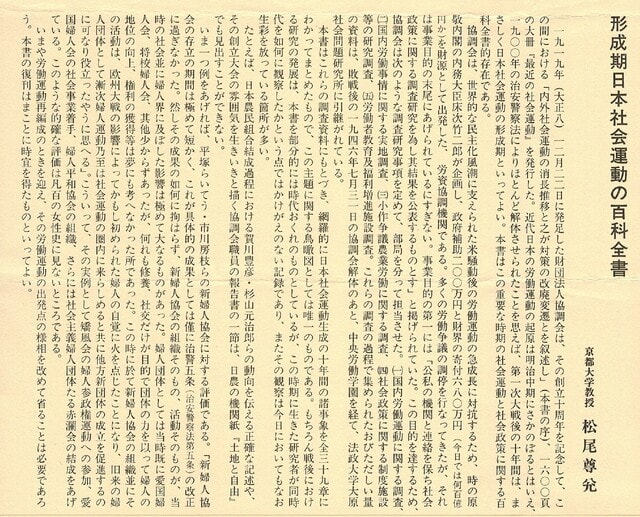
以上です。
昨日は書いたものの大半が消えてしまい、その徒労感はなんとも言えませんでした。
書いているといろいろのことが思い出されて、あっちを見たりこっちを検索したりとやり始めます。それがもとでパソコンが狂いだす・・・。
要するに、ブログは簡明を旨とすべし、なんですね。
ワシ曰:「我、No.400にしてブログの極意を知る。」

北桔橋門より:正面は毎日新聞社と共立大学?

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます