(1)山岳小説家で知られた新田次郎の作品『山が見ていた』(1961年、文春文庫)に大岳山が出て来ることをご存じの方もあるでしょう。詳しくは読んでいただくとして、およその話の筋は次のようなことです。
主人公は仕事の途中で子供をはねてしまいます。当然、救助すべきところですが、怖さのあまりにその場から逃げ去ってしまいます。しかし、それを負い目に感じ、自責の念から死のうとして大岳山に来ます。ところが、山中で道に迷った5人の子どもを助けたことから、死に場所を失うという話です。
(2)新田作品は60年以上前のものです。大岳山の雰囲気も今とだいぶ違うでしょう。
今の大岳山のコースからはここを死に場所に選ぶなどということは想像もできません。ちょっと途中を紹介しましょう。
1.日当たりがよく、平坦な所

2.やや日陰で、石ころがある所

3.少し険しいところ。もっと険しいところもあります

(3)しかし、18日に登ったサルギ尾根のように人通りの少ない「通常のコース外のコース」や、整備されたコースを外れたところで具合が悪くなったり、ケガで動けなくなったときは、誰にも見つけてもらえないということがあり得ます。スマホなどを持っていても、電池が切れてしまっていたり、電波が届かない範囲に入ってしまうと、不幸なことになり得ます。
(4)とはいえ、天気の良い日なら、特別な装備などなくてもチョイと登れます。
実際、1月4日には、御嶽神社で受けたお札だけを持って登って来た人を見ました。ケーブルに乗って参拝に来たところ、天気も良いから行ってみるかと思い立ったのでしょうけれど、散歩がてらではやはり危険です。遭難も多いのです。
また、18日には、外国人10人くらいの集団が、街歩きの服装(ジャンバーに運動靴ばき、リュックを背負っていないどころか水も持たない)で、手ぶらで登って来ました。
驚いたのはそれだけではありません。この時、時刻はすでに午後1時半を回っていて、まだ頂上まで1時間ほどかかるところでした。この調子だと、おそらく、頂上に着くのは早くて2時過ぎです。少し景色を見て2時半に降り始めたとすると、ケーブル駅に戻った頃はもう4時近くでしょう。そうすると、途中の杉林の近くでは真っ暗ということもあったでしょう。
山は、陽が落ちると視界が悪くなり、急に寒くなります。夏なら雷雨もあります。それを考えると、彼らは本当に無防備な山知らずの人たちといわなければなりません。
(5)それだけではありません。新田次郎の作品の主人公のように死にに来たわけではないと思いますが、上の外国人グループだけでなく、山登りの装備をしているとはいえ頂上に着いたら2時を過ぎるだろうと心配される人をずいぶん見ました。高齢の夫婦?3組、中年の日本人と外国人のペア?、それから単独行の20代前半の女性です。
(6)私は、上の外国人に「It takes one hour.」と言い、それぞれに「これからですか?」と声をかけました。上の小屋に宿泊するならともかく、明らかに危険と思われたからです。
とくに、単独行の若い女性には「帰りは暗くなりますよ」とも言いました。すると、「ライトを持っています」と答えました。もちろん私も持っていますが、それは非常用です。何か目的があるというならともかく、暗くなることを承知で出てきていることがわかり、驚きました。仕方ないので、「ちょっと先にご夫婦が上がっていきましたから、追いかけて一緒に行動するように」といって別れました。
山の怖さを知らない「都会人」には驚かされます。
(7)長くなりました。
私は14:20にビジターセンター前に着きました。コースタイムでは下までは40分ですから、15時頃にはバス停に着けると読んで歩くことにしました。
1.少し歩くと、ケーブル・カーの線路をくぐります。実際はもっと明るくて、雰囲気の良いところです。この付近で、若い二人連れの青年が追い越していきました。

2. 道がつづら折れになっていて、しばらく降るとケーブル・カーの線路脇に出ました。その時ちょうどケーブルが上がって来ました。

3.ケーブル・カーはここの少し上で登りと下りが交換します。待っていると、下りが来ました。

4.さらに降ると、思い出の場所にきました。
もうかれこれ40年前のことになりますが、娘と息子がまだ小学生の頃、家族4人でここを上がったことがあります。その時に二人がこの中に入って雨宿りの真似をしたのです。たぶん子供は皆そんなことをするでしょうね。

5.バス停につきました。少し遠くの山を眺めていると、なんと、日ノ出山北尾根が夕陽に照らし出されているではありませんか。少し拡大して撮りました。
木が伐採されていて尾根筋がよく見えます。まだ取っ付きのところですが、ここをぐいぐいと上がっていく登りは、高度感もあり格別です。

6.バスで青梅線の御岳駅前に着きました。駅前はT字路になっていて、信号脇に東峯園というラーメン店があります。メニューの一番上には「みそラーメン」などがありますが、ここの昔からのお勧めは、メニューの一番下に小さく書いてある「みたけラーメン」です。「通」を気取るわけではありませんが、シンプルな味でオススメです。でも、昨今の野菜価格高騰のためでしょうか、野菜がやや少なくなったように思いました。昔は、野菜をかなり食べてからでないと麺にたどり着けなかったのではないかと思います。そういう記憶を書いている本もあります。
今日はここで。
【コレクション】はタイムオーバーにつき、明日に。
























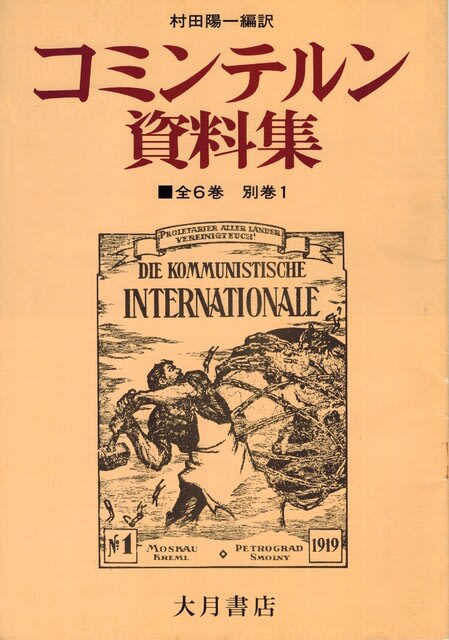
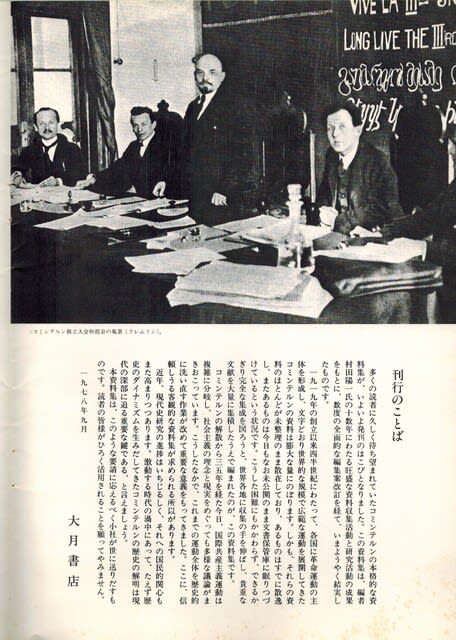 )
)





















