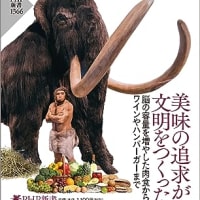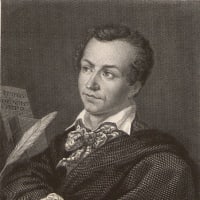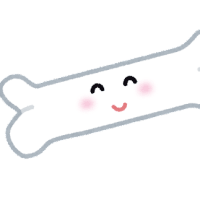古代ローマの農業の発展と衰退(4)
優れた農業技術を有していた古代ローマ人だったが、そのような技術も使われないと何の意味もない。紀元前200年頃から増えてきた大規模農地のラティフンディアでは目先の利益を優先したことから、輪作などで土地を休ませることをしなかった。その結果、土壌から次第に栄養が失われていった。
やせた土壌は乾燥しやすく崩れやすい。このため、少しの風や雨で土壌は流失してしまう。特に、鉄製の農具を使って深く耕した土地は土壌が流出しやすい。また、鉄製の農具で森を切り開いて作った農地は傾斜地にある場合が多いので、風や雨によって土壌が流れ出しやすかった。土壌がいったん流失してしまうと岩盤がむき出しになり、もはや農耕地としての回復は見込めなくなってしまうのだ。
一方、牧草地でも土壌の流出が進んだ。イタリア南部のラティフンディアはヒツジの巨大な放牧場になっていた。ここでも儲けを多くしたいために、土地のキャパシティを越えて大量のヒツジを飼育する「過放牧」の状態になっていた。ヒツジからはミルクと羊毛が得られるためとても有用な家畜だが、過放牧を行うと土地の荒廃を引き起こしやすい危険な動物でもある。
ヒツジによって土地が荒廃する仕組みは次の通りだ。
家畜の密度が高すぎると放牧地の草が食べつくされてしまうが、ヤギとヒツジは貪欲で、地上部分に食べる物がないと根まで食べてしまうのだ。根まで食べつくされてしまうと、牧草の復活は難しいし、根という支えが無いために土壌が流出しやすくなる。そして、土壌が流出するともはや何も生えない土地になってしまうのである。イタリア南部はローマ時代の過放牧によって荒廃し、今日でも元の状態まで回復していないと言われている。
このように、節度のない農業と牧畜が行われた理由を博物学者のプリニウス(西暦23~79年)は、広い農場を奴隷監督に任せているからだと記している。ラティフンディアでの作業員はもちろん奴隷が務めていたが、その監督も奴隷が行っていたのだ。彼らの労働意欲は高くなく、ラティフンディアの生産効率は中世期の農奴制よりもずっと低かったと言われている。つまり、ラティフンディアの拡大によってローマ帝国の農産物の生産性が下がるとともに、農地や牧草地も荒廃したのである。
さて、農地や牧草地から流出した土壌は川に流れ込むわけだが、土壌が川底に堆積すると川は氾濫しやすくなる。やがて川の氾濫が常態化すると、耕作地だった一帯が湿原化してしまった。このようにして生まれたのが、ローマの南東にある悪名高いポンティノ湿原だ。この海岸近くの湿原は幅が8~16kmで長さは約 50kmに及び、紀元前200年頃からマラリアのはびこる地として有名だった。ここが干拓地として再整備されるのは20世紀のムッソリーニの時代まで待たなければならない。
また、土壌が川を下って海に流れ込むと、河口で堆積し河口近くの港が使えなくなってしまうという事態をまねくこともあった。ローマを流れるテヴェレ川の河口にはオスティアと呼ばれる港町があったが、この港が堆積物で使用できなくなってきたのだ。
属州などからの物資はいったんオスティアに運ばれていた。そして小型の船に積み換えられてからテヴェレ川をさかのぼり、約20キロ内陸にあるローマに到着するのだ。つまり、オスティアはローマの玄関口という重要な役割を果たしていたのだが、この港の使用が難しくなってきたためローマへの物資輸送が滞り始めたのだ。ローマ人は別の場所に新しい港を作って危機を回避したが、オスティアはやがて土砂に埋まって放棄されてしまった。

オスティアの遺跡(ローマから30分くらいで行くことができる)
農地の荒廃に加えて食料生産に大きな打撃を加えたのが気候の寒冷化だ。西暦200年から400年にかけて北半球において広く寒冷化が生じたため、作物の生産量が激減したのだ。食べるものが無いと人は生きていけない。食料難の結果、2世紀に100万人を越えていた都市ローマの人口は400年には40万人まで減少した。ヨーロッパ全体でも、この期間に総人口は半減している。
ローマ帝国の版図について見てみると、最大となるのが「テルマエ・ロマエ」に登場するハドリアヌス帝などの五賢帝の時代(西暦96~180年)で、それ以降は新しい領土の獲得はできなくなる。すると、新しい征服地から奴隷が手に入らなくなり、また食料不足のため奴隷が産む子も減少したため、次第に奴隷の数が少なくなっていった。その結果、奴隷に依存していたラティフンディアはそのままでは立ち行かなくなってきたのだ。
そこで農場主は、農地を放棄した市民を小作人として大量に雇って、大規模農場を維持することとした。これをコロナトゥス制と呼ぶ。西暦332年には小作人の自由な移動を禁止する法律が出され、小作人は土地に一生涯にわたって縛り付けられることになる。このような厳しい法律が出される背景には、食料生産の急激な落ち込みがあったと考えられる。
一方、世界的な食料不足は「民族の大移動」を引き起こすことによって、古代ローマの衰退は急速に進んでいくことになる。
(次回はゲルマン人が登場します)