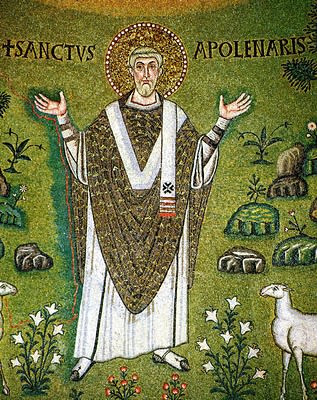南ドイツのこともまだですが、、
記憶が鮮明なうちにオランダ~ベルギー旅行を整理します。
最初の記事は、旅行記ではありませぬ。
ちょっとおもしろいことがあったので、それを書いてみようと思います。
先日ドイツの旅行ガイドをしている方にお会いする機会があり、こんなお話しをうかがいました。



日本人旅行者とある聖堂を訪れた時の事、
参加者の一人から、聖堂内の彫像の足が祭壇のほうを向いているのは何だか変な感じがしますね、と言われた。
そう言われてみると、拝む場所に足を向けるのは罰があたりそうな気もするが、
埋葬の向きというのは決まりがあるのだろうか?と考えている、と。
ヨーロッパの教会では、聖堂内の床下に死者が埋葬されていることが一般的にあり、
床に墓碑が刻まれているのをしばしば目にします。
墓は特に区切られた場所にあるのではなく、普通の床、人が通るところにもあります。

例えばこれは、画家レンブラントの妻サスキアのお墓。
石材の床に名前が彫ってあります。
(教会を訪れたとき、上を歩くのは落ち着かない気がします…。)
さて、墓の上には、死者の像が設置されていることがあります。
胸像もあれば、全身像もあるのですが、足を向けているのが不思議、、となったのは、
全身像で、寝ている状態(埋葬された時の姿)の彫刻の足が祭壇のほうを向いていたのを見たからです。
日本的な感覚で足を向けるのがうんぬん、ということはなさそうなものの、
埋葬の向きについて私も気になっていたのですが、今回の旅行で答えになりそうなことが見つかりました。

これは、ブルージュ(Brugge)の聖母教会(O. L. Vrouwekerk: Onthaalkerk)内にある
ブルゴーニュ公国のシャルル突進公と娘マリーの霊廟です。
公と公女の彫刻は寝ている姿で、手を合わせています。
どちらも主祭壇の祭壇画に足を向けていますね。
この像の足元をみてみると、公と公妃にそれぞれライオンと犬が寄り添っています。

奥のライオン、手前の犬はどちらも前方(足が向いているほう)を見上げている様子、、
祭壇を見つめていることが分かります。
つまり、これらの動物によって人物が同じく祭壇を見ていることが明確に示されている訳です。
これらの像は祭壇に向かって祈る姿が表現されています。
もしくは、ほとんどの教会はエルサレムのある東に向いているので、彼らは聖地を拝んでいるのかもしれません。
もちろんこのケースが全ての像にあてはまる訳ではありませんが、
もし訪れた教会で上記のような像を見かけて、祭壇に足を向けて寝ている、と思ったら、
それは死後も神に祈りを捧げている信仰の表現なのかもしれません。
文化によって、ものの受け取り方や表現は様々でおもしろいな、と思い、
仏壇や神棚(あるいはお世話になった人?)に足を向けるのは良くないとされるのは、どんな思想や文化から来ているのか、
アジア圏やさらには世界的にもこの考えは当てはまるのか、
崇敬や不敬の表現はどのようなものがあるのか、、色々なことが頭に浮かびます。