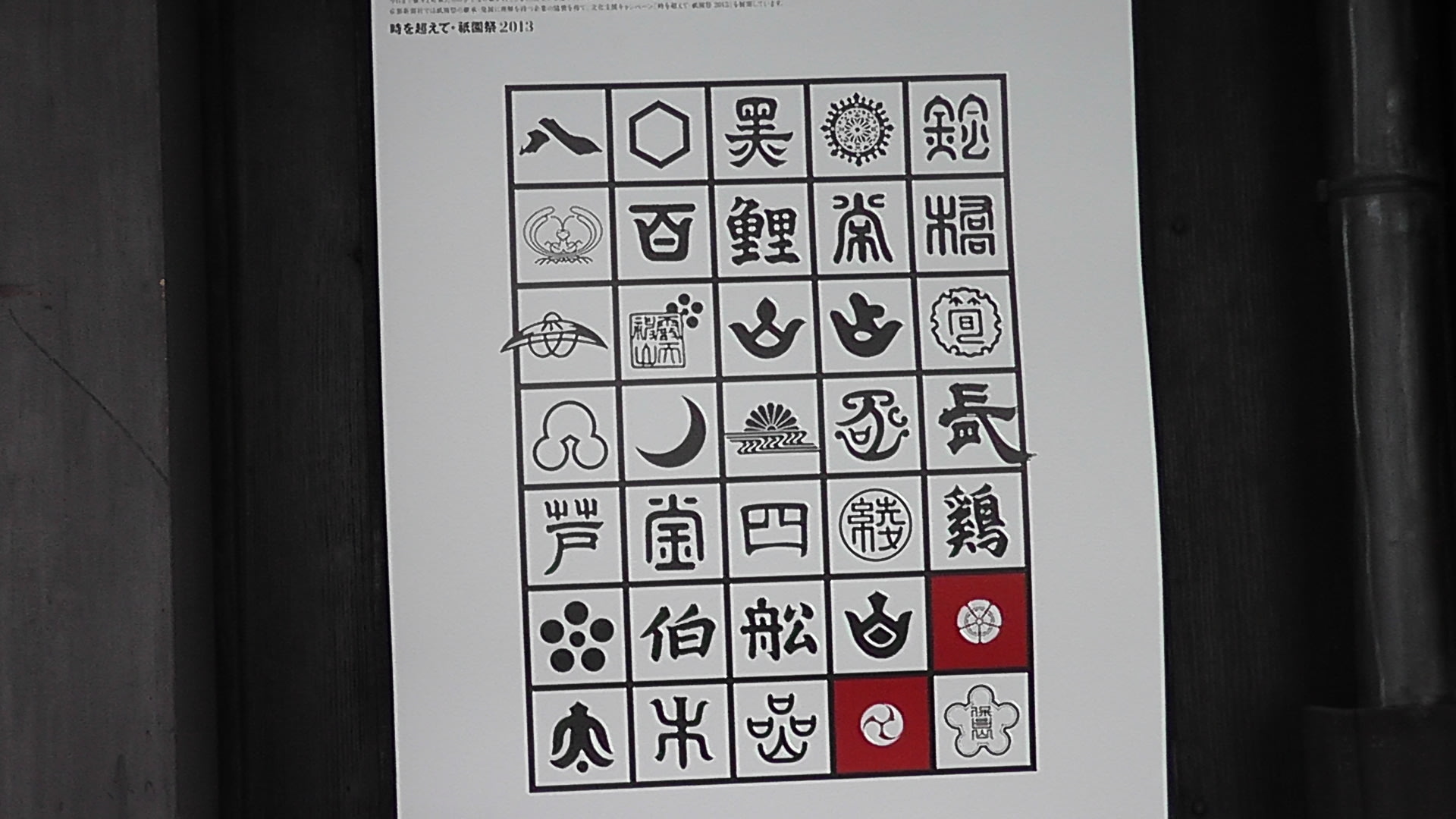今年も祇園祭が始まりました。
7月1日には、祇園祭の長刀鉾の稚児らが祭りの 無事を祈願する「お千度の 儀」が、東山区の八坂 神社で営まれました。各山鉾町 でも神事始めの吉符入りが 行われ、1カ月にわたる祇 園祭が幕を開けました。
そして昨日の7月2日には、祇園祭の山鉾巡行(17 日)の順番を決めるじ取 り式が、京都市中京区 の市役所市議会議場で行わ れました。
先頭の長刀鉾に続く 「山一番」は、去年と連続で郭巨山が引き当てました。
連続となるのは、占出山以来、37 年ぶりだそうです。
祭の最大の山場は17日の山鉾巡行ですが、鉾が建ち始める10日から、一気に祭ムードになり、巡行前日の宵山、さらには宵々山には、身動きできないくらいの人出になります。
だいだい毎年、山鉾巡行の前後に梅雨明け宣言が出されますが、この頃は蒸し暑さもピークです。
私は京都に出てきて42年が過ぎましたが、祇園祭に行き出したのはこの十数年です。
祭の山鉾が多く建つ四条烏丸周辺へのアクセスが良くなった、現在の住所に転居してからです。
毎年、祭の雰囲気を味わいに、妻と宵山にでかけますが、いつも人の多さに圧倒されてしまいます。
特に山鉾が多く建つ、室町通りや新町通りは、人が多すぎて事故が起きないか心配になります。
今までに全ての山鉾町内をまわりましたが、ゆっくり見れるのは早朝がいいです。
午前8時前後は観光客も少なく、露店も開いていないので、ゆったりとした気分で見学できます。
山鉾巡行日は、働いている時は土日以外だと行けませんでした。
今までに一度だけ巡行を見ましたが、暑くて、一緒に行った妻がギブアップしてしまいました。
今年は退職して時間もありますので、主に朝に山鉾町を巡りたいと思います。



祇園祭 主な日程(2013年版)京都新聞より
日 時刻 行事 内容説明 場所
7月1-5日 吉符入り 各山鉾町で祭礼奉仕の決定や、神事の打ち 合わせを行う 各山鉾町
1日 午前10時 長刀鉾町お千 度 町内一同が稚児を伴い参拝。神事の無事を 祈る 八坂神社
2日 午前10時 くじ取式 17日の山鉾巡行の順位を決めるため、各山 鉾町の代表者が集まり、京都市長の立ち会 いでくじをとる
京都市役所
午前11時30 分 山鉾連合会社 参 各山鉾町の代表者が八坂神社に参拝し、祭 礼の無事斎行を神前に祈願する 八坂神社
7日 午後2時30分 綾傘鉾稚児社 参 綾傘鉾に奉仕する稚児6人が、町内の役員 とともに神事の無事を祈願する 八坂神社
10-13日 鉾建て 各鉾町で、鉾を組み立てる 各鉾町 10日 午前10時 幣切 長刀鉾町の神事に必要な各種御幣を、八坂 神社の神職の奉仕で行う 長刀鉾町
午前10時 神用水清祓式 神輿(みこし)洗に使う神事用水を修祓す る。水は鴨川の水を使用する 宮川(鴨川)堤
午前11時 高橋町社参 神事の無事斎行を祈願する 八坂神社 午後1時 日本神話「語 り」奉納 「古事記」の語りが奉納される 八坂神社
午後4時30分 -9時 お迎提灯 神輿洗の神輿を迎えるため、万灯会員有志 が八坂神社を出発。周辺地域を巡り、再び 同神社に戻る コース:八坂神社→四条河原町→京都市役 所前→寺町通→四条通→八坂神社
氏子区内
午後8時 -8時30分 神輿洗式 午後6時に奉告祭執行後、神輿3基を舞殿 に据え、うち1基(中御座)をかつぎ、列 の前後にたいまつをともし、四条大橋の上 で神輿を清める儀式を行う。午後8時30分 ごろ、八坂神社に戻った後、3基の神輿を 飾り付ける
四条大橋
12-13日 鉾曳初め 囃子を奏で、それぞれの町内の中で鉾を曳 く 各鉾町
12-14日 山建て 各町内で山を組み建てる 各山町 13-14日 舁初め 町内でそれぞれの山をかつぐ 各山町 13日 午前11時 長刀鉾稚児社 参 稚児が馬に乗って八坂神社に詣で、神の使 いとして「お位」を授かる 八坂神社
午後2時 久世駒形稚児 社参 久世駒形稚児が祭りの無事を願う 八坂神社
15日 午前4時30分 斎竹建て 長刀鉾稚児が巡行当日に太刀で切る注連縄 (しめなわ)を高橋町の人々が建てる。 四条麩屋町
午前10時 月次祭並包丁 式 日本式庖丁道生間流による庖丁式が奉納さ れる 八坂神社
午後3時 祇園祭伝統芸 能奉納 今様などの伝統芸能が奉納される 八坂神社
午後8時 宵宮祭 境内の灯を消し、暗闇の中で神輿に神霊を 移す 八坂神社
16日 午前9時 献茶祭 裏千家家元による茶席 八坂神社 午前9時 豊園泉正寺榊 建て 神輿の神幸列を前行する形で、中御座神輿 の前を供奉する 東洞院仏光寺東 入ル 午後6時30分 石見神楽 スサノオノミコトの大蛇退治の舞を披露す る 八坂神社
14-16日 夕方より 宵山 山鉾を飾り、祇園囃子を奏でて祭りの雰囲 気を盛り上げる 各山鉾町
16日 夕方より 宵宮神賑 奉納行事 石段下の四条通で、鷺踊や京舞など、さま ざまな芸能の奉納が行われる 四条通
午後11時 日和神楽 翌日の山鉾巡行の晴天を願い、町家と四条 御旅所の間を往復する。長刀鉾町は午後10 時30分から、八坂神社との間を往復し、囃 子を奉納する
四条御旅所 八坂神社
17日 午前9時 山鉾巡行 祭りのクライマックス。32基の山鉾が京都 市内の中心部を巡行する 氏子区内
くじ改め 山鉾巡行で、京都市長が奉行となり順位を ただす 四条堺町
午後4時 神幸祭 神輿渡御に先立ち、本殿で祭典が行われる 八坂神社 午後6時 神輿渡御出発 式 石段下で三社神輿の差し上げが行われる。 この後、3基の神輿が氏子の地域を練り歩 き、四条御旅所に向かう
八坂神社石段下 -四条御旅所
20日 午後3時 花傘巡行宣状 授与式 花傘巡行に奉仕する馬長稚児、児武者の宣 状が交付される 八坂神社
23日 午前9時 煎茶献茶祭 煎茶道家元の輪番奉仕により行われる。常 磐殿に拝服席が設けられる 八坂神社
午後1時 琵琶奉納 琵琶協会により、琵琶の奉納が行われる 八坂神社 午後2時 オハケ清祓式 八坂神社又旅社で、「オハケ」と称して芝 を敷き、3本の御幣を立て、斎竹を四隅に 立てる
八坂神社又旅社
24日 午前10時 花傘巡行 傘鉾や馬長稚児、児武者らが石段下を出発 し、四条通などを練り歩く。八坂神社に到 着後(午後零時ごろ)、舞踊の奉納を行う
石段下- 京都市役所- 八坂神社 午後11時ご ろ 還幸祭 午後5時ごろから、四条御旅所を3基の神 輿が出発。市中を巡り、三条御供社で祭典 後、神輿に明かりを入れ、午後9時ごろか ら11時ごろまでに八坂神社に還幸。神霊を 本社に戻す
四条御旅所 -八坂神社
25日 午前11時予 定 狂言奉納 茂山忠三郎社中により狂言奉納が行われる 八坂神社
28日 午前10時 神用水清祓式 10日に同じ 宮川(鴨川)堤 午後8時 神輿洗式 10日に同じ 四条大橋 29日 午後4時 神事済奉告祭 祇園祭の終了を奉告し、神恩を感謝する 八坂神社 31日 午前10時 疫神社夏越祭 鳥居に大茅輪を設け、参拝者はこれをく ぐって厄気をはらい、護符を授かる 八坂神社境内・ 疫神社