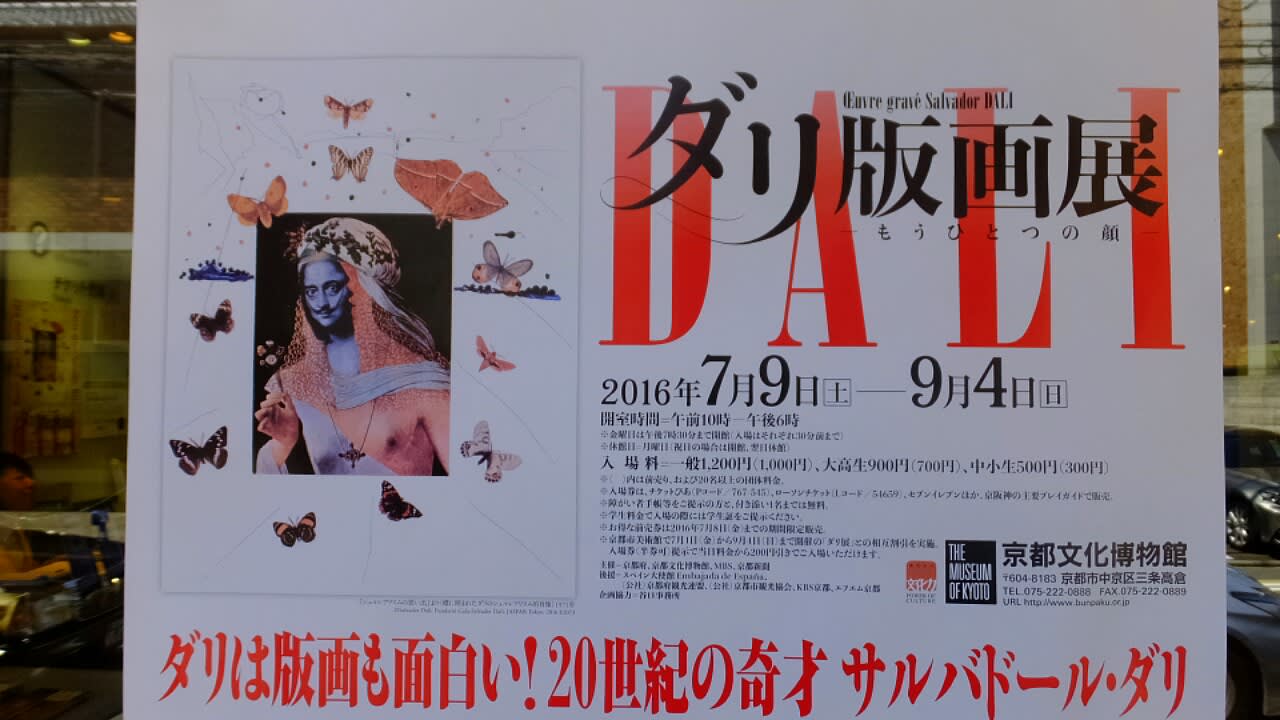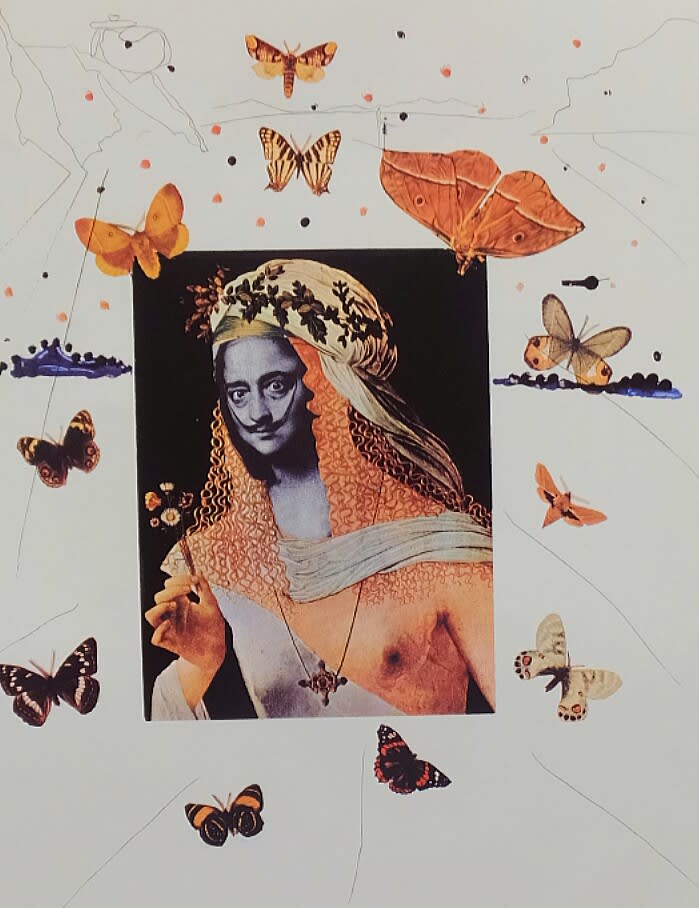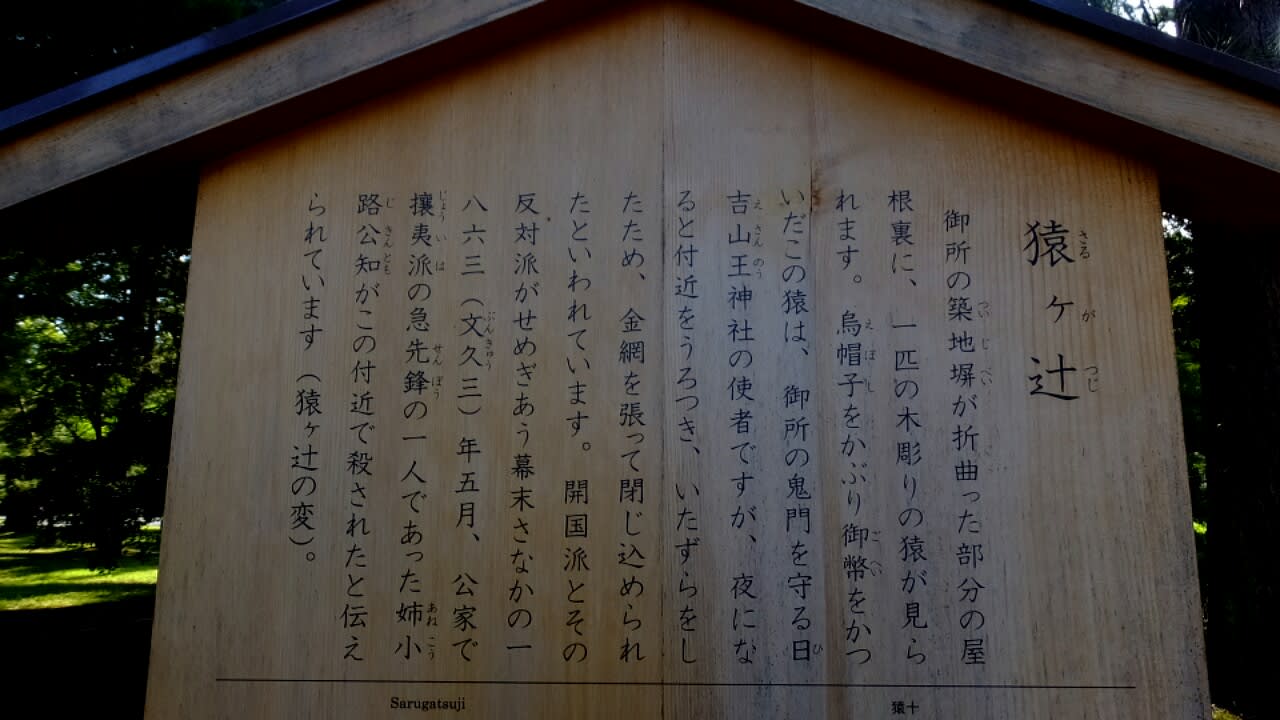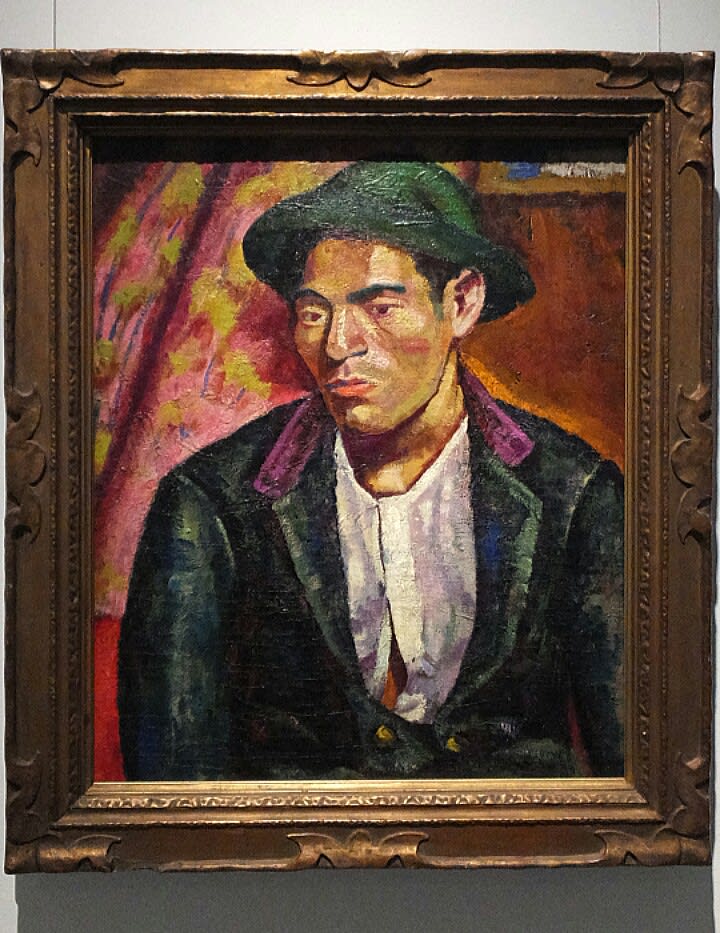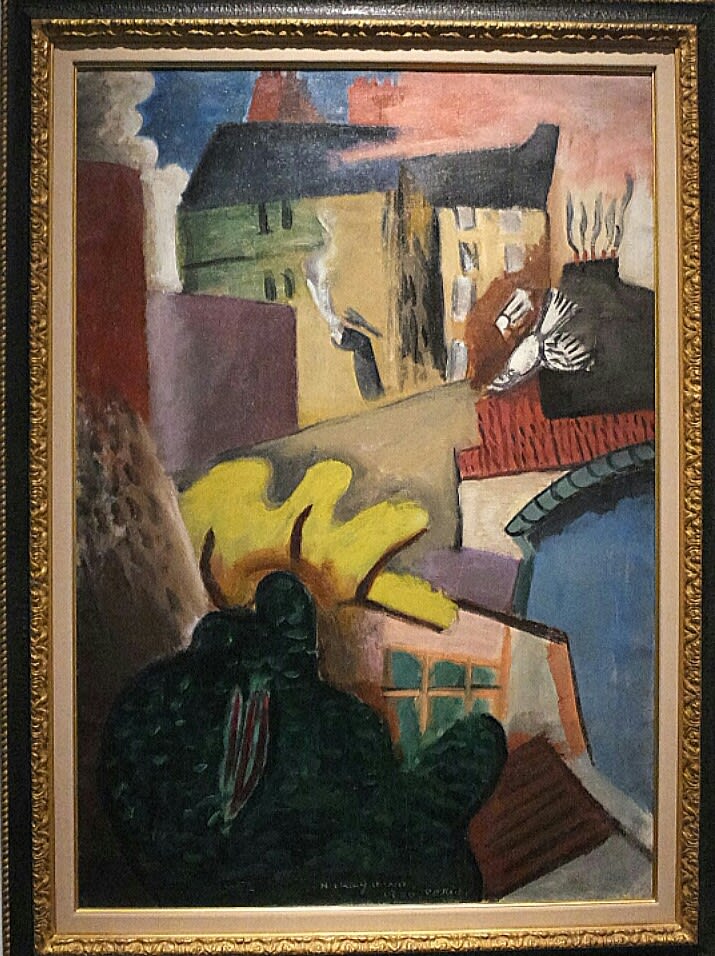昨晩は台風の影響でしょうか、京都市内に大雨洪水警報がでるほどの強い飴が降りました。
今日、明日と近畿、東海、関東とさらには災害の傷が癒える間もない東北北海道にも雨の影響がでそうです。
皆々様も御注意下さいますように。
九月に入りそろそろ彼岸花が咲く季節になりました。
彼岸花に先駆けて小彼岸花が開花し、ヒガンバナ科のリコリスも見頃になってきました。
小彼岸花(コヒガンバナ)
ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草で、原産地は中国ですが古くか日本にも帰化し、人里に近い川岸や田の縁などに生えています。
彼岸花より小さいイメージがありますが、あまり変わらないように思います。


白花彼岸花もうすぐ開花しそうです。
白花彼岸花(シロバナマンジュシャゲ)は彼岸花の雑種とされています。

リコリスは彼岸花の仲間で彼岸花より早くから開花します。
ピンク

シロバナ

赤色

蝶が蜜を吸っています。


タヌキマメ
小さな青い花を待っていたのですが、どうも開花の時期を逃してしまったようです。

ヒナタヒノコヅチ

ミズヒキ

赤トンボ

イセハナビ

オミナエシ

ヤブハギ

トウガラシ(UFOピーマン)

ホトトギス


秋咲きのシクラメン

ススキ

スペアミント花

ペパーミント花

キャットミント花

マンデビラ(キョウチクトウ科)

ジンジャー



センニチコウ


蝶