石川啄木は1886年(明治19年)生まれで、歌集『一握の砂』や『悲しき玩具』などを作っているが、啄木の短歌で記憶にあるのは次の二つで、享年27歳で亡くなっている。
「東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて蟹とたはむる」
「しらじらと氷かがやき 千鳥なく 釧路の海の冬の月かな」
前の句は、啄木が函館山から東へ伸びる“大森浜”で作ったとされている。その浜の先には、歌手 森昌子が、「立待岬」を歌ってヒットした立待岬がある。
啄木が函館にいたのは、小樽に行く前の132日間であったが、友人に向けた手紙の中で「死ぬのなら函館で」と書いていたそうで、啄木にとって波乱万丈の人生の中で、束の間の平穏な時期だったのかも知れない。
その後、年齢22歳の啄木は函館から小樽、そして釧路に行き、二つ目の句を読んでいる。その短歌を書いている歌碑は釧路港を見下ろす米町公園にあり、近くに住んでいたこともありたびたび行った。
啄木は、料亭で働いていた芸者“小奴(こやっこ)”と恋に落ちたが、現代流で言えば“不倫”であった。啄木は釧路新聞社の記者をしながら多くの短歌を残しているが、滞在期間は76日間と短い期間であった。
なお、同世代の作曲家 滝廉太郎も1879年(明治12年)に生まれており、啄木と同様に結核を患い満23歳で亡くなっている。ご存知のように滝廉太郎は、文部省唱歌の“荒城の月”や“花”を作曲している。
「十勝の活性化を考える会」会員
注) 滝廉太郎
瀧 廉太郎は、日本の音楽家、作曲家。明治の西洋音楽黎明期における代表的な音楽家の一人である。 一般的には「滝 廉太郎」と表記されることの方が多い。
1879年(明治12年)8月24日、瀧吉弘の長男として東京府芝区南佐久間町2丁目18番地(現:東京都港区西新橋2丁目)に生まれる。瀧家は江戸時代に、豊後国日出藩の家老職を代々務めた上級武士の家柄である。
1894年(明治27年)4月に同校を卒業し再度上京。同年9月東京音楽学校(現:東京芸術大学)に入学し、ピアノを橘糸重、遠山甲子に学ぶ。
彼の代表作である「荒城の月」は、「箱根八里」と並んで文部省編纂の「中学唱歌」に掲載された。
また、人気の高い曲の一つである「花」は1900年(明治33年)8月に作曲された、4曲からなる組曲『四季』の第1曲である。「お正月」、「鳩ぽっぽ」(「鳩」とは別物である)、「雪やこんこん」(文部省唱歌「雪」とは別物である)などは、日本生まれの最も古い童謡作品として知られるが、これらは1900年(明治33年)に編纂された幼稚園唱歌に収められた。
1901年(明治34年)4月、日本人の音楽家では3人目となるヨーロッパ留学生として出国し、5月18日にドイツのベルリンに到着。
同地で日本語教師を務めていた文学者の巌谷小波や、ヴァイオリニストの幸田幸、また海軍軍楽隊から派遣されたクラリネット奏者吉本光蔵(後に「君が代行進曲」作曲)などと交友を持ち、共に室内楽を演奏したりした。
文部省外国留学生として入学、ロベルト・タイヒミュラーにピアノを、ザーロモン・ヤーダスゾーンに作曲や音楽理論を学ぶが、わずか5か月後の11月に肺結核を発病し、現地の病院で入院治療するが病状は改善せず、帰国を余儀なくされる。
1902年(明治35年)7月10日にドイツを発ち、ロンドンを経由して10月17日に横浜に着く。その後は父の故郷である大分県で療養していたが、1903年(明治36年)6月29日午後5時に大分市稲荷町339番地(現:府内町)の自宅で死去した。満23歳没(享年25)。
(出典:『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

















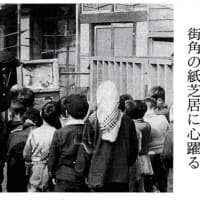


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます