アイヌ文化圏は、北海道に加えて東北6県までの広い範囲を指していた。私の母の両親は北東北出身なので、アイヌのDNAを受け継いでいる可能性が高い。東北6県出身の先祖を持つ人々が道産子には多いので、私と同様ではないだろうか。また、九州の隼人も、アイヌのDNAを持っているアイヌ語族で、九州にもアイヌ語地名があるのはそのためのようだ。
北海道は、明治政府が行なったアイヌの同化政策などによってアイヌ人口が減り、コタンが消滅したケースもある。新型コロナ禍もあって、神謡集やアイヌ文様などに見られる自然への畏敬などのアイヌ文化が見直されようとしているが、それは共生という現代日本人が失ったひとつを、アイヌ民族が色濃く持っているからだと思う。
日本人の祖先である縄文人と中国、朝鮮半島からの渡来人が混血を繰り返しながら現在の私たちがいるのである。なお、渡来人とは中国揚子江流域などから伝わった稲作を日本に持ち込み、古代の文化形成に大きな役割を演じた人々と考えられている。なお、私は青森市に住んでいたことがあるが、ここには紀元前4500年前頃にできたとされる“三内丸山遺跡”というものがある。三内丸山遺跡は大規模集落跡で、遺跡発見によりすでに稲作を作っていたことが分かり、縄文文化の定説を覆したことで有名である。
アイヌは原日本人であるので、アイヌの歴史をさかのぼることによって日本の歴史の一端が分かってくるように思う。日本人のことについては、“縄文人の核ゲノムから歴史を読み解く”と題した、国立科学博物館の研究員である神澤秀明氏のレポートが分かりやすいので、その抜粋を掲げよう。
『現在の日本列島に住む人々は、形態や遺伝的性質から大きく3つの集団、アイヌ、本土日本人、琉球人に分かれる。この3集団にはどのような成立ちがあるのだろう。数千年、土に埋もれていた縄文人のDNA配列解析から現代へとつながる歴史が見えてきた。 (中略)
現代日本列島人の成立ちを説明する学説として、1991年に形態研究に基づいて提唱された「二重構造説」がある。これは、縄文人と渡来民が徐々に混血していくことで現代の日本列島人が形成されたという説で、列島の端に住むアイヌと琉球の集団は、縄文人の遺伝要素を多く残すとしている。近年、行なわれた日本列島人の大規模なDNA解析からも、基本的にはこの説を支持する結果が得られている。』
「十勝の活性化を考える会」会長
注) アイヌ文化
アイヌ文化とは、アイヌが13世紀(鎌倉時代後半)ごろから、現在までに至る歴史の中で生み出してきた文化である。現在では、大半のアイヌは同化政策の影響もあり、日本においては日常生活が表面的には和人と大きく変わらない。
しかし、アイヌであることを隠す人達もいる中、アイヌとしての意識は、その血筋の人々の間では少なからず健在である。アイヌとしての生き方はアイヌプリとして尊重されている。アイヌ独特の文様(アイヌ文様)や口承文芸(ユカㇻ)は、北海道遺産として選定されている。
アイヌ文化という語には二つの意味がある。ひとつは文化人類学的な視点から民族集団であるアイヌ民族の保持する文化様式を指す用法であり、この場合は現代のアイヌが保持あるいは創造している文化と、彼らの祖先が保持していた文化の両方が含まれる。もうひとつは考古学的な視点から、北海道や東北地方北部の先住民が擦文文化期を脱した後に生み出した文化様式を指す用法である。
(出典:『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

















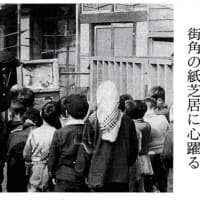


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます