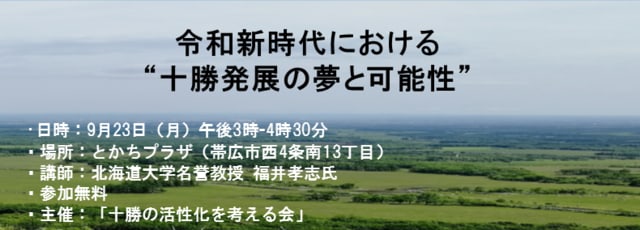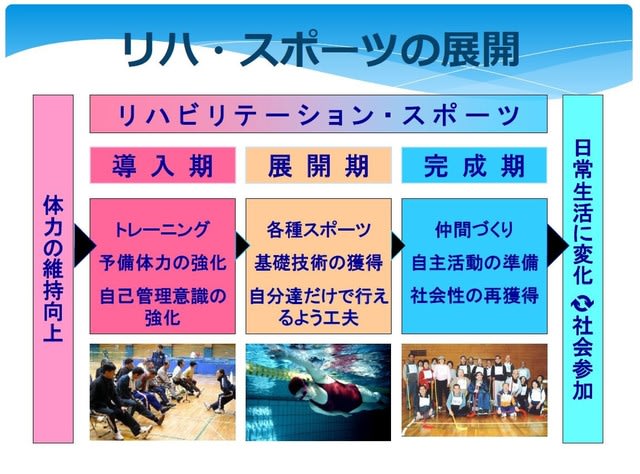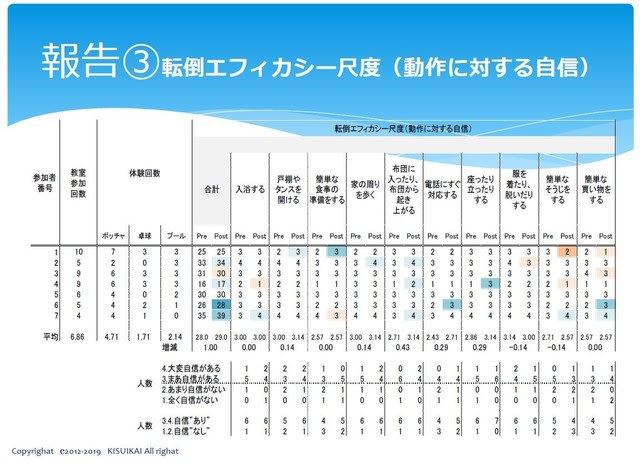私は8年前、脳出血で倒れました。そしてその後遺症で、車を出来ないなど障害を抱えています。しかし、私は障害を克服しました。その理由は、以下のとおりです。
① 自ら一歩を踏みだすこと
② 危険を恐れずチャレンジすること
③ 同じような仲間とロールプレイングすること
④ 何事もプラス思考で行なうこと
⑤ 頑固でなく柔軟であること
⑥ 生きることを楽しむこと
⑦ 努力を怠らないこと
⑧ 新陳代謝を良くすること(運動すること)
⑨ 同じ仲間がいることを忘れないこと
⑩ お互いに支え合って生きていることに気づくこと
障害は百人百様ですので、障害を克服する理由も人によって異なります。
しかし、国は障害者基本法や障害者雇用促進法の改正、障害者差別解消法の施行(平成28年4月)など国内法を整備し、制度改革を進めています。
十勝の活性化とは、障害ある人もない人も共生していくことが、活性化に繋がるひとつだと思っています。
「十勝の活性化を考える会」会長
注)障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。障害者差別解消法などと略される。
[法律概要]
- 障害者権利条約・障害者基本法に実効性を持たせるための国内法整備として制定された。
- 法律の理念を実現するために、障害を理由とする差別の解消を推進することが明記された。
- 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、障害を理由とする差別に関し、職員が適切に対応できるように必要な職員対応要領を作成する(第9条)。地方公共団体の機関も同様に、地方公共団体等職員対応要領を定めるよう努める(第10条)。
- 国(主務大臣)は、事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)を定める。国(主務大臣)は、事業者による障害を理由とする差別に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。これに従わず、虚偽の報告をした時は、罰則の対象となる(第11条、第12条)。
- 国及び地方公共団体は、障害者およびその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止または解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る(第14条)。
- 障害者に対する「合理的配慮」については、この法律では特段の定義は無いので、障害者権利条約第2条の定義によって定められる。
[障害を理由とする差別]
法は、以下の通り、事業者及び行政機関等に対し、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を提供すべきことを定めている。
[不当な差別的取扱い]
障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件をつけることなどにより、障害者の権利利益を侵害すること。法は、事業者、行政機関等いずれに対しても不当な差別的取扱いをすることを禁止している。
[合理的配慮の提供]
行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている。行政機関等については合理的配慮の提供は法的義務、事業者については努力義務として定められている。
(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』)
注)合理的配慮
合理的配慮とは、障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである。
障害者権利条約第2条に定義がある「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものである。
合理的配慮の文言が、障害者に対する差別を防止する意図で用いられた最初の例は、リハビリテーション法の施行規則(1977年)[1]だとされる。それ以降、障害を持つアメリカ人法でさらに明確に定義され、さらに障害者権利条約で採用されたことで、一般的に知られる概念となった。
障害者権利条約では、原文(英語)では「reasonable accommodation(リーゾナブル・アコモデーション)」と表記されるが、ここでいう「accommodation」は、「配慮」と翻訳されている。しかし、実際にはそれよりも具体的な意味をもつ「便宜」「助け」と解釈するのが適切でわかりやすい。自治体、公的機関、障害者支援団体、NPO等、各所で合理的配慮の具体的な事例を紹介する動きがみられる[2]。
[法的位置づけ]
合理的配慮は、障害者一人一人の必要性や、その場の状況に応じた変更や調整など、それぞれ個別な対応となる。これに併せて、民間事業者の場合と国・自治体の場合とでは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律により、法的な位置づけが異なる[3]。
[民間事業者の場合]
障害者が合理的配慮を求めた場合、負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。ただし、事業における障害者との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、求められる配慮の内容・程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については、努力義務とされている[4][5]。
国の行政機関・地方公共団体等の場合[編集]
国の行政機関・地方公共団体・独立行政法人・特殊法人等の場合は、合理的配慮を行う法的義務がある[6]。
[合理的配慮の基本的考え方]
障害のない人も、その人自身が持つ心身の機能や個人的能力だけで日常生活や社会生活を送っているわけではない。日常生活や社会生活を営むにあたり、様々な場面で人的サービス、社会的インフラの供与、権利の付与等による支援を伴う待遇や機会が与えられているのである。
ところが、こうした支援は、障害のない者を基準にして制度設計されており、障害者の存在が想定されていないことが多く、障害者はこれを利用する、その支援の恩恵を受けられないといった事態が発生することになり、社会的障壁が発生する。障害者が利用できるように合理的配慮を提供しないことは、実質的には、障害のない者との比較において障害者に対して区別、排除又は制限といった異なる取扱いをしているのと同様である。
例えば、多目的ホールでの講演において、聴衆に対するサービスとしてマイクとスピーカーが用意される。聴衆はこのサービスがないと講演内容を聞くことができない。障害がない人々に対しても、人的サービス、社会的インフラの付与などの支援(配慮)がある。障害のない人々は、これらの支援(配慮)を受けて日常生活・社会生活を送ることができる。
しかし、耳の聞こえない障害者には、この支援を利用することができない状況が発生し、これが社会的障壁となる。障害者がそうした社会的障壁を取り除くために、実質上の平等を実現するために必要な配慮を要求することを障害者の人権ととらえることは重要である。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
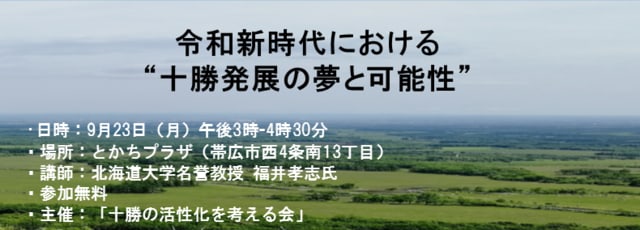
十勝の活性化を考える会」会員募集