ー 「陶芸」 が教えてくれる 15 のしあわせ ー
第三章 頭で考えようとすること
ようやく、基本的なことを教えてくれそうな教室を見付けた。休日に渋谷駅の道玄坂沿いの教室に通うことにした。手びねりを一から始めた。カリキュラムをこなし、手びねりのやり方も一通り分かってきた。
次に、電動ろくろも知っておいた方がいいだろうと思い、ろくろにもトライしてみることにした。最初は、陶土の 「菊練り」 をするが、要領が全くつかめなかった。この頃から陶芸の参考書を読むようになった。参考書には素敵な作品がたくさん掲載されていた。だが、写真の説明をしてるだけで、肝心の知りたいことが何も書かれていなかった。どの入門書を読んでも写真の真似をしてやりなさいというスタイルだった。知りたいのは、 “なぜそうするのか” ということである。それが何処にも書かれていない。どの入門書も同じようなものだった。 「自分で考えてみるしかないなぁ」 と思えた。いろいろと模索してる内に、全てに理屈があることが分かってきた。
例えば、土殺しという芯出しの時に、土を上に伸ばし下へさげる時は、時計の11時の方向に押して倒すとスルスルっと下がる。考えてみたら単純なことだった。遠心力を求心力に変えてるだけなのである。前に倒そうが手前に引き寄せようが、どちらでもよいのである。
手びねりのカリキュラムを一通りこなした頃に、穴窯による焼締め作品に魅力を感じるようになった。それからは穴窯焼成をやっている新宿駅西口前の教室に通うようにした。中野の自宅からも距離にして4 kmである。歩いてでも行ける教室だった。渋谷の陶芸教室には2年半ほど通ったことになる。
新宿駅の教室に通い始めた時に50歳前後の外人のご婦人がろくろをやっていた。ろくろの上手なフランス人だった。芯出しの土殺しを見ていると、上に伸ばした土を下へさげる時に、手前に引いている。「あれっ!」 と不思議に思って手前に引く理由を訊ねた。
流暢な日本語で、「フランスで、こう習ったんです」 と応えてくれた。
なぜ、左前方に倒すのかということは、どんな参考書にも書いてない。誰も聞いたことがないだろう。別に難しいことではない。遠心力を求心力に変えてるだけのことなのである。もう少し分かりやすく言うと、上に伸ばした土の先端部分を左前方に押すと、上の部分が傾く。回転すると傾いた頭と首が回る。誰にでも分かることだ。遠心力で回ろうとするこの頭の所を止めてあげると求心力に変わり土が下がって行くのである。土殺しは求心力を使って土を中心から上に伸ばし、求心力を使って下へさげるのである。
フランス人が手前に引いていたのは引き寄せる力が強いからだろう。体が大きく腕力のある外人とのフィジカル面の違いを感じさせられた。
数年前に私が自費出版した不朽の名著とも言われる? 『生活にうるおいを与える食器づくり』 にもこんなことを記した。読んだ人は目からうろこが落ちるだろう。(この拙著は、アマゾンや楽天ブックスで通信販売されている)
話は少し変わるが、最近は YouTube などにも電動ろくろの実演動画などが発信されている。参考になるものも多いのだが、発信してる一部の人たちのやり方なのかなと疑問を感じる動画もみられる。首をかしげたくなるような動画を見掛けることがある。それを見たろくろの経験のない人たちは恐らく 「電動ろくろって難しものだなぁ~」 と思って引いてしまうだろう。やる気が失せてしまうのではなかろうか。趣味としてスンナリと入って行けるようなやり方とは思えない。陶芸なるものが、目で見て覚える職人芸的なものだったのかもしれない。繰返しくりかえしの習練で、習得するものだったのたろう。
そこには納得できるようなロジカルな説明もない。ましてや、手びねりに通じるものがない。手びねりの手法と、電動ろくろの手法が全く切り離されていて別物になっている。
陶芸は回転という機械的な動きを伴うものである。そこには共通した理屈があってしかるべきだろう。私は陶芸も基本的なロジカルな理屈を踏まえたものであって欲しいと思っている。ただただ上手に形や作品が作れれば、どんなやり方をしてもいいよと言うものではないような気がする。茶道と同じように多少の流派の違いこそあれ、共通する作法や手法があってほしい。陶芸が趣味としても日常の生活の中に馴染めるものてあってほしいと思っている。こんなことをこの拙文の中から読み取ってもらえるだろうか・・・。
↓↓ ボチッとクリックしてね! 皆さんの応援クリックがランキングに反映されます。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング
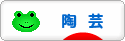 にほんブログ村
にほんブログ村 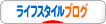 にほんブログ村
にほんブログ村
第三章 頭で考えようとすること
ようやく、基本的なことを教えてくれそうな教室を見付けた。休日に渋谷駅の道玄坂沿いの教室に通うことにした。手びねりを一から始めた。カリキュラムをこなし、手びねりのやり方も一通り分かってきた。
次に、電動ろくろも知っておいた方がいいだろうと思い、ろくろにもトライしてみることにした。最初は、陶土の 「菊練り」 をするが、要領が全くつかめなかった。この頃から陶芸の参考書を読むようになった。参考書には素敵な作品がたくさん掲載されていた。だが、写真の説明をしてるだけで、肝心の知りたいことが何も書かれていなかった。どの入門書を読んでも写真の真似をしてやりなさいというスタイルだった。知りたいのは、 “なぜそうするのか” ということである。それが何処にも書かれていない。どの入門書も同じようなものだった。 「自分で考えてみるしかないなぁ」 と思えた。いろいろと模索してる内に、全てに理屈があることが分かってきた。
例えば、土殺しという芯出しの時に、土を上に伸ばし下へさげる時は、時計の11時の方向に押して倒すとスルスルっと下がる。考えてみたら単純なことだった。遠心力を求心力に変えてるだけなのである。前に倒そうが手前に引き寄せようが、どちらでもよいのである。
手びねりのカリキュラムを一通りこなした頃に、穴窯による焼締め作品に魅力を感じるようになった。それからは穴窯焼成をやっている新宿駅西口前の教室に通うようにした。中野の自宅からも距離にして4 kmである。歩いてでも行ける教室だった。渋谷の陶芸教室には2年半ほど通ったことになる。
新宿駅の教室に通い始めた時に50歳前後の外人のご婦人がろくろをやっていた。ろくろの上手なフランス人だった。芯出しの土殺しを見ていると、上に伸ばした土を下へさげる時に、手前に引いている。「あれっ!」 と不思議に思って手前に引く理由を訊ねた。
流暢な日本語で、「フランスで、こう習ったんです」 と応えてくれた。
なぜ、左前方に倒すのかということは、どんな参考書にも書いてない。誰も聞いたことがないだろう。別に難しいことではない。遠心力を求心力に変えてるだけのことなのである。もう少し分かりやすく言うと、上に伸ばした土の先端部分を左前方に押すと、上の部分が傾く。回転すると傾いた頭と首が回る。誰にでも分かることだ。遠心力で回ろうとするこの頭の所を止めてあげると求心力に変わり土が下がって行くのである。土殺しは求心力を使って土を中心から上に伸ばし、求心力を使って下へさげるのである。
フランス人が手前に引いていたのは引き寄せる力が強いからだろう。体が大きく腕力のある外人とのフィジカル面の違いを感じさせられた。
数年前に私が自費出版した不朽の名著とも言われる? 『生活にうるおいを与える食器づくり』 にもこんなことを記した。読んだ人は目からうろこが落ちるだろう。(この拙著は、アマゾンや楽天ブックスで通信販売されている)
話は少し変わるが、最近は YouTube などにも電動ろくろの実演動画などが発信されている。参考になるものも多いのだが、発信してる一部の人たちのやり方なのかなと疑問を感じる動画もみられる。首をかしげたくなるような動画を見掛けることがある。それを見たろくろの経験のない人たちは恐らく 「電動ろくろって難しものだなぁ~」 と思って引いてしまうだろう。やる気が失せてしまうのではなかろうか。趣味としてスンナリと入って行けるようなやり方とは思えない。陶芸なるものが、目で見て覚える職人芸的なものだったのかもしれない。繰返しくりかえしの習練で、習得するものだったのたろう。
そこには納得できるようなロジカルな説明もない。ましてや、手びねりに通じるものがない。手びねりの手法と、電動ろくろの手法が全く切り離されていて別物になっている。
陶芸は回転という機械的な動きを伴うものである。そこには共通した理屈があってしかるべきだろう。私は陶芸も基本的なロジカルな理屈を踏まえたものであって欲しいと思っている。ただただ上手に形や作品が作れれば、どんなやり方をしてもいいよと言うものではないような気がする。茶道と同じように多少の流派の違いこそあれ、共通する作法や手法があってほしい。陶芸が趣味としても日常の生活の中に馴染めるものてあってほしいと思っている。こんなことをこの拙文の中から読み取ってもらえるだろうか・・・。
↓↓ ボチッとクリックしてね! 皆さんの応援クリックがランキングに反映されます。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング


















