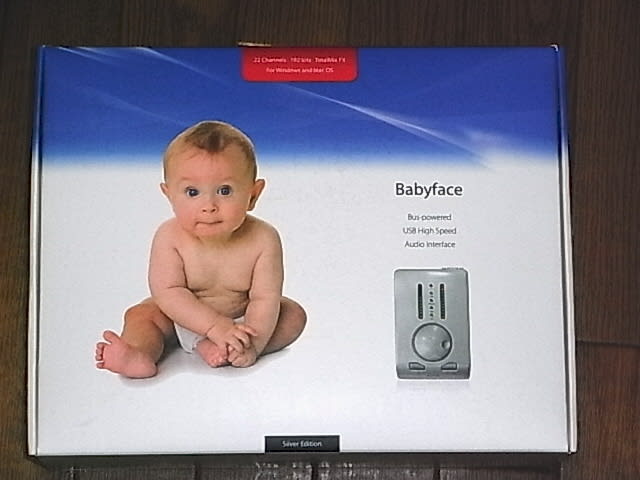問題はアンプです。正直あまりお金はかけたくないですが、それ以上にスペースの問題が大きいです。可能であればデスクトップ用のミニアンプにしたいところ。候補はFOSTEXのAP15dですが、出力が15W+15Wでこのクラスで果たして明確な差が出るのかことが難しいところです。

そこで考えたのは、現在使っているLXA-OT1の後継というか上位のLXA-OT3というアンプ。これも雑誌のフロクです。電源が強化されてAP15dと同等の12W+12Wです。雑誌自体は売り切れですが、アンプ本体は出版社の直販サイト買えます。2台セットで3780円。基盤のみですが、LXA-OT1用のケースがそのまま使えるようです。AmpBaseという名前のこのケース(というか名前のとおり基板を固定する台座ですね)ですが、質感が良くお気に入りなのです。

で、注文してしまいました。待たされる予定が意外と早く到着。基盤の色がLXA-OT1の緑から赤になっています。ACアダプターも大きくなり15Vとなっています。早速ケースからLXA-OT1を外してLXA-OT3に換装、スモークカラーのアクリルフードをかぶせると見た目は全く変わりません。正直あまり期待しないで音出しをしたものの、これが大当たり!
まず聴感上のS/N比が明らかに違っていて、以前から感じていた音の紙臭さが払拭され、音がクリーン。そして、低音の質の改善。抑制の効いていない音の輪郭があいまいな低音からしっかりコントロールされた弾むような低音への様変わり。さらに中高域の抜けが明らかに違う。一番違いを感じるのは歌もの再生したときで、ストレスなく朗々と歌ってくれます。しばらく聴き入ってしまったぐらい。
ここまで鳴るのであればアンプはLXA-OT3で固定して他を詰めていった方がいいと判断しました。このアンプに限らず、中華デジアンも含めて気になるのがACアダプター。コストの兼ね合いもあるので、当然スイッチングですし、それほどいいものは使われていないと思われます。せめてトランス式のACアダプターをと思って探していたら、見つけてしまいました。LXA-OT3用のトランス電源キット。OIトランスを使用したキットで、内部配線をつなぎかえることで12V仕様にもなるとのこと。中華デジアンも12V仕様のものも多いので流用もできそうな感じです。DACで電源の重要性を思い知らされたので、ちょっとお高めですがこれを導入してみます。
(まだまだいくよ。)

そこで考えたのは、現在使っているLXA-OT1の後継というか上位のLXA-OT3というアンプ。これも雑誌のフロクです。電源が強化されてAP15dと同等の12W+12Wです。雑誌自体は売り切れですが、アンプ本体は出版社の直販サイト買えます。2台セットで3780円。基盤のみですが、LXA-OT1用のケースがそのまま使えるようです。AmpBaseという名前のこのケース(というか名前のとおり基板を固定する台座ですね)ですが、質感が良くお気に入りなのです。

で、注文してしまいました。待たされる予定が意外と早く到着。基盤の色がLXA-OT1の緑から赤になっています。ACアダプターも大きくなり15Vとなっています。早速ケースからLXA-OT1を外してLXA-OT3に換装、スモークカラーのアクリルフードをかぶせると見た目は全く変わりません。正直あまり期待しないで音出しをしたものの、これが大当たり!
まず聴感上のS/N比が明らかに違っていて、以前から感じていた音の紙臭さが払拭され、音がクリーン。そして、低音の質の改善。抑制の効いていない音の輪郭があいまいな低音からしっかりコントロールされた弾むような低音への様変わり。さらに中高域の抜けが明らかに違う。一番違いを感じるのは歌もの再生したときで、ストレスなく朗々と歌ってくれます。しばらく聴き入ってしまったぐらい。
ここまで鳴るのであればアンプはLXA-OT3で固定して他を詰めていった方がいいと判断しました。このアンプに限らず、中華デジアンも含めて気になるのがACアダプター。コストの兼ね合いもあるので、当然スイッチングですし、それほどいいものは使われていないと思われます。せめてトランス式のACアダプターをと思って探していたら、見つけてしまいました。LXA-OT3用のトランス電源キット。OIトランスを使用したキットで、内部配線をつなぎかえることで12V仕様にもなるとのこと。中華デジアンも12V仕様のものも多いので流用もできそうな感じです。DACで電源の重要性を思い知らされたので、ちょっとお高めですがこれを導入してみます。
(まだまだいくよ。)