
2010年度 2冊目
『宮田登 日本を語る 4 俗信の世界』
宮田登 著
吉川弘文館
2006年5月10日 第1版
P.226 2600円(+税)
昨年宮田登先生の 『宮田登 日本を語る』シリーズ全16巻のうち半分の8たちを購入。
まだ読んでなかった『宮田登 日本を語る 4 俗信の世界』を読了。
過去わたしが読んだ日本を語るシリーズは
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14
の12冊であり、残り 4冊。
1、12、15、16
になる。
購入した8冊の中には1、12、15を含んでいないので、日本を語るシリーズはなかなかすべてを読むに至らないということになる。
これは少々購入の仕方を間違ったかとも思うが、再読したいものを中心に購入したのだから仕方が無い。(笑み)
『宮田登 日本を語る 4 俗信の世界』も面白く得ると頃がおおかった。
吉川弘文館の案内によると、津具のように目次が設定されている。
目次
=祈りの民俗(人は神仏に何を祈るか/民間信仰と現世利益/江戸時代に再編成された日本の宗教/奇怪なる神々/絵馬について/江戸の絵馬―絵馬の由来と変遷―/安産の神仏たち)/=俗信と心意(俗信の世界/日本民俗信仰に表われた“符呪”/日本人と匂い/辻のフォークロア/神霊・怪異の音/餅の呪力―里の食物誌―/日本の数信仰/名前のフォークロア―命名の心意―/俗信の諸相)/=世相と俗信(日本コスモロジー―現代における宗教の意味と意義―/現代都市の怪異―恐怖の増殖―/現代都市の命運―都市の民俗学序説―/民俗学からみた
『俗信の世界 4』では
絵馬、
安産の神仏、
言霊、
鬼門、
都市の禁忌
人は神や仏に何を祈るのか
など、興味深い内容がわかりやすくとかれ、風邪の体をいたわりつつ楽しむのにはもってこいの本であった。
餅なし正月
左義長
といった今の季節にふさわしい内容もこの本でも書かれており、興味深く読む。
食事時娘にきかせ、楽しむ。
そういうともうすぐどんどやき。
x著書(単著)
『生き神信仰』 塙書房〈塙選書〉、1970年
『ミロク信仰の研究 日本における伝統的メシア観』 未來社、1970年
『近世の流行神』 評論社、1972年 (のち『江戸のはやり神』と改題)
『原初的思考 白のフォークロア』 大和書房、1974年
『民俗宗教論の課題』 未來社、1977年
『叢書身体の思想6 土の思想』 創文社、1977年
『日本の民俗学』 講談社〈講談社学術文庫〉、1978年
『神の民俗誌』 岩波書店〈岩波新書〉、1979年
『新しい世界への祈り弥勒 日本人の信仰』 佼成出版社、1980年
『江戸歳時記 都市民俗誌の試み』 吉川弘文館、1981年
『都市民俗論の課題』 未來社、1982年
『女の霊力と家の神 日本の民俗宗教』 人文書院、1983年
『妖怪の民俗学 日本の見えない空間』 岩波書店、1985年
『現代民俗論の課題』 未來社、1986年
『ヒメの民俗学』 青土社、1987年
『終末観の民俗学』 弘文堂、1987年
『霊魂の民俗学』 日本エディタースクール出版部、1988年
『江戸の小さな神々』 青土社、1989年
『民俗学』 放送大学教育振興会、1990年
『怖さはどこからくるのか』 筑摩書房、1991年
『日和見 日本王権論の試み』 平凡社〈平凡社選書〉、1992年
『「心なおし」はなぜ流行る 不安と幻想の民俗誌』 小学館、1993年
『山と里の信仰史』 吉川弘文館、1993年
『民俗文化史』 放送大学教育振興会、1995年
『ケガレの民俗誌 差別の文化的要因』 人文書院、1996年
『老人と子供の民俗学』 白水社、1996年
『民俗学への招待』 筑摩書房〈ちくま新書〉、1996年
『民俗神道論 民間信仰のダイナミズム』 春秋社、1996年
『歴史と民俗のあいだ 海と都市の視点から』 吉川弘文館〈歴史文化ライブラリー〉、1996年
『正月とハレの日の民俗学』 大和書房、1997年
『日本の50年日本の200年 日本人と宗教』 岩波書店、1999年
『冠婚葬祭』 岩波書店〈岩波新書〉、1999年
『都市とフォークロア』 御茶の水書房、1999年
『都市空間の怪異』 角川書店〈角川選書〉、2001年
『宮田登日本を語る』 吉川弘文館、2006-2007年
*(1)民俗学への道
*(2)すくいの神とお富士さん
*(3)はやり神と民衆宗教
*(4)俗信の世界
*(5)暮らしと年中行事
*(6)カミとホトケのあいだ
*(7)霊魂と旅のフォークロア
*(8)ユートピアとウマレキヨマリ
*(9)都市の民俗学
*(10)王権と日和見
*(11)女の民俗学
*(12)子ども・老人と性
*(13)妖怪と伝説
*(14)海と山の民俗
*(15)民俗学を支えた人びと
*(16)民俗学の方法
最新の画像もっと見る

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。
最近の「民俗学、柳田國男、赤松啓介、宮田登、折口信夫」カテゴリーもっと見る

『狐猿随筆』 柳田國男 岩波書店(2011/03発売) /バッハ Bach: 無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長/

『身毒丸 』 折口信夫 23 彼の聨想が、ふと一つの考へに行き当つた時に、跳ね起された石の下から、水が涌き出したやうに、懐しいが、しかし、せつない心地が漲つて出た。

『身毒丸 』 折口信夫 22 彼は花の上にくづれ伏して、大きい声をあげて泣いた。すると、物音がしたので、ふつと仰むくと、窓は頭の上にあつた。

『身毒丸 』 折口信夫 21 彼は耳もと迄来てゐる凄い沈黙から脱け出ようと唯むやみに音立てゝ笹の中をあるく。

『身毒丸 』 折口信夫 20 あけの日は、東が白みかけると、あちらでもこちらでも蝉が鳴き立てた。昨日の暑さで、一晩のうちに生れたのだらう、と話しあうた。
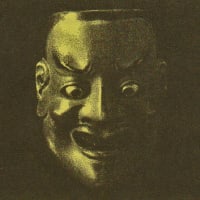
『身毒丸 』 折口信夫 19 分別男や身毒の予期した語は、その脣からは洩れないで、劬る様な語が、身毒のさゝくれ立つた心持ちを和げた。
最近の記事

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 20 中巻読了(次回から下巻) 東海道を行く官軍 朝廷からはさらに軍勢を下総に向かわせた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 19 中巻 秀郷は、三井寺斗その守護神である新羅大明神に参拝して加護を祈り、下総に向かった。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 18 中巻 将門に対面する秀郷 将門の服装や食事の態度が不作法なのを見て、秀郷は軽蔑し、考えを変えた。

『サルヴァドール・ダリ&アルフォンス・ミュシャ(ムハ)展』内『ダリ展』のみ 全26景
カテゴリー
- 繰り返し記号 memo(5)
- 読書全般(古典など以外の一般書)(1057)
- 哲学(129)
- ギリシア神話(53)
- 古典全般(奈良〜江戸時代)(44)
- 漢文(7)
- 文学入門(17)
- 民俗考・伝承・講演(194)
- 民俗学、柳田國男、赤松啓介、宮田登、折口信夫(176)
- 絵巻物、縁起絵巻、巻物、絵解き掛け軸、屏風(223)
- 変体仮名見むとするハいとをかし(43)
- 草双紙:洒落本、仮名草子、黄表紙、黒本、赤本、合巻 等(109)
- 絵本百物語 桃山人著(11)
- 疫病:疱瘡心得草 他(24)
- 俳諧、連句(『役者手鑑』などを含む)、狂歌(18)
- 在原業平、そして、伊勢物語 と、仮名草子 仁勢物語(125)
- 紀貫之(20)
- 菅原道眞(37)
- 説経節、幸若舞、舞の本等(31)
- 浄瑠璃、文楽について(2)
- 近松門左衛門(87)
- 滝沢馬琴(43)
- 井原西鶴(140)
- 山東京傳(140)
- 十返舎一九(44)
- 式亭三馬(3)
- 古事記、日本書紀(5)
- 梁塵秘抄(今様)(5)
- 鴨長明(6)
- 竹取物語(3)
- 源氏物語(35)
- 枕草子(137)
- つれ/″\種→徒然草 詳密色彩大和絵本(八十六段より)(40)
- 和歌、短歌(43)
- 本居宣長 『古今集遠鏡』『玉あられ』(37)
- 藤原定家『明月記』(5)
- 名作歌舞伎全集/古典文学全集(浄瑠璃含)、歌舞伎関係本(39)
- 観世流(続)百番集、日本古典文学大系(謡曲)、能楽関係本(68)
- ことのは(276)
- 書道(2)
- お出かけ(1090)
- 110㏄でお出かけ(5)
- 神社仏閣・祭り(190)
- 美術・文様・展示物(348)
- 歌舞伎(135)
- 能楽・狂言(98)
- 舞台・芝居(100)
- TVで 歌舞伎・能楽(376)
- TVで舞台(74)
- 音楽Live(45)
- クラッシック音楽(43)
- 映画(1026)
- ドラマ(208)
- 舞台・音楽 雑感メモ(470)
- イラン2007~2010(6回)(120)
- 中国 2006~2019(7回)・台湾・ベトナム(122)
- オーストリア・チェコ(22)
- トルコ・エジプト(51)
- 資料での旅(11)
- ヨーキなモモちゃん(26)
- 乱鳥徒然 Rancho's room.(1630)
- Ranking(順番考え1,2,3!)(6)
- 落書き Rancho's picture. 2022年月から(8)
- 外メシ、うまし。家メシ、うまし。昼弁当は、尚も良し。(32)
- ブックマーク(2013年時点)追加予定(1)
バックナンバー
人気記事



