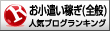「まあ、スパシーバ王子様では・・・」
「そうです、スパシーバです。ご無沙汰していました」 彼がそう言ってもリューバ姫は絶句したまま、なかなか言葉が出てきません。「どうして、あなた様がここに・・・」と言うのがやっとでした。
「ごめんなさい。あなたにぜひ会いたくて、やって来たのです。私の商人(あきんど)姿は満更でもなかったですか、ハッハッハッハ。ところで、私が忍び込んできたことは、もちろん内密にしてくださいよ」
「ええ、それはもう・・・でも、本当に驚きました。和平交渉の時以来ですね」
「あの時は、あなたの美しさに見とれていました。今はそれよりもさらに美しくなりましたね。ずっとここにいたい気持です」
「まあ・・・」
「僕はあなたのことが忘れられず、どうしても会いたくて来ました。もし、ここで素性がばれ逮捕されようとも、あなたにお会いできたのですから、何の後悔もありません。それほど会いたかったのです。 あなたを愛しています」
「・・・」
「僕ばかりがしゃべって申し訳ないですが、今日は突然だったので、あなたも答えようがないでしょう。でも、僕の真心が本当だということを是非知っていただきたいのです。僕は永久にあなたを愛していきます」
「でも、あまりに突然で・・・」
「それは本当に申し訳ない。もちろん、今すぐに返事をいただこうなどとは思いません。ただ、私がここにいる限り、何度でもお邪魔したいと思っています。あなたの返事がもらえるまで来るつもりです。どうか私の真心、誠意を信じてください。それだけです」
「ロマンス国では、他国の異性とは交際できない“掟”があります。それはご存知でしょうか」 リューバ姫がようやくまともに口を開きました。
「それは知っています。でも、おかしいと思いませんか。自国であろうと他国であろうと、愛する人同士が結ばれるのは自然ではないですか。いえ、それこそ神様のご意思だと思います。こういう言い方が変だというなら、今はそういう時代になったのではありませんか。いつまでも封建的な物の考え方をしていたら、この世は全く進歩しません。人間が不幸になるだけです」
「その考えは分かります。私も同じような気持でいました。でも・・・私たち二人は、カラフト国の王子とロマンス国の王女という“立場”ではありませんか。そう簡単に、自由に・・・」 リューバ姫は途中で言葉が出なくなりました。
「その“立場”というのが問題です。人間は身分や地位に関係なく、自由平等であるべきです。それが理想であり、私たちはそういう社会を目指して・・・ごめんなさい、こういう話はやめましょう。 私はただあなたを愛しているだけです」 この後も、スパシーバは自分の愛する気持を熱く、真剣に語っていきました。リューバ姫はほとんど聞き役に回っていたのです。
最後に、スパシーバ王子は再訪問の約束をリューバ姫から取り付けました。彼女はその方法として、侍女のカリンカを必ず通すようにと言い残しました。カリンカは最も信頼の置ける侍女のようで、これでスパシーバは再訪問の望みをかなえたのです。
それから数日して、スパシーバ王子は独りで王宮を訪れ、若い守衛にカラフト国の商人だと告げ、侍女のカリンカへの取次ぎを頼みました。間もなくして、中年の女性が現われましたが、その人がカリンカだったのです。 彼女はリューバ姫から指示を受けていたらしく、スパシーバをすぐに姫の居室へ案内しました。
彼は今日中に話をつけようと決意を固めていました。もとより、リューバ姫がスパシーバの愛を簡単に受け入れてくれると楽観してはいませんでしたが、先日の訪問で良い感触を得たと思っていたのです。 一方、リューバ姫はこの数日間 悩み抜いていました。彼女は和平交渉の時から、“敵方”のスパシーバ王子に好意を抱いていたのです。それは彼がりりしい青年であるばかりでなく、誠意を持って難しい交渉に当たってくれたからです。あの3日間の話し合いで両国の和平が成立したのは、何と言っても王子の優れた指導力、包容力があったからだと内心思っていました。
このため、リューバ姫はスパシーバに対し一種の尊敬の気持、いや、はっきり言って好意を抱いていたのですが、そのことは誰にも言いませんでした。もちろん、相手がカラフト国の王子であり、自分はロマンス国の王女だという立場をわきまえていたからです。 しかし、スパシーバ王子が商人の姿に身をやつしてまで、自分に会いに来てくれたことに大きなショックを受けました。生まれて初めて、異性の熱烈な愛の告白を受けて、心が激しく動揺したのです。
スパシーバははっきりと切り出しました。「姫、私の愛を受け入れてくれるのなら、こんな喜びはありません。もう死んでもいいくらいです。いや、死ぬまで一緒にいましょう。どうですか、私の愛を受け入れてくれますね」
リューバ姫は答えました。「あなたのお気持はよく分かります。私も同じような気持になりました。でも・・・」
「でもって、どういうことですか・・・ ああ、それは分かります。あなたはこの国の王女だし、ご両親の了解がなければ結婚などできないでしょう。それに、この国は・・・」
「この国は、他国の異性とは付き合うこともできないのです。まして、結婚など・・・」
「ですから、はっきりと申しましょう。私と一緒に逃げてください! それしかありません」
「・・・」
「あなたは迷っていますね。当然です。私と一緒に逃げることは、この国を、また国王ご夫妻を捨てることになります。とんでもないことです。それでも、私はお願いします。私の愛を受け入れてください」
リューバ姫の表情は苦悶に満ちあふれました。しかし、スパシーバはなおも続けます。
「もし、私の愛を受け入れてくれないのであれば、私はこれから貴国の裁判所に“出頭”します。そのくらいの覚悟はできています。逮捕されようと囚人になろうとも構いません! 私は愛するあなたのためなら、どうなろうとも構いません!」
リューバ姫は感動と苦悶になす術がなく、テーブルに顔を埋めるように泣き崩れました。
それを見て、スパシーバ王子はリューバ姫の足元にひざまずきました。彼は姫の手を優しく握ると、「ごめんなさい。私の言い方があまりにも激しかったようです」と述べました。
「やめてください。おやめになって・・・」 リューバ姫はそれしか言うことができません。彼女はむせび泣くだけでした。二人の間に暫く沈黙が続きます。
やがて、スパシーバが言いました。「姫、私の決心は変わりません。それで宜しいですか」 リューバ姫はかすかな声で「はい」と答えました。その瞬間、スパシーバの全身に喜びがあふれ、彼はリューバ姫を抱きしめました。でも、彼女の体が炎のように熱くなっていたので、思わずたじろいだのです。
リューバ姫はもう涙を見せませんでした。彼女も決心がついたのです。スパシーバは言いました。「このまま国王ご夫妻の所へ行って、お許しを請いましょうか」
「いえ、結構です。父も母も決して許してくれません。それは分かっています。私は決心がついたのです。あなたの後に従うだけです」 リューバ姫はしっかりと答えました。
それから、どのくらい時間がたったでしょうか。二人は短い会話を続けましたが、リューバ姫は両親に“置き手紙”を書くと述べました。この時代、政略結婚さえ認められていないのですから、異国同士の恋人が結ばれるには、いわゆる“駆け落ち”しかなかったのでしょう。
スパシーバ王子は逃避行の計画も話しましたが、あまり具体的には語りませんでした。なぜなら、リューバ姫が全てを彼に任せていたからです。ただし、彼女は侍女のカリンカを連れて行くことだけは、スパシーバに認めさせました。姫にとって、カリンカは掛け替えのない忠実な人だったのです。
数日後の王宮脱出を約束した後、別れ際に、スパシーバは狂おしいまでにリューバ姫の唇を奪いました。二人の唇、二人の体は炎のように燃え上がったのです。
ついにその日がきました。数日後の夜、スパシーバ王子は家来1人を連れて王宮を訪問しました。守衛にカリンカに会いたいと言うと、連絡を受けた彼女が姿を現わしました。カリンカは“何か”を守衛に手渡すと、その守衛はにっこり笑って立ち去ったのです。全てカリンカの手筈どおりに進みました。
やがて、黒い服に身を包んだリューバ姫が現われました。スパシーバは彼女の手を取ると、外に用意していた荷馬車へと小走りに案内しました。カリンカもその後に続き3人が乗ると、御者になった家来が荷馬車を出発させました。こうして、リューバ姫は王宮を脱出でき、スパシーバ王子と共に一路 南へ南へと向かったのです。
翌日、姿を見せない娘のことを不審に思って、母のカチューシャ王妃はリューバ姫の居室を訪れました。そして、テーブルの上にあった置き手紙を発見したのです。そこには、「父上様、母上様。親不孝なリューバをお許しください・・・」で始まる書置きがしてありました。驚いた王妃はすぐに、その手紙を持ってツルハゲ王の所へ跳んで行きました。手紙には、スパシーバ王子とカラフト国へ行くこともはっきりと書いてあったのです。
これを知った時のツルハゲ王の形相といったら、凄まじいものがありました。怒り心頭に発するとはこのことです。まさに“禿げ頭”から湯気が出る感じでした。「許せん! 絶対に許せん!」と、王は叫びました。彼はすぐに侍従長を呼びつけ、脱走したリューバ姫らを捕らえるよう命令を下したのです。
王女が脱走したという話は、王宮の内外にあっという間に広まりました。こんな大事件は滅多にないことです。まして、国王夫妻が最も愛する自慢のリューバ姫が脱走したのです。人々は寄ると触ると、この話で持ち切りになりました。
さらに、ついこの間まで敵国であったカラフト国の王子が、ロマンス国の王女を連れ去ったのです。多くの人が「これは拉致だ、略奪だ、略奪婚だ!」と騒ぎ立てました。 最愛の娘を奪われたツルハゲ王は、もう立つ瀬がありません。面目丸つぶれです。何とかしなければなりません。
でも、この“王女略奪・脱走事件”が、やがて途方もない大動乱へ発展していくとは、どれほどの人が予測したでしょうか・・・
スパシーバ王子とリューバ姫の一行は、大急ぎで国境を目指しました。もたもたしていたら、ツルハゲ王の追っ手に捕まるかもしれません。そうなったら一巻の終わりです。王子と姫は永久に結ばれないでしょう。荷馬車の一行は夜を日に継いで必死に逃げました。もちろん、現代と違って通報手段がほとんどない時代ですから、逃げるが勝ちだったのです。
それでも何日もかかって、一行は国境にたどり着きました。これを越えれば王子のカラフト国なのでもう安全です。国境と言っても、警備兵が沢山いるわけではありません。主な道路の数カ所に検問所があるだけです。山間(やまあい)の細い道を通れば全く問題はなかったのです。
国境のある所に着いた時、リューバ姫はカリンカに「これ以上、私について来なくてももう大丈夫です。あなたの好きなようにしたらどうですか」と言いました。すると、カリンカは「王女様、何を言うのですか。あなたをお守りするのが私の役目です!」と、どこまでも姫に付き従う決意を表わしました。カリンカはリューバ姫が子供の頃から守役に徹していたのです。こうして4人の一行はカラフト国に入り、首都のトヨハラを目指しました。
一方、ロマンス国では、ツルハゲ王が重臣たちを集めて対策に大わらわでした。リューバ姫とスパシーバ王子がカラフト国に入ったのは間違いなく、ロマンス国としてどうするか対策を協議したのです。そうは言っても、妙案があるわけではありません。せっかく両国の関係が正常化したというのに、とんでもない事件が起きたものです。
とにかくリューバ姫を取り戻さねばなりませんが、カラフト国がそれを拒否したらどうするのか。はあ そうですかと、引き下がるわけにはいきません。それなら、リューバ姫を取り戻すために一戦をまじえるのか・・・しかし、今のロマンス国の軍事力では、とてもカラフト国に勝てる見込みはありません。カラフト国の方がむしろ強いぐらいです。だから、先の和平交渉はロマンス国の方から申し入れ、国境線の画定も譲歩せざるを得なかったのです。
王や重臣たちがいくら協議しても、妙案は浮かんできません。その時、ずっと沈黙を守っていた宰相のラスプーチンが初めて口を開きました。
「陛下、それに重臣の皆さん、こうなったら最後の“切り札”を使うしかありません。 思い当たる人もいるでしょうが、シベリア帝国に援軍を要請することです!」
ラスプーチンの発言に、一座はし~んと静まり返りました。ついに“奥の手”が出てきたのかという感じです。
シベリア帝国というのは、狭いタタール海峡をはさんで、ロマンス国の西に広がる巨大な国家でした。ユーラシア大陸の東部にありますが、ロマンス国とは昔から友好な関係を結んでいたのです。でも、実態はシベリア帝国が「宗主国」のようなもので、ロマンス国は毎年、貢ぎ物を献上していました。ロマンス国はいわば、シベリア帝国の属国だったのです。
だから、いざという時は、ロマンス国はシベリア帝国の助けを借りていました。災害や飢饉で困った時はよく援助を受けていたのです。しかし、今回は“軍事援助”の要請です。事は重大です。いかにラスプーチン宰相の提案とはいえ、そう簡単に結論が出るような問題ではありません。
ツルハゲ王は暫く考えていましたが、やがてこう言いました。「ラスプーチンの提案は重い意味を持っている。いま急いで結論を出すわけにはいかない。もう少し考えてみよう」 王はこう言うと、重臣たちとの会議をひとまず閉じることにしました。
しかし、翌日、ツルハゲ王はラスプーチンを呼びつけました。二人で徹底的に議論して、結論を出そうと考えたのです。王は言いました。「シベリア帝国の軍事援助も分かるが、そうなると、わが国はますます属国化する恐れがあるぞ。それで良いのか」
ラスプーチンが答えました。「陛下のご心配はよく分かりますが、残念ながら、わが国の力だけではリューバ姫を取り戻すことはとても無理です。日がたてばたつほど、ますます困難になります。ここはシベリア帝国の力を借りるしか他に手はないでしょう。どうか、その方向で決断を下していただきたいと思います」
ツルハゲ王はまだ考え込んでいました。しかし、ラスプーチンの次の一言が王の心を大きく揺り動かしたのです。
「たとえシベリア帝国の力を借りようとも、リューバ姫を取り戻し、さらにサハリンの南北王朝を統一して、陛下はその国王になられたら良いのです。悲願であった統一王朝が実現します」
これにはツルハゲ王も胸に応えました。自分がサハリンを統一してその国王になる、これほど素晴らしいことはないでしょう。ツルハゲ王は決断を下しました。「うむ、分かった。それでは、シベリア帝国の軍事援助の交渉はそなたに任せよう」 こうして、シベリア・ロマンス両国の軍事協力の道が開かれたのです。
話をスパシーバ王子とリューバ姫の方に戻しましょう。カラフト国に入った一行4人は、もう追っ手の心配もなく、2週間ほどで順調に首都・トヨハラに着きました。長い逃避行でさすがに疲れましたが、4人はゆっくりと休んで体調を回復したのです。
そして数日後、スパシーバ王子はリューバ姫を伴って国王夫妻に謁見しました。夫妻は王子の無事な帰還を喜びましたが、内心は複雑な思いでした。他国の女性との結婚は公式には認められていないし、王宮内には王子の行為を批判的に見る人がかなりいたのです。封建的な時代ですから、それは当然でしょう。ただ、スパシーバの妹・ナターシャ姫だけが、兄の無事な帰還を心から祝福しました。
そういうわけで、王子の帰還祝賀会などはいっさい行なわれませんでした。特に処分はなかったものの、スパシーバとリューバ姫は一種の“謹慎”状態に置かれたのです。
ただ、王宮内の人たちはリューバ姫を見た時、その美しさに驚嘆したそうです。彼女は中肉中背ですが、色白でぱっちりとした瞳、バラ色の唇、いかにも上品な鼻筋、しなやかな体つきなど、どこを見ても美しさに輝いていました。誰もが、こんなに美しい人は見たことがないと思ったそうです。 スパシーバ王子を慕っていたオニャンコ姫やモームス嬢、ブヨブヨ嬢らも、これには溜息をついて諦めざるを得ません。残念でしたね(笑)。
スパシーバ王子がリューバ姫を“略奪”したことで、ヒゲモジャ王はロマンス国の出方を警戒していました。このため、国境の警備隊を増やしましたが、ロマンス国がただちに攻めてくる気配はないようです。王は少し安心しましたが、いずれ今回の大事件の後始末をつけなければと、覚悟を固めるのでした。 そして何故か、王の脳裏にふと、カラフト国の南にある大きな島国・ヤマト帝国のことが浮かんできました。しかし、ヤマト帝国の話はまた後でしましょう。