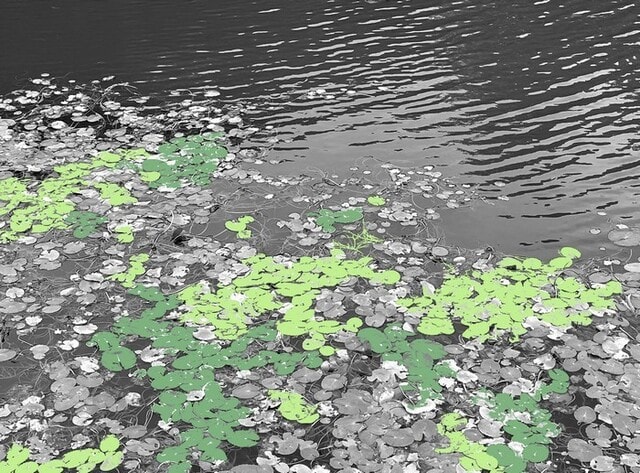期せずして孫のiPhoneが 僕のところに回ってきた これまでずっと僕のスマホは 中華製の格安スマホだったが 孫が手にするアップルのスマホの スマートでしゃれたデザインを いいないいなと眺めていたのを 12型から最新の14型に 買い替えたのを機に 12型が僕のところに というか 僕にiPhoneを使わせたいと あえて14型に買い替えた ようでもあるが もちろん僕にとっては 羨望のiPhoneだから 断る理由は何もない それも最上位クラスのPro Max これで存分に写真が撮れると 僕にとってスマホは 通信よりもカメラなので それと懐かしい林檎のマーク ふたたび林檎を齧れる歓び 久しぶりの林檎との再会 その林檎とともに 苦闘した日々が甦ってきた その頃は文字の暮らし というか活字なるものが ぼくの生活の中心だった アルバイトで入った出版社で 写真植字というものに出会い さまざまな文字の形を知り 自在に文字を作るレタリングや 文字の美しさを視覚的に捉えていく タイポグラフィなどという 文字を扱う楽しさに熱中していた ところにちょうど アップルという林檎で スティーブ・ジョブズが開発したのが マッキントッシュという名のパソコン それによって 文字もデジタル化され 豊富な書体やバランスのとれた文字など パソコンで扱えるフォントが 彼によってさまざま創り出された 「マッキントッシュは世界で初めて美しい活字を扱えるパソコンになった」 とジョブズは言った 僕がはじめて手に入れたパソコン マッキントッシュは 日本語がとても貧弱だった 文字(フォント)の形も美しくはなく 種類も明朝体とゴシック体だけ まだ仕事として使えるものではなかった それでもマウスを操作すれば 自分で文字を作ることはできた モニターの何もないところに 文字が浮かび上がってくる それは新しい体験であり 未知の世界を発見する わくわくする楽しさがあった マッキントッシュという器械にも ふんだんに遊び心があり その感覚を享受できる喜びがあった 一方いきなり 爆弾マークが飛び出して 画面がフリーズしてしまうと 作業も心臓も止まるほどだったが 進化を続けるマッキントッシュに モリサワフォントが導入され 日本語フォントも豊かになっていく 写真植字のガラス板文字で モリサワの活字とは親しんでいたので パソコン上でも 馴染みの活字に再会できて嬉しく 仕事はどんどん拡大した そして時はすすみ ジョブズが最後に作り出したのは マウスではなく指先で操作できる iPadという掌にのる 小さなコンピューターだった パソコンが人に近づき 誰でも気軽に扱える器械になって 皮肉にもぼくのパソコンは 仕事としての機能を失っていく "Stay hungry. Stay foolish." (ハングリーであれ バカであれ)は ジョブズが若者たちに贈った言葉だった ぼくはもう若くはないけれど 今でもハングリーであり バカであると思っている バカは孫からもらったiPhoneの 小さなコンピューターの 林檎にふたたび齧りついている かつて飢えた魂で赤い林檎を齧った そのときの新鮮な感覚と感動を いままた取り戻そうとしている