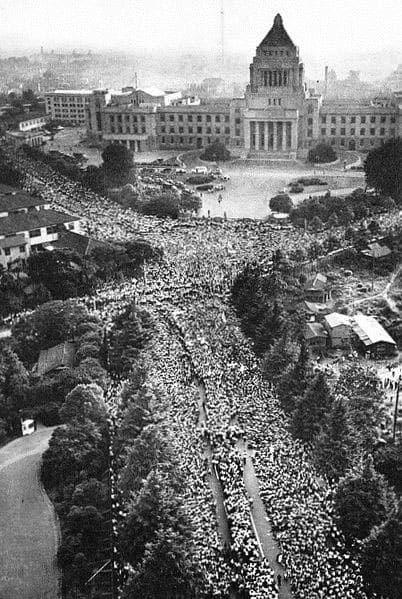ローマ最大のフラミニオ墓地の入り口の花屋 こんなのが20軒あまり軒を連ねている
~~~~~~~~~~~~~~~
ローマの火葬と散骨
不発に終わったイタリア語の説教-2
~~~~~~~~~~~~~~~
思い出していただきたい。私が説教をするはずだった日の朗読はルカの福音書からだった。
イエスは、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちにたとえを話された。
「ある町に、神を畏れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところが、その町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、『相手を裁いて、わたしを守ってください』と言っていた。裁判官は、しばらくの間は取り合おうとしなかった。しかし、その後に考えた。『自分は神など畏れないし、人を人とも思わない。しかし、あのやもめは、うるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやって来て、わたしをさんざんな目に遭わすにちがいない。』」それから、主は言われた。「この不正な裁判官の言いぐさを聞きなさい。まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでもほうっておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうか。」(ルカ18章1-8節)
別にクリスチャンでなくても、天地万物を創った生ける神の存在を受け入れる立場に仮にも身を置けば、上のたとえ話はそんなに難解なものではないだろう。神がいるなら、絶えず祈り求めるものの願いを聞き入れないことがあるはずがない。問題は、疲れを知らず神に祈り求めたのに、願いどおりに聞き入れられなかったと思われるケースが実際には決して少なくない、という現実をどう受け止めるかだろう。
前回のブログで紹介したイタリア人の同僚神父の説教は、その点を何とか人間の知恵で折り合い良く説明しようとしたものだった。
生まれて間もない初子の赤ん坊が、高熱を発して苦しんだ挙句、五日目に死んだ。必死で祈り続けた若い母親の祈りは空しかった。神はどうして速やかに聞き入れて下さらなかったのか。その母親の悲嘆は誰が慰めてくれるのか。
神は人間の祈りを速やかに聞き入れてくれるものである反面、無私な愛が動機であれ、欲得のためであれ、人間が祈りで神を都合よく操ろうと言う試みは決してうまくいかないという、ただそれだけのことだろう。(ご利益主義の宗教の世界の話ならともかく・・・。)これは神の自由に属する神秘であって、人間の合理的な説明を受け付けない。
そもそも、私の不発に終わった説教は、上のテーマに何かより賢い解説を試みるものではなかった。私の関心は全く別なところにあった。
あの「悪い裁判官としつこいやもめ」のたとえ話の結びの言葉に続いて付け加えられた、
「しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうか。」
と言う、やや脈絡不明の謎めいたキリストの問いかけに私の好奇心がピクリと反応したことをめぐって展開するはずだった。
約2000年前のパレスチナの地に生きた歴史上の人物、ナザレのイエス=キリスト=は自分の事を好んで「人の子」と自称していた。そして、「人の子が来るとき」とは、自分の再臨の時、つまり終末の時、今の宇宙の歴史が終る日、のことを指している。宇宙の始まりとされるビッグバンから今日までに137億年が経過したとは、神を信じない科学者の定説だが、始まりのあったものには、必ず終わりもあるだろう。「人の子の再臨」(世界の終末)まで、今から1000年なのか、100万年なのか、数十億年先なのか、誰も知らない。
そのとき
「はたして地上に信仰を見出すだろうか」
と言うイエスの問いは、その終末のときキリストの教えはまだ命脈を保っているだろうかとか、そもそも、宗教と言うものがまだ存在しているだろうか、と言う問いとも受け取れる。また、たとえキリスト教が生き延びていたとしても、本物の信仰を持った人が残っているだろうか、と言う意味にも取れる。
もしそうだとすれば、このイエスの唐突な問いは、今の時代に生き、あと十数年もすれば死んでいなくなるはずの私と、私の同世代人には、取り敢えず何のかかわりもない話と言うことにはならないだろうか。
だが、果たしてそうだろうか。私はどうも腑に落ちない。イエスが、話している相手に直接関係のないことを言う、とはどうしても思えないのだ。だから、
「しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうか。」
と疑問を投げかけるとき、イエスは私に、
「お前はどう思う?お前の場合はどうなんだ?」
と聞いておられるように思えてしようがない。さらに、
「イエス様ご無体な!そんな何万年先かも分からない世の終わりの事をわたしに聞かれたって知りませんよ。
私には関係ないでしょう?」
というトボケた返事をイエスが期待しておられるはずがないと私は思う。
実に謎めいた話だが、まあ、この話はひとまずここで一休みしよう。
~~~~~~~~~~
先日、私はイタリアではまだ珍しい火葬された遺灰の散骨の現場に立ち会った。人口270万人の都市ローマに、一か所だけ人間の火葬場がある。さらに2005年には、その火葬場に隣接して散骨葬をする場所が設けられた。東京には1300万の人口に28か所の火葬場があるが、そのような散骨施設を備えた墓地の話などまだ日本では聞いたことがない。

まるで何かの工場のような火葬場の佇まい

脇に回れば 霊柩車が次々と遺体の入ったお棺を運んでくる

裏には何十というお棺が何日も常温のなか火葬の順番を待っている

新しいお棺が焼却炉に入って火がつくと 下腹に応えるゴーッという炎の音が周りに響きわたり
煙突からは始めのうち黒煙がもうもうと立ち上がる
順番待ちの後 火葬が終ると 引き取り日を指定した通知が届く
人々は、火葬場で遺灰の詰まった茶色のアルミの壺を受け取り、その足で散骨の場所に向う
そこに遺灰を撒いて死者の弔いの締めくくりとするためだ
(もちろん日本のように遺灰を墓地に葬る人も少なくない)
私はその散灰に立ち会ったが、正直のところひどいショックを受けた。

火葬場から50メートルほど離れたところに「追憶の庭」と書かれた石があった
2005年に開設されたばかりだった

その中には白い壁に一部を囲まれた芝生の空間が広がっていて
その芝生の中にカーブする一本の道があった
白壁の右肩あたりには、目の高さに小さな真鍮の銘盤がぎっしりと貼られはじめていた
ここで散骨された人々の唯一の手がかりだ

その一本道はやがて真っ直ぐな緩やかな上り坂の木道に繋がる
ここから見ると その坂道の行く手は空で
まるで光に包まれた天国につながっているかのようだった

しかし その道を先端まで進むと そこには朝露の粒ををレースのように繋いだ蜘蛛の巣があった

天国への道はそこで終わり 蜘蛛の巣の真下には巨大なコンクリートのお皿があった
遺族は火葬場の事務所の窓口で遺骨の壺を受け取ると、まっすぐ木道を進み、その灰を下に撒いてさっさと帰っていった。目の前に私が-つまり、カトリックの神父が-いるのに、彼らはお祈りの一つも頼むことを思わなかったのだ。宗教は、したがって、信仰はそこには見いだされなかった。(まるで2000年まえのキリストの問いに早速答えが出ているかのようだった。)
灰は日本の火葬場の遺骨のように真っ白でまだ何とか骨の形を保ったものを拾い集めたものではなく、まるで臼で挽いたかのように細かな灰色の粒子になっていた。散骨の台からから撒くと、乾いた砂のようにサーッと下へ落ちていくが、細かい粉末状の部分は下まで落ちる前に風にあおられて空中に舞い上がる。それが居合わせる人々を包み、目に入ったり、鼻の穴や口の中をざらりとさせる。一方、下まで落ちた灰は大皿の中心に小さく盛り上がるが、皿の周りのノズルから噴き出した水が、中心部を残して全て洗い流し、リング状の隙間から地中に浸み込ませ、大部分はあっという間に見えなくなる仕掛けになっている。形は大きなお皿だが、原理は洗面台やビデやトイレと同じことだ。灰を流した水の行先まで考えたくない。まさか生活排水の下水管に直結していないことを祈る。

これで何人分の灰だろうか? このリング状の溝の外に落ちた灰は
皿の縁に配置された数個のノズルから噴き出す水できれいに流されていった
遺灰は風に流され、地下水に溶けてどこかへ消えていった。墓碑もない。もはや死者は愛する人々の追憶のなか以外にどこにもいないのか。


庭を戻る道が沿うあたりの壁には幅10センチほどの真鍮のミニ銘盤が隙間なく貼られていたが
中には同じ大きさの陶板に写真を焼き付けたものもあった
左のマリアは今年の7月7日に死んだ 遠いテルニの町から運ばれてきた あの町にはまだ火葬場がないのだろう
右側の筋肉男(65歳)はこの10月4日に死んだ。まだ一月にもならない。
この人たちにも 彼らをここに葬った人たちにも もはや信仰は見出されない
「イエス様 これが現実です!」

人々が挨拶もそこそこに解散する中、私もその場を去ろうとしたが、立ち話をしている火葬場の職員の作業着の背中を見て、またもギョッとした。背中のマークは紛れもなく見慣れたローマの清掃局のものだったからだ。町中の汚いゴミ箱にも、それを収集に来る清掃車にも、その作業員のツナギの服の背中にも同じマークがついている。五本指のようなあの印だ。ama Roma S.p.A.をヤフーイタリアで検索すると、「ごみの収集、運搬、処理、再生、廃棄を業とする株式会社」と定義されていた。イタリア人にとって、人間はただのゴミだったのか?もし神を畏れ人間の不滅の魂の尊厳を認めるなら、こんな露骨な扱いをするだろうか。資本は同じでも、せめて「フラミニオ斎場」とか名乗って、清掃局のロゴも隠して、別組織を装うだけのデリカシーは無いものか。
「もう地上に信仰は見出されない」 のか?
なぜ「不発弾の説教」の話が「ローマの散骨」の話にすり替わったのか?
それは、私がするはずだったあの「説教」の核心部分と深い関係があったからだ。
だが、そのあたりの事情は次回のブログに譲ることとしよう。
~~~~~~~

ローマの火葬場の周りの普通の墓
他にも高層マンション型の個室の墓 お金持ちの家族向け家型の豪華一戸建ちの墓もある

これは貧しい人の墓?

ところ変わって 神戸のカトリック教会墓地にある母の墓
銀行マン時代にドイツから持ち帰ったグラナイトの墓石に
母の作曲手帳から私の好きな曲の手書きの譜面を写して刻んだ音楽墓碑
その前には父と妹と二人目の母の墓碑
庵治石は高松の信者の石屋さんがタダで譲ってくれた
(つづく)