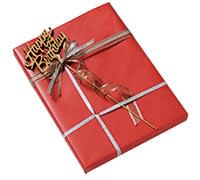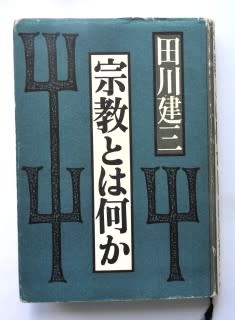~~~~~~~~~~~~~~~~
私の「インドの旅」総集編
(8)悲しき雀
~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)導入
(2)インカルチュレーションのイデオロギー
(3)自然宗教発生のメカニズム
(4)超自然宗教の誕生―「私は在る」と名乗る神
(5)「超自然宗教」の「自然宗教」化
(6)神々の凋落
a)自然宗教の凋落
b) キリスト教の凋落
c) マンモンの神の台頭 天上と地上の三位一体
(7)遠藤批判
(8)悲しき雀
(9)田川批判
(10)超自然宗教の復権

「悲しき雀」の著者 H・ホイヴェルス師
(8)悲しき雀
私は、流れから言って、(7)「田川建三による遠藤周作批判」の次(8)のテーマは、「田川健三批判」であろうと思い込んでいたが、そうではないことに気が付いた。何故なら、田川建三を批判するツールとして、どうしても(9)の元の題「絵に描いた餅」の話が必要だったからだ。しかし、「絵にかいた餅は食えない」という命題は、一方では、自明の理であって全く説明を要しない点はいいのだが、他方では、あまりにも陳腐で通俗的すぎて面白くもなんともない。
何かもっと品のいい話はないものか、と思案するうちにふと心に浮かんだのが、私が敬愛してやまないホイヴェルス神父様の次の短編随筆だった。
心の洗濯のために謹んでご一緒に味わっていただきたい。

拾われた時は何の鳥かわらなかった
ホイヴェルス師の初期の随筆集「時間の流れに」(ユニヴァーサル文庫‐21‐) の中に「悲しき雀」という短編がある。
それは、次の言葉で始まる。
「友だちの家の縁側には、鳥籠の中に一羽の小鳥がさえずっていました。鳥籠は朝かぜの中にゆりうごき、鳥の声は悲しそうでした。私が見にゆきますと、鳥は黙り込んでしまいました。・・・」
そして、少し先で「しばらくして、雀の鳥籠での生活は、とても退屈に違いない、と同情しました。この雀のために遊び仲間を工面してやりたいな、と思ったものの、もちろんできっこありません。でもある哲学者によれば、現象の世界と実在の世界との差別はありませんから、この雀はなおさら現象と実在を分けることなどできまい、と思いつきました。
私は鳥籠を縁側から私の部屋のテーブルの上に運び、そこでうまく一つの鏡を鳥籠の側に立てました。それで鏡の中にも鳥籠と一羽の雀が現れました。それからわたしは静かに部屋の隅に退きました。すると雀は、たまたまぐるりと向き直って鏡の中の雀を見つけます。自分の種類とすっかり同じ鳥です。私は、雀がすぐこの新しくつくられた雀のところに遊びに来るだろうと思いました。けれども、わが雀は哲学者ではなく詩人で、物を所有することよりも、物に対する希望を大切にしますから、その胸をふくらませ、嘴を天にあげて翼をバタバタと打ち、そして喜びにあふれて一心に歌い出しました。長く長く歌いました。

鏡の中の雀も歌います。翼をバタバタと打つ、それで熱心はいよいよ増してくるのです。ようやく歌い終わってからお互いの挨拶のために、ぼつぼつ近づき、嘴でつつきあうのでした。それからまたさえずる。戻っては飛びまた近づきあいます。近くになってもいつもいつもただ嘴だけなのです。そのためにこの二羽の鳥は驚きあいました。疑い深くなったのです。またはなれて、少し遠くから、じっと互いに睨みあい、またもういっぺん歌いましたが、もはやそんなに希望にみちた歌ではありませんでした。もう一度挨拶をしてみようととんでゆきました。しかしこの固いガラスは同情を知らないので、この二羽の友達は一緒になれませんでした。哀れな雀は現象の世界の悪戯に失望し、早くも詩人は疑い深い哲学者になってしまいました。そしてこの贋物の鳥から、なるべく遠くとびはなれて背中をむけ、時々ピーピーと嘆くのでしたが、でもたまにはそっとふりかえって、鏡の中の鳥をぬすみみていました。
わたしも雀に同情しました。また現象と実在の相違をそんなに早く見て取ったことにいくらか感心しました。ある哲学者たちはこう早くは現象と実在の差別を悟らないものですから。」
ここまでで、師の短編のちょうど半分。残り2ページの展開を惜しみながら、話を先へ進めたいと思う。

ホイヴェルス師は、世の並みの哲学者たちがなかなか悟ろうとしない「実在と現象の明白な違い」を小鳥が賢くもいち早く認識するに至った事実を、この随筆にーいささかの皮肉を込めてー綴られたものと思う。
問題の理解をさらに深めるために、師の詩的な格調を穢すことを敢えて恐れず、ここに私が好んで使う短い挿話を加えたい。それは、私が杉並区の夜の街角で見た光景についてである。
「師走の寒い夜、裸電球に照らされた町内会の掲示板に、一枚の『火の用心』のポスターが貼ってあった。そこへ、足元のおぼつかない忘年会帰りのおじさんがゆらゆらと通りがかり、立ち止まってポケットをまさぐって煙草を取り出して口にくわえ、ポスターに描かれた火に近づけて、煙草に火を貰おうとしている。うん?と怪訝そうに首をかしげながら、なおもしきりに煙草を火にくっつけるが、もちろん火は着かない。何度か同じ仕草くりかえしたのち、やがて火のついていない煙草をくわえたまま、首をすくめ、ゆらゆらと闇の中に消えていった。」如何か。
ポスターに描かれた、或いは、印刷されたカラー写真の「火」は、絵に描いた餅に相当するのに対して、食えば腹が膨れる「食える餅」に相当するものは、「光と熱を放って燃えている生きた焚火の火やマッチの炎」のことであろう。酔っぱらいは、咥え煙草にポスターの火から火をもらおうとして、なぜ火が着かないか理解できなかったのだ。
実在と虚像、または実存と現象の違いを一早く見抜いた小鳥は、並みの哲学者よりも、またこの酔っぱらいよりも、よほど洞察力に優れていたのだろうか。
「絵にかいた餅」も、「ポスターの火」も、「鏡の中の小鳥」も、みんな「食える餅」、「燃える火」、「生きた小鳥」に対応している。一つは「実在」で、もう一つはその単なる「写し」に過ぎないということだ。ドイツ語では「“Sein“=存在」と「”Schein”=虚像」という。
ここで大事なのは、食べられる餅も絵に描いた食べられない餅も、燃える火もポスターの火も、生きている小鳥も鏡に映った小鳥も、全て自然の中の存在であり、自然の中の現象だということだ。加えて、その事を区別し、その区別を認識するわれわれ人間自身も、全て自然界の存在である点では共通している。
では、宗教の世界はどうだろうか。これこそ、今回のブログの決定的に重要なポイントだから、よく注意して、緊張して、読んでいただきたい。
先ず「自然宗教」の世界を見ると、神々とは、そもそも自然現象の圧倒的な力の背後に人間の畏怖する心が投影したもので、大自然の実在性よりもさらに希薄でより抽象的な存在であって、自然界を超えるものではない。その神々の像を刻み寺社・神殿に安置してみても、神々はその像を刻んだ人間と共に自然の一部を構成するに過ぎない。言葉を変えて言えば、食べられる餅の対応する諸宗教の神々も、絵に描いた餅に対応する神々の絵も像も書物も知識も、全て自然の世界の中に包含され、自然の中で自己完結している。それが「自然宗教」と言われる所以でもあろう。
では「超自然宗教」の場合はどうだろうか。神を礼拝する聖堂、会堂、教会も人間の手になったもの、神について書かれた経典・聖典も、そこで執り行われる祭儀もそれに与かる信者たちも自然の一部を為す人間とその営みであり、神に関する観念も教えも宗教の歴史も全て自然の枠を超えるものではない。それらは皆、いわば現象の世界、生ける神に関する現象に過ぎない。しかし、自然の中のどこを探しても、「わたしはある」と名乗る「生ける神」はそのなかに包含される自然の部分としては存在していないのだ。言葉を変えて言えば、超自然宗教の神は、自然現象の中にふくまれない、自然界の存在の部分としては存在していないからこそ、超自然の神と呼ばれ得るのだ。
「超自然宗教の神」が森羅万象を無から創造した生ける神であって、自然の一部ではないのであれば、自然の中に生きる我々が創造主、生ける神について知っている全ては、絵に描いた餅、ポスターに描かれた火、自然という鏡に映った虚像であって、食える餅、煙草に火のつく光と熱を放って燃えている火、動き囀る生きた小鳥に対応する「生ける神」そのものではない。この神は、自然を超越し、自然の埒外に、即ち、「超自然の領域」に存在している。
要約すれば、「自然宗教」の世界では食える餅としての神も、絵に描いた食えない餅としての神も、共に自然界の中に見出されるが、「超自然宗教」の世界では、自然界で捉えられる神はすべからく絵に描いた食えない餅としての神であって、食える餅としての「生ける神」「自然界を無から創造した神」は自然の埒外の「超自然の世界」にあるということである。
ホイヴェルス師の随筆の中の小鳥は「ザイン”Sein”=現実」と「シャイン”Schein”=現象」の違いをあっさりと区別することが出来た。しかし、師走の街角のおじさんは、酔っていたから、ポスターの火は虚像の火であって、タバコに火をつけることのできない火であることの簡単な理を理解できなかった。ホイヴェルス師の上品な皮肉よれば、世の大学の哲学の先生方の中には、ザインとシャインの初歩的な区別が分からない、酔っぱらい哲学者が名声を覇することが出来るほど、世のなかは迷妄の淵に沈んでしまっているのだ。
あなたは大丈夫ですか?酔っ払っていませんか?あなたは食える餅も、絵に描いた餅も、両方とも自然の中に見つけられるし、自然宗教の神々も、その現象も、両方とも自然界の中に見つけられるが、超自然の神だけは自然界には見出されず、超自然の領域にのみ実在し、自然の中に見出される神に関する事象はすべて超自然の神を廻る現象、観念、虚像にすぎないことを十分に納得し、はっきりとご理解いただけただろうか。
このブログの筆者が言い立てることは、何かひっかかる。俄かには承服できない。と、この期に及んでなおもブツブツつぶやく吾人の脳みそは、ホイヴェルス師の短編の中の雀の脳みそよりも小さいと言われても文句は言えない。スズメの脳みそは小さいですよ。5mm3にも遥かに届かないのではないか?

真に「Sein = 存在」 の名に値するものは「私はある、あるという者である」と名乗る超自然の神以外にはない。その神「私はある」についての思弁も考察も含めて、他の自然宗教の神々も、全ては自然の中の現象「Schein=虚像」と呼ばれるにふさわしい。「わたしはある」の神は一切の自然界、現象の世界を凌駕した「超自然」の中に生きていて、自然の一部には還元され得ないのだ。
このことは、次の「(10)田川批判」にとって決定的な鍵になるので、是非しっかり頭に刻んでおいていただきたい。