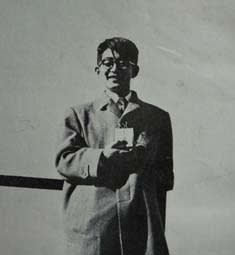~~~~~~~~~~~
野尻湖の夏 2014
今年も神学生たちと共に・・・
~~~~~~~~~~~
今年も野尻湖の山荘に神学生たちがやってきた。

東京と奈良の小さな家に住みながら日本語学校に通っている予備神学生の一部と、ローマで哲学や神学を勉強している上級生で夏休みを日本で過ごす者たちの一部だ。今年は例年より多く一度に8人もやってきて、わが家の寝部屋は満杯だ。



副院長アンヘル神父のお得意のパエリア。一人分これぐらいでもみなぺろりと食べる。
四国の三本松にあった高松教区立の「レデンプトーリスマーテル神学院」が、ベネディクト16世教皇の粋な計らいでローマに移されて以来、私もローマの「日本のためのレデンプトーリスマーテル神学院」に居を移したが、長い日本の夏季休暇をくつろいで過ごせる場所は、この野尻湖国際村以外にないのだ。
木々の間から湖面が見え隠れする斜面に建つこの家は、緑と静寂につつまれた楽園だ。神学生たちもここで勉強を離れて英気を養う。
野尻湖の国際村は、NLA(ノジリ・レイク・アソシエーション)と呼ばれ、90年以上前に、当時日本全国に散って盛んに活動をしていたプロテスタントの宣教師たちが、年に一度、夏のひと時を共に過ごすための別荘地として拓いた村だ。将来軽井沢は必ず俗化すると見越して、この辺鄙な北信の地に場所を求めた宣教師たちの先見の明に脱帽する。
小さいながら選挙で選ばれた大統領と議会を備え、半ば独立国の体裁を整えたこの共同体は、もともとは、ほぼ100%が青い目と金髪の欧米人プロテスタント牧師家族の集団で、戦時中は逆に外国人を収容して監視するゲットーとしても使われた。戦後は少しずつ日本人のメンバーが増えたとはいえ、今でも公式共通言語は英語で、中に入るとまるで外国に来たような錯覚に襲われる。この共同体を支えているのは、今もキリスト教とボランティア精神だ。

毎週火曜日の午前は燃えないゴミの収集日。雨の中でゴミの分別に励むボランティアーの神学生たち。
メンバーとゲストは、タダでゴルフやテニスをし、湖上ではセーリングに興じることができる自由で開放的な空気がいい。
私の大叔父は、アメリカ帰りのちょっとした成功者だったのだが、帰国の船の中で知り合った宣教師との縁でNLAの湖畔に面した21Bの家を手に入れた。私は大学に進んだころから、毎夏そこに遊びに来ていたのだった。
21Bから少し斜面を上った3軒目の113のキャビンに山尾さんという日本人の一家が住んでいた。第2次世界大戦中は、ご主人が三井物産はベルリン駐在の単身赴任だったので、ゆり子夫人と一粒種の俊ちゃんが世田谷から野尻湖に疎開していたのが縁のようだった。
東大理科から慶応医学部に転進した俊ちゃんは、たまたま私と同じ昭和14年生まれで、学生仲間から愛された秀才だったが、多感な彼は希望に満ちた未来を自殺で断ってしまった。
最愛の息子を失い悲嘆に暮れた母親のゆり子夫人は、心の支えを信仰に求めた。それも、プロテスタント一色のNLAに居ながら、何故かカトリックで洗礼を受けたのだった。
わたしが彼女の視野の中をうろうろしていたのは、イエズス会の志願者時代であったが、国際金融マンになってからは仕事に夢中で野尻には全く足が向かず、その結果、彼女の視界から私は忽然と消えていたのだった。
それが、四半世紀後のある夏、「ぼくはカトリックの神父になりました」と言ってひょっこり野尻に現れたのだから、彼女はびっくりするやら、喜ぶやらで、113のベランダでのお紅茶のひと時はあっという間に過ぎていった。

ベランダには私が土産に持ち帰ったカプリ島の陶器のハウスナンバーが。
神学の教授ライセンスを取りにローマに戻ったある日、彼女から一通の手紙が追っかけてきて曰く、「年老いて、世田谷の屋敷も何もかも整理して、東京ではケアー付きのマンションに住んでいるが、春から秋までは懐かしい野尻で過ごしている。息子の思い出が詰まった野尻の家だけはどうしても手放せなかったからだ。それが、今回あなたに会って、ようやく決心がついた。あの家をあなたにあげる。だから、私が生きている間は夏休みをそこで一緒に過ごしてくれないか?」という文面だった。若々しい俊ちゃんのイメージが、中年男の私と重なったのだろうか。

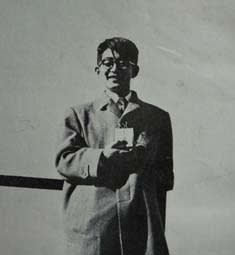
追悼記念の文集に集められた写真の一枚。みんなから愛された医学生の俊ちゃん。

俊ちゃんと同じ齢の私がまだ若かったころの写真
出家する前に、リーマン時代からの身辺の垢 -家も何もかも- をさっぱりと整理して無一物になったつもりの私だったから、今さら家などもらっていいものだろうかと戸惑い、当時の上司の深堀司教様にお伺いを立てた。すると、「将来きっとあなたの役に立つから、ありがたく頂いておきなさい。」というお返事だった。
ローマから夏休みに帰国して彼女と野尻で一緒に住んだのが二夏だったろうか。その次の夏には彼女はすでに車いす生活だった。そして、どんなに誘っても、「人様に迷惑をかけてまで、私は参りません!」と頑なに断った。
娘時代にイギリスに留学し、馬に乗り、双葉の飛行機の操縦席にも座った明治の才女のプライドが、急な野尻の坂道を私に車椅子を押されて行くことを許さなかったのだろう。
私が最後に見舞ったとき、老人ホームのベッド脇の小灯台の上にメモ用紙と5センチほどにちびた鉛筆が一本ポツンとあった。咄嗟に私は鞄の中から人のメールをプリントしたA4の紙を取り出して、その裏に、その短い鉛筆でスケッチを始めた、5分と経たないうちに、せっかちの彼女は早く見せろとせがむのをわざとじらして、これ以上待たせにたら怒り出すぞという頃合いに、クルリと紙をひっくり返して見せたら、彼女は思わずニヤリと笑った。毎朝化粧鏡の中に見慣れた自分の顔とよく似ていたからだろうか。

Yuriko Yamao John K. Taniguchi 2000.5.30.
たまたま持ち合わせた紙は人のメールをプリントしたもので、左下のあたりには表のテキストがうっすらと透けて見える。
そして私はローマに帰った。その後まもなく、彼女も天国に帰って行った。そして、下手なスケッチが彼女の最後の形見として、今も113のキャビンの暖炉の上を飾っている。
彼女の私への口頭の遺言は、「幸紀ちゃん、113の家は神様のために役立ててくださいね!」だった。
今こうして神学生たちがやってきて、毎日ベランダで朝夕の祈りを唱え、夕べには居間に掲げたあのスケッチの前でミサを奉げる姿を見守って、ゆり子さんもさぞ満足していることだろう。

神学生の里親さんたちを迎えてミサを奉げるアンヘル副院長


ミサの後の夕食のひと時 里親さんたちの差し入れのお料理で

夕食後はベランダで神学生たちの歌を里親さんたちと聴くのも慣例になっている


別の夜、神学生の里親で92のキャビンのオーナーの S.T.夫人とそのお友達に夕食に招かれた。食事の後はここでも

K.M.嬢はS.T.夫人と私の共通の知人。私の母の形見のギターに合わせて、イタリア語やスペイン語の歌で夜が更ける。
湖面にはキャビンと一緒に譲り受けた俊ちゃんの愛用のヨットが浮かんでいる。神学生にせがまれると一緒にセーリングに出る。ゆり子さんが80歳でも一人で乗って、野尻湖村までお買い物に行ったという伝説のヨットだ。

私はヨットのセーリングを中学3年の時に琵琶湖でおぼえた。まさか、棚ボタでもらった別荘にヨットまでついてくるとは思わなかった。神学生の中には、いつの間にか風を読む勘を覚え始める者もいる。


ある日、東京や奈良から神父たちもやってきた。頭が重なって陰になっている者も数えて、これで総勢16人。明日の日本の福音宣教の情熱に燃えた連中だ。さすがの我が家もこれがキャパシティーの限界。
「ゆり子さん、あなたの遺産は神様のために役立っていますよ。」そして、「深堀司教様、あなたの予言は的中しましたね。」
もしこの家を貰っていなかったら、私は日本の夏をどこで過ごせばよかったのだろう、と思わずにはいられない。

宣教司祭の養成には8~10年ほどの時間がかかります。その養成費もバカになりません。その多くの部分が里親たちの寄付に依存しています。神学校が高松からローマに移されて以来、新しい里親の参加が伸び悩んでいます。そして、以前からの里親たちも高齢化して、支えてきた神学生が目出度く司祭になったのを機会に、里親をやめる人も増えてきました。新しい里親の参加が切に期待されています。
瞳の輝いた、日本での宣教活動の熱意に燃えた若者たちを、一人前の司祭になるまで祈りと献金で支えて下さる里親になることを決意される方は、是非私のブログのコメント欄にお申し出ください。もちろんいただいたコメントは非公開状態のまま残り、個人情報は私が責任をもって管理いたします。そして、その方には一人の神学生が霊的子供として与えられ、信仰に裏付けられた個人的な親子の交流が始まります。それは実に恵み豊かな体験です。ぜひよろしくお願いいたします。

(おわり)
追伸:
上の里親の呼びかけに対して、早速反応の第一号が届きました。コメント欄にはすぐお礼のコメントを書きましたが、コメント欄を見る人は意外に少ないので、ブログ本文の追伸として採録します。
Y.Y.さま
早速の里親のお申込みありがとうございました。
すぐに一人の神学生を本人の氏名、誕生日、国籍、人物紹介などを写真とともにあなたの里子紹介として送らせていただきます。
末永く見守り育ててやってください。
あなたのお祈りと経済的支援に神様が豊かに報いてくださいますように。