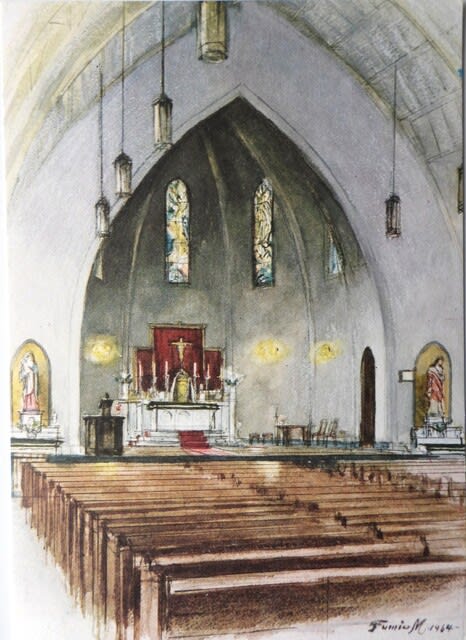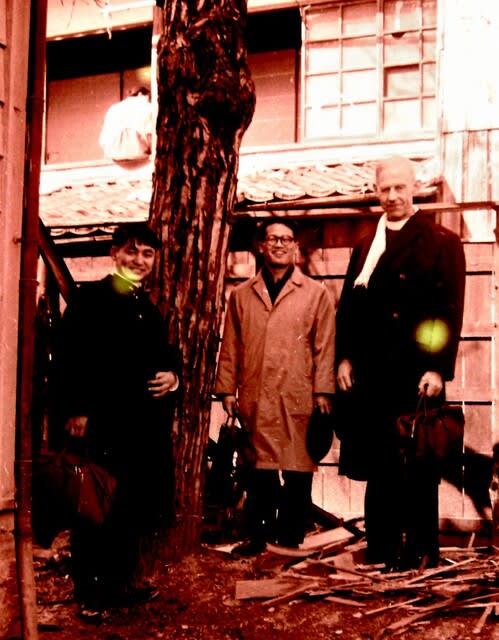~~~~~~~~~~~~~~~~
鶯と詩人
ホイヴェルス著 =時間の流れに=
~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~
鶯と詩人
~~~~~
私は五歳のとき、よく鶯の歌を歌いました。
Nachtigall, Nachtigall !
Wie sangst du so schön
Vor allen Vögelein !
「鶯よ うぐいすよ
なんと美しくうたったことよ
どの小鳥よりお上手に」
などと母からならって――けれども鶯の声を聞いたことがありませんでしたから、この不思議な鳥の声を始めて聞けるのはいつかしら、とあこがれていました。二、三年たってからいろいろな鳥の声を聞きました。中には、森の中に自分の名を呼んでいる郭公鳥の声もありました。鶯もそうしたらいいのに、と私は思いました。
ところがある五月の朝、森を通って行くと、突然中から、何かのラッパの音なのか笛の音なのか、大きな喜びの叫びや、また悲しいさえずりなどが響きましたので、私は息を押えました。確かに鶯です。すべての鳥よりも美しく歌うのです。
五月の朝のそうした出来事のあとで、私はいろいろな国を訪れました。新しい国にはいると、その国では五月になると鶯が歌うかしらと、すぐ気にかかりました。ずっとあとになって日本に来たときに、日本も鶯の国だと聞いて非常によろこびました。私が万葉集の和歌を研究したときには、春とともに必ず鶯の名もそこに出て来るので、鶯という言葉は、もう一番美しい感情にみたされた日本語となりました。日本の鶯の声が始めて耳に響き、深く心にはいるのはいつのことでしょうか。
私が来朝したのはちょうど八月のことでしたが、秋になり冬になりました。それから春――春のある朝八時頃、庭の中で短い笛の音がしました。 鶯かしら、と立ち聞きました。しかしやはり一つの短い歌でした。もっともっと聞きたい。庭の中へはいって、ひそかに歌声の方に近づいて行きました。やはり鶯です。鳥は枝にとまって速かにその歌を終わりました。それからあちこち飛んで虫を食べ景色を眺め、もういっぺん短く歌いました。鶯よ、そんなに短く歌うのにお前を Nachtigall といってよいのでしょうか。
ある若い詩人が、私に一人の有名な詩人の著した本を寄贈して下さいました。それは七百五十五首の和歌を納めたものでした。中には春と鶯についても、かなり詠んでありました。七百五十五の和歌、どういうわけでそんなに短いものにしたのでしょう。詩人もやはり鶯のように、その製作をあまりに早くまとめてしまい過ぎます。日本の鶯と詩人の気持はいつになったらわかるのでしょう。
しばらくたって若い詩人は七百五十五首の和歌を詠じた詩人のところに私をつれて行きました。一見その詩人は決して詩人のようには見えませんでした。都会の美術家や文芸作家などのように長い髪をしていません。またその目つきも普通です。ある若い美術家などは、サムソンの力が髪の毛にあると思っているかのように、非常に長い頭髪をたくわえ、その歩き方や目つきは、いつもダンテとともに地獄のどん底をめぐり、あるいはファウストとともに魔女の厨を訪ねるもののようです。この詩人には何もこうした怖しいところがありませんでした。
初め私たちは応接間の安楽椅子に腰をおろしましたが、なかなか話がうまく進みませんので、居間に案内され、そこに坐って、やがて楽しい会話となりました。詩人は心よく自分のほかの著作を見せましたが、それもおおかた三十一文字の和歌でみたされてありました。この詩人は自然のうちに潜みかくれ、静かにしていて、自然の息を感じると、柔かい手つきで捉え、三十一の珠玉の言葉の中に花束のように包み、読者に献げるのです。
詩人の夫人は茶菓をすすめて静かに詩人の後に坐りました。あとから詩人の合図でレコードを出し、作曲されたいろいろの和歌をきかせました。中には有名な蝶々の和歌もありました。また蝉の声、蛙の和歌を聞かせました。それがすむと、夫人は紅茶と菓子を新たに運んで来ました。そこで私は勇気をふるい起こして、詩人に私の悩みを言い表わしました。
「二、三日前に始めて鶯を聞きました。正直に申しますと、私は失望したのです。あまり早く歌い終わってしまいますから。もちろん歌うところは美しく響きますが。けれども日入る国々の鶯の荒々しい熱情、底しれぬ淵のような嘆き、あこがれの歓喜の声などはどこにあるのでしょう。そうしてまた日本の詩人たちも、失礼ですけれども鶯のように、何か軽く詩人の仕事を行うのではないかと思いますが、日本の詩人たちは、自然に沈み、ある景色と花とか、その魂にまで触れ、それから浮世のはかなさにあわれを覚えるなど、その感興を三十一文字の和歌に吹きこみます。この三十一文字は私たちには歌の表題としか思われません。歌そのものは与えられておりません」
などと私は言いました。
詩人は忍耐強く終わりまで私の言葉を聞いていました。私は、机の上に置かれた詩人の右手の指先が軽く机を叩くのを見て、その不賛成がそれも詩人の力強い返事としてわかってくるのでした。
「平和な自然のうちにありながら、何だって埃を立てたり、感情を鞭打っていらだたせたりするのでしょう。また山の上に山を置いたり、森を根絶やしにしたり! 自然においてはすべてはなれなければならぬ状態にあるのです。自然世界が移りかわって行くならば、その印象を受け、三十一字なり、十七字なりで表現したら十分ではないですか。自然に反抗したって何のためになるのでしょうか。花が咲き花が凋落する。それをあわれと思う人は、その感じる所を、決して反抗的な気持でではなく、優しい感情を紙に書き、涙ぐみながらその和歌を桜の木の枝に結びつけたらいいではないですか。と、こうわれわれ詩人たちは思うのですが――。今日知ったばかりですが、わが国の鶯もその通りするわけなんですがね」
詩人の夫人はもう一つ主人の歌のレコードをかけて、この対話の波をやわらげました。私たちはいい気持で別れを告げました。詩人は、しばらく私たちとつれだって歩み、草原を越えました。そこで私は三十一文字の謎をといたのであります。それはこういうわけなのです。小さい蝶々が詩人の袖に飛んで来てとまりました。私は日入る国の者として、すぐこの蝶が人類に与える害を思い、打とうとして手を上げました。けれども詩人は、さながらアッジジの聖フランシスコのように、この小さな生物を見えない力で自分の方にひきよせました。蝶は保護されたと感じて逃げません。詩人は、蝶の上に手をかざしてかばい、なでいとしみ、しばらくそのままで、歩いて小さい弟の蝶のために安全な場所をさがすのでした。ようやく手頃な所を見つけて、土にかがみ、小さいものを草の中に滑らせました。蝶はまもなく見えなくなってしまいました。
それは、どんなに美しい和歌になることでありましょう。

ホイヴェルス師はウグイスに託して、東西の文化の違い、こころの持ち方の違いをさり気なく書いています。
私もホイヴェルス神父様の祖国ドイツのデュッセルドルフに4年ほど住んで、その半分は市の中心のホーフガルテン(宮廷庭園)の森のそばに住んでいたので、この短編を読むと、短い夏の夜、夜通しさえずるサヨナキドリ・ナイチンゲールの美しい声を楽しんだことを懐かしく思い出します。
ヨーロッパのヨナキウグイスと日本の鶯と比べて、日本のウグイスの歌声が余り短くあっさりしていることに、師は正直に失望したと言います。
名は同じ「ウグイス」でも、ドイツのそれはスズメ目ヒタキ科ウグイス属の鳥であり、日本の鶯はスズメ目スズメ・ウグイス科の鳥で、日本三大鳴鳥の一つに数えられますが、種類が明らかに違います。たまたま「ウグイス」の名が共通したのでしょう。
YouTubeでドイツ語でNachtigallと引けば、ヨナキウグイスの音声動画が幾つもヒットします。懐かしい美しい、途切れなく長い変化に富んだ歌声です。日本の鶯のホーホケキョ、ケキョケキョ、もYouTubeで聞けます。
あとは、ホイヴェルス神父様の文章そのものが全てを語っているので、野暮なコメントは必要ないでしょう。
ただ、ナイチンゲールと言えば、19世紀クリミア戦争に従軍したフローレンス・ナイチンゲールが有名ですが、赤十字と繋がって近代看護師の基礎を築いた女性です。日本で、もし初めてでなければ、極めて初期のナイチンゲール章を授与された井深八重子さんという看護婦さんがいました。彼女は、良家のお嬢様育ちだでした。不幸にも癩病と診断され富士の裾野の神山福生病院に隔離され、1年後ぐらいに誤診と判明して、自由の身になったのですが、入院時の院内の生活の悲惨で絶望的状態が忘れられず、看護婦の資格を取って同病院に戻り、生涯そこで奉仕の生活を送られました。
私は、ホイヴェルス神父様と出会った学生時代、日本のカトリックの黄金時代の偉大な先達の跡を慕って、あちこち足を運びましたが、富士の裾野の神山福生病院には故岩下壮一神父の遺徳を偲んで訪れ、そこでまだ存命中だった井深八重子さんご自身に院内を案内していただきました。当時はまだかなりの数の癩患者が収容されていました。
岩下壮一神父と言えば、東大の哲学科の俊秀で、天皇から恩賜の銀時計を受けた人物ですが、カトリックの司祭になり、東京の初代の大司教・枢機卿の任命を受けたのに、それを断って、関西の岩下財閥の財力で神山福生病院を設立し、生涯を癩病の患者のために捧げた人です。彼は少年時代に足を怪我して、以来ビッコだったのですが、日本のカトリック教会の顔になるべき人間がチンバでは絵にならないだろうというのが辞退の理由でした。
聖書の翻訳では「癩病」は差別用語として避けられ、「重い皮膚病」などと訳されていますが、岩下師を語る場合に「思い皮膚病」の病院ではどうにもなりません。歴史的にも重い意味の込められたこの病気の聖書言葉の訳に「癩」の字が使えないというのであれば、一層のこと「レプラ」とカナ表示にすればよかったのに、と思います。
癩病院と言えば、私が高松教区の司祭として働き始めたころ、高松港から公営無料連絡ランチで30分ほどの小島の癩病院「青松園」に、二週に一度ミサをささげに行くのが大切な務めでした。数名のカトリック信者の患者さんがいて、ミサ後のお茶の時間は貴重なものでした。現在は、入園者が高齢化で皆他界し、閉園後はリゾート地か何かに変身するのではないかと風の便りにききました。80年以上も生きると、いろいろ世の移り変わりをみることになりますね。