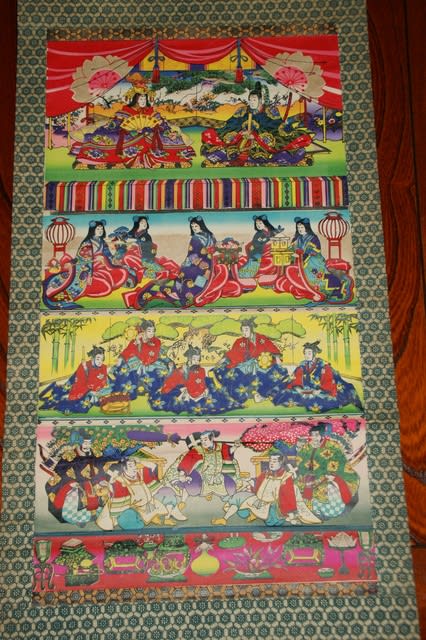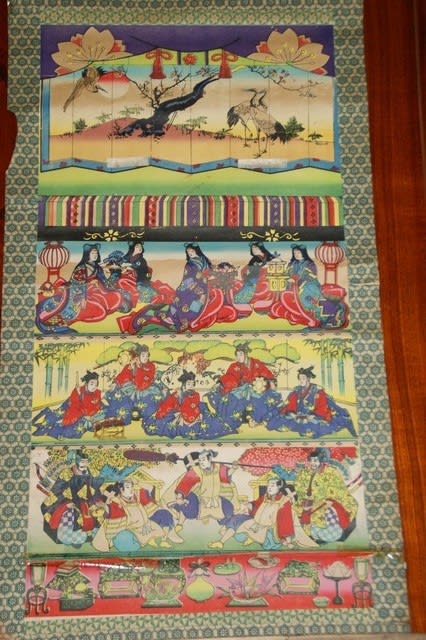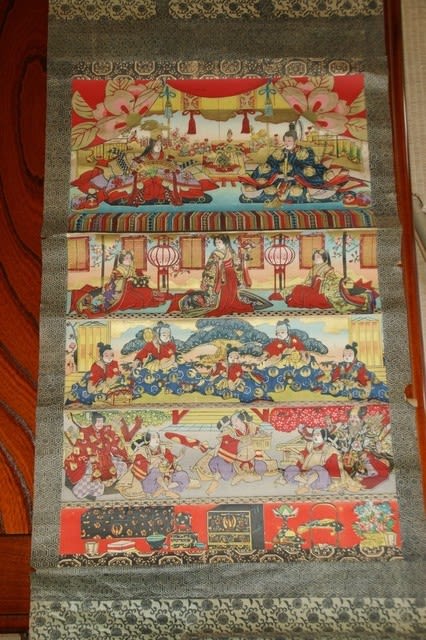「竹籠(たけかご)」(上)と「竹笊(たけざる)」(下)。今はほとんど使われなくなりました。
時間が経つにつれ、綺麗な飴色に変化していき、古色な感じが魅力的でいいですね。

「竹籠」は正式な名称・用途は判りませんが、「持ち手のある角型ゲタ脚の竹籠」とでも言うのでしょうか?

野菜や果物を入れて、持ち運び、平らな所に置いてもひっくり返らないよう足がついています。

こちらの「竹笊」も正式な名称・用途は判りませんが「深竹まるざる」とでも言うのでしょうか?
米を研ぎ水切りをしたり、野菜を洗った後の水切りに利用していたのではないかと思います。
お米が漏れないほど、網目が詰まっています。
竹は水切りに優れており、プラスチック製品とは比べのもにならないくらい水を切ってくれます。
口回りのみ針金を使用しています。

深い丸型竹笊

紐が付いていたので、腰に付けてミカンなどを収穫する竹籠でしょうか?入口が狭いのはなぜでしょう?

竹で出来た「行李(こうり)」。竹を編んでつくられた葛籠(つづらかご)の一種。直方体の容器でかぶせ蓋となっている。
衣料や文書あるいは雑物を入れるために用いる道具。かぶせ蓋で一対のはずなのに片方がありません。

「箕」。脱穀などで不要な小片を吹き飛ばすことを主目的として作られる平坦なバスケット形状の選別用農具(農作業で使う手作業用具)。機械式の脱穀用具と区別して手箕(てみ)とも言う。箕の裏に昭和39年、43年と墨で書いてあったのでその頃新調したのでしょう。