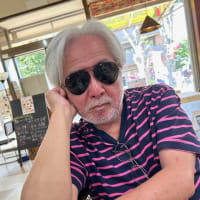【連載】腹ふくるるわざ⑮
グリーンレンジャーに赤信号が
桑原玉樹(まちづくり家) 
なんと県から「待った!」の回答
これまでにもグリーンレンジャーの活動について紹介してきた。この会は、国道464号線沿道や法目川調節池にはびこる葛、笹竹等を退治するのが目的だ。
道路や調節池は千葉県の管理下にある。つまりグリーンレンジャーの活動は千葉県の管理が及ばない範囲を補完しようとするものだった。そのため千葉県のアダプトプログラムに基づいて活動を行うことにして申請し、3カ月にわたり数回の協議をしてきたのである。
ところが、この活動に「待った!」がかかった。「国道464号線は危険だから、アダプトプログラムで実施するのは難しい」と県の担当者から以前から聞いていたが、なんと調節池についても「立ち入り禁止にしているフェンスの内側には立ち入らないでください」と連絡があったのだ。
調節池とは何?
そもそも調節池とは何か。豪雨などで河川があふれることがある。それを防ぐためには、一時的に流量を調節するのが調節池。その中でも特に都市開発に伴うものが「調整池」と言われている。南山公園にある法目川調節池は、千葉ニュータウン開発の中で整備されたので、調整池と言ってもよい。
都市開発すると、それまで田畑や山林など保水力のある土地に降っていた雨が、建物の屋根や舗装された道路に降る。そのため雨水は開発地区から急速に流れ出し、下流の川があふれてしまう。そこでいったん調整池に貯めておいて、雨が収まってからゆっくり放流するために調整池が設置される。
千葉県の北総地域では開発面積1ヘクタール当たり1450トンの雨水が貯まるように開発指導要綱で定められていることが多い。100ヘクタールの開発なら14万5000トン、仮に調整池の平均水深が2~5mなら面積は 2.9~7.3ヘクタールにもなる。
殺風景な調整池
このように結構な広さが必要になるので、採算性に重きを置くと機能性一点張りの無機質で殺風景な調整池になりがちだ。しかし「それではあまりにも…」と景観を重視する調整池も出てきた。法目川調節池は従来の谷戸を堰き止めて作られたから、自然法面も残り、景観的には比較的良い。
それでも、水辺との触れ合いなどはまだまだ親水空間としては不十分だ。また堤体にはびこる雑草や雑木の除去についても、マニュアルどおりに管理区域から約5mの幅を除草するだけで、その内側は葛などが伸び放題となっている。
景観に配慮した調整池も
●小室では水際まで除草した
小室調節池は、白井市に隣接する船橋市の小室地区にあり、法目調節池と同じように千葉ニュータウンの開発で設置された調整池だ。しかし、堤体は水際まで除草されているし、住民も水辺近くまで行くことができる。管理は千葉県ではなく、船橋市が行っている。管理者によってずいぶん違うものだ。

▲小室調節池は水辺まで除草された
●長野県大町市ではフェンス内を公民協働で除草
また、除草などを住民が行った調整池もある。長野県大町市にある久保調整池(ため池)で令和2(2020)年10月、同市の職員と住民計70人が一緒になって、「ため池の景観整備イベント~久保調整池を再生しよう~」と銘打って池を全面的に水抜きしたのだ。
水抜きの後で沈砂池の泥を除き、停滞やフェンスの除草を行ったのである。立ち入り禁止のフェンスはあるが、その中での作業だった。

▲久保調整池(大町市)で市民と市役所が協働でフェンスや堤体の除草
●柏市ではフェンスを取り去り親水空間に
当初は殺風景だった調整池でも、その後の変更で住民が水辺を楽しむことができる様になった例が柏市にある。つくばエクスプレスの沿線開発として千葉県により整備された柏の葉地区にある2号調整池だ。改修前の調整池は周囲に高さ1.8メートルのフェンスがあり、水辺に近づくことはできなかった。

▲改修前の「柏の葉2号調整池」(柏市)
この調整池を三井不動産や柏市など公民が連携して交流空間に大規模改修し、平成28(2016)年11月「アクアテラス」としてオープンさせたのだ。調整池の外周6カ所にゲートを設置し、階段やスロープを使って水辺に下りられるようにした。今ではイベントも開かれるなど、市民の憩いの場になっている。さらに平成30(2018 )年度のグッドデザイン賞に輝いた。

▲柏の葉調整池改修後の「アクアテラス」(柏市)

▲「アクアテラス」で行われた夜のイベント

▲市民で賑わう「アクアテラス」の昼
●八千代市でもフェンスがない
八千代市にある萱田地区公園は、住宅公団が開発した地区にある公園だ。公園全体が調整池の機能を持っているが、美しい水辺を持つ公園として整備された。当然水辺近くまで住民は行くことができるし、除草も当然全体的になされている。

▲萱田地区公園(八千代市)。公園全体が調整池の機能をもち大雨時には水没する

▲萱田地区公園の修景施設。水辺の柵は低い
水辺を楽しめる調整池が夢なのに
さて法目川調節池は住宅地の中の調整池だ。水の事故を起こしてはいけない。しかし、管理者としての千葉県には、管理責任一辺倒ではなく、水辺空間を楽しむための工夫も求められているのではないだろうか。
もう 20数年前になるが、当時職場の顧問弁護士だった元日弁連会長の中坊公平さんがこう言った。
「池の周りにフェンスは作らないでくれ。仮に子供が転落しておぼれ死んで訴訟になったら私が弁護する」
もちろん安全をないがしろにするということではない。安全な設計をしたうえで、住民を仰々しいフェンスで水辺から遠ざけてはいけないという意味だ。
また景観に配慮したり、除草範囲を拡げたくても、県には予算の制約があるかもしれない。だからこそ住民のパワーを利用しながらも安全を確保し、景観の向上を図る方策に知恵を出してほしいものだ。
「フェンス内には立ち入らないでほしい」と一方的に通知するのではなく、住民と一緒に知恵を出し合う。そんなことができないものだろうか。いずれにしても、グリーンレンジャーはまだまだくじけるわけにはいかない。

▲景観を重視した故・中坊公平氏

▲葛と雑木が繁茂する法目川防災調節池(南山公園)の堤体

▲法目川防災調節池には「フェンス内立入り禁止」の無粋な看板が
【桑原玉樹(くわはら たまき)さんのプロフィール】
昭和21(1946)年、熊本県生まれ。父親の転勤に伴って小学校7校、中学校3校を転々。東京大学工学部都市工学科卒業。日本住宅公団(現(独)UR都市機構)入社、都市開発やニュータウン開発に携わり、途中2年間JICA専門家としてマレーシアのクランバレー計画事務局に派遣される。関西学研都市事業本部長を最後に公団を退職後、㈱千葉ニュータウンセンターに。常務取締役・専務取締役・熱事業本部長などを歴任し、平成24(2012)年に退職。現在、印西市まちづくりファンド運営委員、社会福祉法人皐仁会評議員。