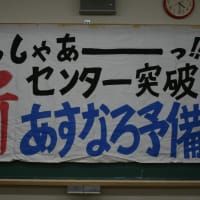一年先輩の佐宗さんを通じて、粋棟さんと知己を得た。国立の教育大学で西洋史学を博士課程まで修められ、某シンクタンクに佐宗さんと同期入社となったそうだから、結構歳が離れている。二条城に近いご実家から大阪の会社まで通勤されていて、佐宗さん曰く、住んでいるところも近いし、趣味も合いそうだから「会わせてみたくなった」のだそうだ。二人の職場のある大阪まで呼び出されたのか、京都で引き合わされたのか、初対面がどこだったかはっきりと覚えてはいない。たぶん京都だったんだろうと思う。落ちあったとき、佐宗さんと粋棟さんは二人で『形而上学しりとり』というのをやっていた。どういうものかよく分からなかったが「バカボンのおまわりさんのピストル」とか何とか訳のわからないことを言い合っている。酔狂なこった。佐宗さんは元来理屈言いというのか、ともするとちょっと衒学的な言い回しに振り回されるようなところがある。おんなじような人がもう一人増えるのかと思っていたが、実際に本人と話をしてみると読んできた作家や漫画家、聞いてきた音楽、いいと思った映画、好きな落語家、その頃気に入っていたミステリーシリーズと、気味の悪いほどことごとく合致した。生活圏がそれほど離れてはいないので、普段よく利用する本屋もCD屋も大体同じである。今もあるかどうかは知らないが、千本今出川を少し下がった東側に間口のそれほど広くない、小汚いというと失礼だが店先が乱雑な感じの新刊書店があって、古書店に見えなくもないからわざわざこう書いているのだが、そこは品揃えがいい。普通なら入荷しないような、入荷しても1冊とか2冊とかの扱いを受けそうな本でも、発売日には複数冊を店頭に並べていた。そこの常連だという話を聞いて、できた方だと思った。もとより酔っ払いの判断である、碌な根拠などあるはずもないが、初対面の印象はそんなわけで「なんかいい人」であった。それからちょくちょくご一緒させてもらったが、佐宗さんは就職を期に上七軒のアパートを引き払って大阪に住んでいたので、京都在住の二人で呑むこともあった、というか、呑みに連れて行ってもらった。時々はうちの下宿で呑むこともあった。こっちに合わせて付き合うのを面白がっているようなところもある。そういうところもとっつき易さの一因だったんだろうと思われる。
あるとき、卒論の話になった。平安末期から鎌倉初期成立のある絵巻物を扱おうと考えていたが、それまで調べてあったものをまとめたメモを見せると豪(えら)く気に入って、その頃粋棟さんが出身大学に残って研究活動をしいる人たちと定期的に行っていた歴史学の研究会で発表してみたらどうだと誘ってくれた。当日の出席者はそれほど多くなかったが、学部生から院生、粋棟さんのような修了者まで、いろんな立場の人が参加している。その場を仕切ったのは粋棟さんと同期という妙に恰幅がいい方で、その体つきといい髪型といい、目のくりくりとしたところまで、往時のサモ・ハン・キンポーを髣髴(ほうふつ)とさせる。その金峰氏にも興味を持ってもらえたようで、いろいろと意見を言ってくださって、アドバイスも多くいただいて、大いに参考になった。終了後は大学近くの行きつけの店で歓迎会をしてくれたが、金峰氏はビールばかり飲んで、酔ってくるといろんな教授の酔態を滔滔(とうとう)と語り始めた。斯界のビッグ・ネームもいくつか挙がっている。どこで誰と呑んだって酔うのに変わりはない。最後は金峰氏と、一緒にいた学部生とが最寄りの駅まで送ってくれた。誰かが大きな声で喚(わめ)いていたような気もする。電車を乗り継いで阪急京都線大宮駅まで戻って来る間に二人とも少し醒めてきて、粋棟さんと二人で少しだけ飲みなおしてから別れた。
阪急宝塚線の石橋駅近くにある会場で、立川談志・桂米朝二人会が行われた。行きたいけれども手元不如意で余裕がない。そんな話をしたら、ありがたいことに佐宗さんと粋棟さんが折半でチケット代を持ってくださるということになった。粋棟さんと佐宗さんは職場からなので、石橋駅で待ち合わせをした。指定席ではなかったように思うが、二階席のほぼ真ん中に席を取った。三人並んで座った右側にハンチングをかぶったおじいさんが座っている。最初は談志家元の『ぞろぞろ』、その最後、「一生懸命に研ぎ澄ました剃刀でスーっと剃るてぇと、後から新しい髭がぞろぞろ…」この『ぞろぞろ』の二つ目の『ろ』の音が出切るか出切らないか、『…』の余韻も味わう間もなく間髪をいれずに拍手を始めた人がいた。見ると横にいるおじいである。いかにも「わしは米朝を見に来たんや」とでも言いたげに、なんだか苦虫を噛み潰したような渋い顔をして、『引っ込め』感モロ出しに拍手をしている。こういうところで誰かが拍手を始めると皆がそれに追従する。そのとき談志家元は半ば口を開いて何かを言い出しそうなところだったが、その拍手に小さく「ま、いいや」とつぶやいて深々とお辞儀をした。そのあと米朝師が一席、中入りがあって二人の座談があり、米朝師、談志家元でトリ、という構成だったが、中入りのときに煙草を吸いにロビーに出ると、「誰やあの拍手」とか「絶対あれなんか言いかけてたで」といった声がちらほらと聞こえる。三人で「やっぱり、ねぇ」という話になった。実はそこのところだけが鮮明に思い出されて、あとの記憶はあやふやになっている。なかなかない機会なのに、あのおじい奴(め)。落語会が終わって、石橋駅のそばの焼鳥屋でなんだかんだとだべってから三人で十三まで一緒に行って、そこで京都線に乗り換えた。佐宗さんは同じ京都線の途中の駅で降り、粋棟さんと大宮駅まで、四条大宮でまた少しご一緒して帰った。
粋棟さんとは卒業してから何度かは連絡を取ったが、やがて疎遠になってしまった。佐宗さんとは細々とやり取りが続いていて、あるとき佐宗さんにメールを打ちながらふと思い出して粋棟さんの消息を尋ねてみた。すると、すでに物故されたという返事が返ってきた。まだ40代で、結婚してからの年数も浅く、お子さんもまだ小さいという。亡くなる前年の健康診断でなんだかの数値が異常に高かったそうで、周りからも節制するようすすめられていたが、仕事でかなり無理をされていたらしい。佐宗さんから粋棟さんのご実家の住所と墓所を教えようかと言ってくださったが、亡くなってから1年以上経っていた。のこのこと出向いて行って、ご家族に新たにつらい気持ちを思い出させるようなことにならないか、と心配になり、それに今更どの面下げて、という気もする。ちょっとその気になりかけたがさすがに差し出がましい気がして、よしましょう、それより酒を呑みましょう、ということになった。その晩は一杯余分に酒をついで、粋棟さんの分として酒を呑んだ。佐宗さんもメールのやり取りの後同じことをしたそうだから、粋棟さんは大阪と鳥取のどっちで呑むか迷ったかもしれない。とはいえ故人に関して思うことなど生きている側の思い込みに過ぎないので、自分が一緒に呑んでくれてはるな、と思っていれば、どっちであろうとかまわない。
それから粋棟さんについていろいろ考えていると、どうやら談志家元の『ぞろぞろ』に、あのときの満場の拍手に行き着いてしまうようである。
あるとき、卒論の話になった。平安末期から鎌倉初期成立のある絵巻物を扱おうと考えていたが、それまで調べてあったものをまとめたメモを見せると豪(えら)く気に入って、その頃粋棟さんが出身大学に残って研究活動をしいる人たちと定期的に行っていた歴史学の研究会で発表してみたらどうだと誘ってくれた。当日の出席者はそれほど多くなかったが、学部生から院生、粋棟さんのような修了者まで、いろんな立場の人が参加している。その場を仕切ったのは粋棟さんと同期という妙に恰幅がいい方で、その体つきといい髪型といい、目のくりくりとしたところまで、往時のサモ・ハン・キンポーを髣髴(ほうふつ)とさせる。その金峰氏にも興味を持ってもらえたようで、いろいろと意見を言ってくださって、アドバイスも多くいただいて、大いに参考になった。終了後は大学近くの行きつけの店で歓迎会をしてくれたが、金峰氏はビールばかり飲んで、酔ってくるといろんな教授の酔態を滔滔(とうとう)と語り始めた。斯界のビッグ・ネームもいくつか挙がっている。どこで誰と呑んだって酔うのに変わりはない。最後は金峰氏と、一緒にいた学部生とが最寄りの駅まで送ってくれた。誰かが大きな声で喚(わめ)いていたような気もする。電車を乗り継いで阪急京都線大宮駅まで戻って来る間に二人とも少し醒めてきて、粋棟さんと二人で少しだけ飲みなおしてから別れた。
阪急宝塚線の石橋駅近くにある会場で、立川談志・桂米朝二人会が行われた。行きたいけれども手元不如意で余裕がない。そんな話をしたら、ありがたいことに佐宗さんと粋棟さんが折半でチケット代を持ってくださるということになった。粋棟さんと佐宗さんは職場からなので、石橋駅で待ち合わせをした。指定席ではなかったように思うが、二階席のほぼ真ん中に席を取った。三人並んで座った右側にハンチングをかぶったおじいさんが座っている。最初は談志家元の『ぞろぞろ』、その最後、「一生懸命に研ぎ澄ました剃刀でスーっと剃るてぇと、後から新しい髭がぞろぞろ…」この『ぞろぞろ』の二つ目の『ろ』の音が出切るか出切らないか、『…』の余韻も味わう間もなく間髪をいれずに拍手を始めた人がいた。見ると横にいるおじいである。いかにも「わしは米朝を見に来たんや」とでも言いたげに、なんだか苦虫を噛み潰したような渋い顔をして、『引っ込め』感モロ出しに拍手をしている。こういうところで誰かが拍手を始めると皆がそれに追従する。そのとき談志家元は半ば口を開いて何かを言い出しそうなところだったが、その拍手に小さく「ま、いいや」とつぶやいて深々とお辞儀をした。そのあと米朝師が一席、中入りがあって二人の座談があり、米朝師、談志家元でトリ、という構成だったが、中入りのときに煙草を吸いにロビーに出ると、「誰やあの拍手」とか「絶対あれなんか言いかけてたで」といった声がちらほらと聞こえる。三人で「やっぱり、ねぇ」という話になった。実はそこのところだけが鮮明に思い出されて、あとの記憶はあやふやになっている。なかなかない機会なのに、あのおじい奴(め)。落語会が終わって、石橋駅のそばの焼鳥屋でなんだかんだとだべってから三人で十三まで一緒に行って、そこで京都線に乗り換えた。佐宗さんは同じ京都線の途中の駅で降り、粋棟さんと大宮駅まで、四条大宮でまた少しご一緒して帰った。
粋棟さんとは卒業してから何度かは連絡を取ったが、やがて疎遠になってしまった。佐宗さんとは細々とやり取りが続いていて、あるとき佐宗さんにメールを打ちながらふと思い出して粋棟さんの消息を尋ねてみた。すると、すでに物故されたという返事が返ってきた。まだ40代で、結婚してからの年数も浅く、お子さんもまだ小さいという。亡くなる前年の健康診断でなんだかの数値が異常に高かったそうで、周りからも節制するようすすめられていたが、仕事でかなり無理をされていたらしい。佐宗さんから粋棟さんのご実家の住所と墓所を教えようかと言ってくださったが、亡くなってから1年以上経っていた。のこのこと出向いて行って、ご家族に新たにつらい気持ちを思い出させるようなことにならないか、と心配になり、それに今更どの面下げて、という気もする。ちょっとその気になりかけたがさすがに差し出がましい気がして、よしましょう、それより酒を呑みましょう、ということになった。その晩は一杯余分に酒をついで、粋棟さんの分として酒を呑んだ。佐宗さんもメールのやり取りの後同じことをしたそうだから、粋棟さんは大阪と鳥取のどっちで呑むか迷ったかもしれない。とはいえ故人に関して思うことなど生きている側の思い込みに過ぎないので、自分が一緒に呑んでくれてはるな、と思っていれば、どっちであろうとかまわない。
それから粋棟さんについていろいろ考えていると、どうやら談志家元の『ぞろぞろ』に、あのときの満場の拍手に行き着いてしまうようである。