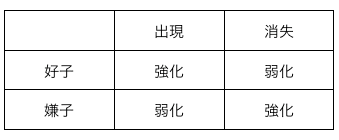社会問題になっているスマホ依存、ゲーム依存…
その解決法はあるのでしょうか?
もともとは利便性を求めて開発・発展してきたものなので、
もはや手放すことはできません。
「使われるな、使いこなせ!」
という意見もありますが、なかなかこれが…。
科学的データで解決法を見いだせないかなあ…
と常々感じていたところに、以下の記事が目に留まりました。
<ポイント>
・子どもをスマホやダブレット、テレビなどのスクリーンベースのデバイスから引き離すことは可能である。
・最も効果的な方法2つ;
(その1)食事中や就寝時にデバイスの使用を禁止する。
(その2)親自身が適切にデバイスを使用する姿を子どもに見せる
・子どもに説教している親自身も、これらのことを実践するよう心がける。
・デバイスの使用を「ご褒美」や「罰」として用いることは、スクリーンタイム減少効果がない。
まあ、「親が手本を見せる」というオチですね。
■ 子どものスクリーンタイム削減に親がすべきこととは?
(HealthDay News:2024/06/28:ケアネット)より一部抜粋(下線は私が引きました);
常にスマートフォン(以下、スマホ)を手にしている子どもに対してフラストレーションを抱えている親にとって心強い研究結果が明らかになった。子どもをスマホやダブレット、テレビなどのスクリーンベースのデバイス(以下、デバイス)から引き離すことは可能なことが、米カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)のグループによる研究で示されたのだ。同研究では、食事中や就寝時にデバイスの使用を禁止すること、親自身が適切にデバイスを使用する姿を子どもに見せることの2つの実践が最も効果的であることが示されたという。・・・
論文の筆頭著者である、UCSFベニオフ小児病院の小児科医であるJason Nagata氏は、「この研究結果は、親がトゥイーン(8〜12歳の子ども)やティーンに使える具体的な戦略を示しているという点で心強い。その戦略とは、スクリーンタイムに制限を設けること、子どものデバイスの使用状況の把握に努め、寝室にいる間や食事の時間にはデバイスの使用を禁じることだ」と話す。さらに「子どもに説教している親自身も、これらのことを実践するよう心がけるべきだ」と付け加えている。
Nagata氏らは、米国の思春期の脳の発達に関する研究(ABCD研究)の参加者のうち約1万人の12~13歳の子どものデータを分析した。ABCD研究では、親が「わが子はデバイスを使いながら眠りにつく」などの項目についてどの程度当てはまるのかを、1(全く当てはまらない)から4(強く当てはまる)までの4段階で回答していた。その後、親の評価により子どもの1日のスクリーンタイムをどの程度予測できるのかを調べた。・・・
その結果、子どもの就寝時のデバイスの使用は、1日当たりのスクリーンタイムの1.60時間の増加と関連することが明らかになった。同様に、食事中のデバイスの使用と、親が子どもと一緒にいるときにもデバイスを使用する「悪い手本」である場合も、スクリーンタイムはそれぞれ1.24時間と0.66時間の増加に関連していた。
一方で、食卓や寝室でのデバイスの使用を禁止するルールを設けることは、子どもの1日当たりのスクリーンタイムの1.29時間の減少につながっていた。また、食事中や就寝時の子どものデバイスの使用状況を監視することも効果的で、1日当たりのスクリーンタイムは平均で0.83時間減っていた。このほか、効果がない対策があることも分かった。デバイスの使用を「ご褒美」や「罰」として用いている親の子どもでは、1日当たりのスクリーンタイムが平均で0.36時間長かった。
Nagata氏は、「子どものデバイスの使用時間を減らすために親にできることの中で最も重要なのは、寝室でのデバイスの使用を禁止することかもしれない。就寝時のスクリーンタイムによって思春期早期の健康や発達に不可欠な睡眠時間が減ってしまう。親は、子どもの寝室にはデバイスを置かないこと、夜間にはデバイスの電源や通知をオフにすることを検討するのが良いだろう」と話している。
論文の筆頭著者である、UCSFベニオフ小児病院の小児科医であるJason Nagata氏は、「この研究結果は、親がトゥイーン(8〜12歳の子ども)やティーンに使える具体的な戦略を示しているという点で心強い。その戦略とは、スクリーンタイムに制限を設けること、子どものデバイスの使用状況の把握に努め、寝室にいる間や食事の時間にはデバイスの使用を禁じることだ」と話す。さらに「子どもに説教している親自身も、これらのことを実践するよう心がけるべきだ」と付け加えている。
Nagata氏らは、米国の思春期の脳の発達に関する研究(ABCD研究)の参加者のうち約1万人の12~13歳の子どものデータを分析した。ABCD研究では、親が「わが子はデバイスを使いながら眠りにつく」などの項目についてどの程度当てはまるのかを、1(全く当てはまらない)から4(強く当てはまる)までの4段階で回答していた。その後、親の評価により子どもの1日のスクリーンタイムをどの程度予測できるのかを調べた。・・・
その結果、子どもの就寝時のデバイスの使用は、1日当たりのスクリーンタイムの1.60時間の増加と関連することが明らかになった。同様に、食事中のデバイスの使用と、親が子どもと一緒にいるときにもデバイスを使用する「悪い手本」である場合も、スクリーンタイムはそれぞれ1.24時間と0.66時間の増加に関連していた。
一方で、食卓や寝室でのデバイスの使用を禁止するルールを設けることは、子どもの1日当たりのスクリーンタイムの1.29時間の減少につながっていた。また、食事中や就寝時の子どものデバイスの使用状況を監視することも効果的で、1日当たりのスクリーンタイムは平均で0.83時間減っていた。このほか、効果がない対策があることも分かった。デバイスの使用を「ご褒美」や「罰」として用いている親の子どもでは、1日当たりのスクリーンタイムが平均で0.36時間長かった。
Nagata氏は、「子どものデバイスの使用時間を減らすために親にできることの中で最も重要なのは、寝室でのデバイスの使用を禁止することかもしれない。就寝時のスクリーンタイムによって思春期早期の健康や発達に不可欠な睡眠時間が減ってしまう。親は、子どもの寝室にはデバイスを置かないこと、夜間にはデバイスの電源や通知をオフにすることを検討するのが良いだろう」と話している。