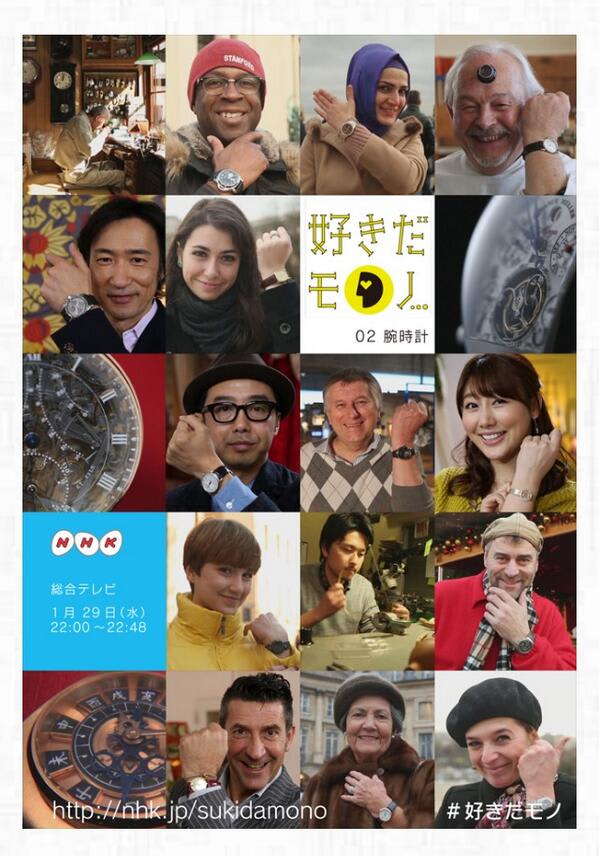近隣のブランド時計を扱う専門店へ久しぶりに出かけました。
目的は「
オメガ シーマスター アクアテラ コーアクシャル」。
「10年間メインテナンスフリー」というキャッチコピーで注目を集める新ムーブメント+150m防水を引っさげ、ロレックスのデイトジャストに真っ向勝負の自信作・・・実物を見て触って ”買い” かどうか判断しよう、と。
そこの時計師さんと時計談義が弾んでしまいました。
彼は年齢不詳のジェントルマンで、今までにも少し話をしたことがありましたが、その出で立ちから店長さんだと勘違いしてきました。
バーゼルフェアやジュネーブサロンにも足を運び、時計マニアの松本零時さんのコレクションも見せてもらったことがあるそうです。
そんなわけで話題は尽きず、オメガから始まって多岐にわたり、コーヒーのおかわり3杯目を勧められたときに時計を見るとすでに2時間以上経過・・・ちょっと長居しすぎましたが、楽しいひとときを過ごせました。
話の内容をかいつまんでメモしておきます;
□
オメガ シーマスター アクアテラ コーアクシャル
現在のものは新型(第二世代)でムーブメントもコーアクシャル専用に設計された逸品。実は旧型(第一世代)は従来のムーブメントを無理やりコーアクシャルにアレンジしたもので、時計師から見るとちょっと無理があった感が否めない。
本来
コーアクシャルは精度を追求したシステムであり、決してメインテナンスフリーが売りではない。それを謳ったのはメディアであり、オメガは一言も宣伝していない。新しいシステムなので修理が難しい。
私の印象・・・旧型と新型を並べて眺めると、質感の違いがハッキリと感じられる。実物を手に取ると、ケースもブレスもブラッシュアップされて精悍さを増した(値段も上昇)。旧型は丸っこくてボリューミー、悪く云えば締まりがないデザイン。人気が出る前のモーリス・ラクロアに似ている。新型ケースは無駄を省いて造形美を高め、ブレスはロレックスの三連ブレスに近い印象。ケースのポリッシュ/サテン仕上げは処理が難しいタイプで、オメガの得意とする分野である。
価格を重視すると、旧型に手が伸びそうになるが、並べて比較すると新型の方が ”そそる” 時計と云える。
□
世界の時計産業の2つの潮流
時計業界では2つの流れが歴然と存在する。
①「イギリス~ドイツ~アメリカ」ライン。
②「フランス~スイス」ライン。
イギリスとフランスの時計産業はほぼ同時期に平行して発達した。フランスで宗教改革が勃発した際、知識人であった時計師たちはスイスの山へ逃避し、そこの屋根裏部屋に隠れて時計制作を行うようになったのがスイス時計の由来。
イギリスの時計技術は地中海を渡り、ドイツに伝わった。その後アメリカもドイツの影響を受けるに至り、日本もこのラインに入る。
ドイツ時計のムーブメントの特徴は「正確」「頑丈」・・・つまりゲルマン民族の質実剛健さがここでも現れている。有名な「
3/4プレート」は堅牢性を追求した結果生まれた。
代表ブランドとしての
ランゲ&ゾーネの文字盤デザインは実用性と幾何学的黄金律で成り立っている。特に「
ランゲ1」はビッグデイトの走りであり、時針を中央から外したのはデイト表示を隠さないためである。
スイスの時計の源流であり伝統は ”ジュネーブ仕様” 。
ジュネーブ・シールに代表されるムーブメントであり、色々な約束事がある。代表ブランドはもちろんパテック・フィリップ。
□
パテック・フィリップの魅力
世界的に「時計」としての資産価値を認められているのは
パテック・フィリップのみ。ロレックスでさえも認められていない。
どういうことかと云うと、例えば30年前に100万円で販売していたパテックの時計は、30年経過しても為替相場に対応して価格が変わるだけで、基本的な価値は変わらない(むしろ上がることも)。
パテックの魅力は常に理想を求めて時計づくりをしてきていること。値段を設定してから時計を造ろうなどと云うことはなく、理想を追求したらこの値段になった、という流れ。自社の時計はいくら古くても修理を受け付けるため、昔の工作機械も残されている。
ムーブメントの美しさはピカイチで、隅々まで磨きがかけられている。しかし、スケルトンでそれを見せびらかすことはない(一時、日本向けモデルでありましたけど)。
カラトラバの96(クンロク)モデルなど、ヴィンテージ・パテックは30~33mmの小振りな時計。しかし手首に装着すると俄然存在感を増すので不思議である。特に横から見たケースの造形美は他の追随を許さない。

パテックの社員食堂のシェフはフランス三つ星レストランのシェフが招かれて作っている。実はロレックスでも同じレベルという。
□
ヴァシュロン・コンスタンタンの残念なところ
パテック・フィリップ、オーデマ・ピゲとともに雲上ブランドの一角をなす
ヴァシュロン・コンスタンタン(昔はバセロン・コンスタンチンと呼ばれていました)。
その歴史を見ると、やりたいことは何でのやり、いろんなこと手を出し過ぎて失敗することも。2003年に発表したグランド・コンプリケーションで「上がり」を経験後、目的を見失ってしまっているようだ。その後はオールド・モデルを復活させたりしているが、リメイクにとどまり新たな魅力が付加されないところが残念。
ヴァシュロンの自動巻ローターのベアリングは長年使用すると劣化する傾向があり、アンティークの購入を考えるなら手巻きがベター。
もちろん、このコメントは雲上ブランドと認めた上での辛口批評であり、その辺の普及ブランドとはレベルが違う。
私はバセロンと呼ばれていた時代からのファンです。実はいくつか所有していますが、いちばんのお気に入りは「ノスタルジー」というモデル。ティアドロップ・ラグに丸っこい印象のケース。1940~50年代の雰囲気を纏っています。

□
IWC創業者であるフローレンス・ジョーンズにまつわる話。
”懐中時計のパテック” と称されるアメリカの時計ブランド「
ハワード」。その社長であったF.ジョーンズがスイスに乗り込んで、スイスの安い人件費を使っての大量生産を試みた。目指したのは高級時計ではなく普及モデルだったようだ。営業にかけずり回ってもなかなか相手にしてもらえず、ようやく見つけたスポンサーがモーザー氏(元時計師の富豪で、近年再興され真面目な時計づくりで話題のブランド)。彼のサポートの元、ドイツに近いシャフハウゼンで創業した。半分はドイツからの労働者だった。アメリカ(社長)とスイス(土地)とドイツ(職人)が手を組んで作った会社という意味で、国際時計会社(
International watch company, IWC)と命名した。
しかし、会社経営は上手くゆかず、4年足らずで他人の手に渡り、F.ジョーンズは事実上クビになってしまう。彼は失意の帰国後、消息不明。
□
カルティエのCPCPライン
カルティエは時計としてより宝飾品として評価されるブランド。しかし、高級ムーブメントを搭載するCPCPライン (CPCP=Collection Privée Cartier Paris) というものが存在し、こちらは高く評価されていた(現在はなくなってしまったらしい)。
その昔、私は「タンク・フランセーズ」のコンビモデルを購入したことがあります。しかしブレスの縞模様に馴染めず、手放してしまいました。緩やかなカーブを描くブレスの装着感は絶品だったのですが・・・。今後狙うとしたら、オールド・タンクでしょうか。

□
時計に使う潤滑油の進化
潤滑油の質は温度変化への適応能力と紫外線への耐性で評価される。
現在スイスで主に使われているのは約40年前に作られた油。長らくスタンダードの地位をキープしてきたが能力は十分とは云えない。また、昨今のスケルトンブームで耐紫外線能力の必要性が以前にも増してクローズアップされてきている。
近年、シチズンで「
AOオイル」という非常に優れた油が開発された。今後普及すると思われる。
□
「デカ厚時計ブーム」を予測していたフランク・ミューラー
近年、日本人の手首には余るほどに大きい腕時計が幅をきかせており、当初は新興ブランドが中心であったが様子を見ていた伝統的ブランドも参入した。今では確固たる一分野を形成するに至っている。
このブームが始まる前に、「これからは大きな時計が流行るよ」というフランク・ミューラーのインタビュー記事を読んだ。理由は書いていなかったが、事実その後ブーム到来。なぜ予測でき七日ずっと不思議に思ってきたが、5年ほど前に謎解きをしたインタビュー記事を目にしてなるほどと思った。キーワードは「G-shock」。機能優先であんなにかさばる時計を若者は喜んで使っている。彼らは大人になってもそんな時計を好むのではないか、と予想したらしい。
店内のディスプレイケースは基本的にブランド専用で借り受けるそうです。一つのブランドを扱うには、結構な費用がかかるとか(こちらから頭を下げて扱わせてもらうらしい)。
オーデマ・ピゲとハリー・ウィンストンのケースには時計が無く、撤去中とのこと。
ちょっと寂しさを感じました。