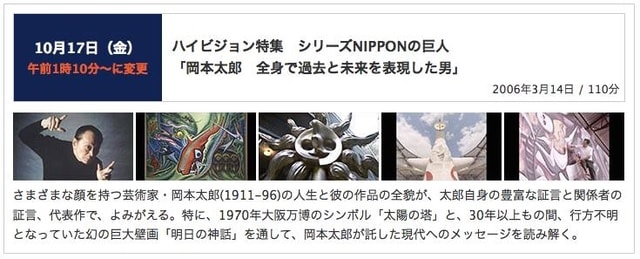人気作家によるエッセイの語りおろしCD集を聴きました。

五木氏は「闇を見つめる作家」だと思います。
日の当たらない人々や歴史に向けたまなざしは、私の波長とよく合うのです。
放浪の旅に明け暮れた若かりし頃の作品も好きですし、
民俗学的な視点を持ったエッセイ集も好きです。
CD集を一通り聴き終えて、彼の原点は戦争の引き揚げ体験であることがわかりました。
優秀な人材もあっという間にいのちを奪われてしまう戦争。
彼の父は平壌で師範学校の教師をしていました。
戦争に負け、朝鮮半島から日本へ撤退・帰国する際に、ロシアによる略奪や非人道的行為を目の当たりにしました。
デカルトの「われ思う、故にわれあり」という文言は有名ですが、実はそれ以前に某宗教家の「われあり、故にわれ思う」という文言があったそうです。
五木氏は某宗教家の文言の方に惹かれるというのです。
人生で何か成し遂げて初めていのちに意味があるのではなく、命があること自体が尊いのではないか。
そうでなければ、戦争で若くして散っていったたくさんのいのちが救われない。
戦後、日本人は努力し前へ進むことを善とし、立ち止まり後ろ向きになることを悪とする傾向がありました。
ポジティブ思考を良しとし、ネガティブ思考を「根暗」とからかう風潮は私の時代にもありました。
しかし五木氏は、物事の明るい面だけ見続けるだけでよかったのだろうか、と疑問を投げかけます。
人間は喜びと悲しみの両者を経験して初めて感情が完成する。片方だけでよいということはない。本当の悲しみを経験した者だけが本当の喜びを知るはずだ、と云います。
明るい面だけを見る風潮の弊害として、人間の心の闇が地下に深く広く浸透してしまった。
それがいじめであり、不登校・引きこもりであり、自殺者の増加である、と。

五木氏は「闇を見つめる作家」だと思います。
日の当たらない人々や歴史に向けたまなざしは、私の波長とよく合うのです。
放浪の旅に明け暮れた若かりし頃の作品も好きですし、
民俗学的な視点を持ったエッセイ集も好きです。
CD集を一通り聴き終えて、彼の原点は戦争の引き揚げ体験であることがわかりました。
優秀な人材もあっという間にいのちを奪われてしまう戦争。
彼の父は平壌で師範学校の教師をしていました。
戦争に負け、朝鮮半島から日本へ撤退・帰国する際に、ロシアによる略奪や非人道的行為を目の当たりにしました。
デカルトの「われ思う、故にわれあり」という文言は有名ですが、実はそれ以前に某宗教家の「われあり、故にわれ思う」という文言があったそうです。
五木氏は某宗教家の文言の方に惹かれるというのです。
人生で何か成し遂げて初めていのちに意味があるのではなく、命があること自体が尊いのではないか。
そうでなければ、戦争で若くして散っていったたくさんのいのちが救われない。
戦後、日本人は努力し前へ進むことを善とし、立ち止まり後ろ向きになることを悪とする傾向がありました。
ポジティブ思考を良しとし、ネガティブ思考を「根暗」とからかう風潮は私の時代にもありました。
しかし五木氏は、物事の明るい面だけ見続けるだけでよかったのだろうか、と疑問を投げかけます。
人間は喜びと悲しみの両者を経験して初めて感情が完成する。片方だけでよいということはない。本当の悲しみを経験した者だけが本当の喜びを知るはずだ、と云います。
明るい面だけを見る風潮の弊害として、人間の心の闇が地下に深く広く浸透してしまった。
それがいじめであり、不登校・引きこもりであり、自殺者の増加である、と。