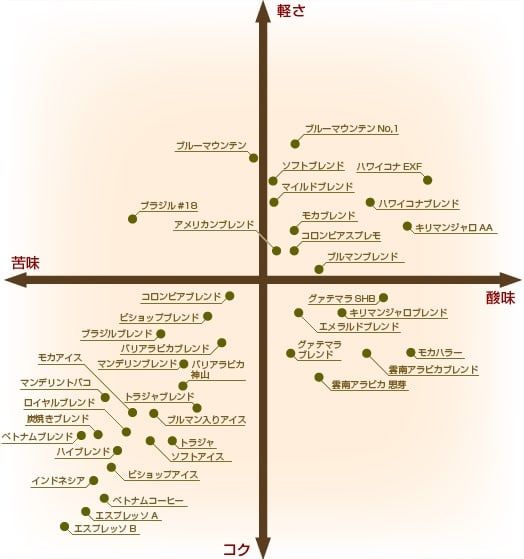珈琲豆の品種に続いて、銘柄(≒生産地)についても整理を試みました。
珈琲豆の銘柄
■ キリマンジャロ
・キリマンジャロ(アフリカ大陸最高峰の山)の麓で栽培。
・上質な酸味と珈琲の苦みのバランスがよく調和し、甘いコクと上品な香りに優れている。
・焙煎度(浅い〜深い)により様々な風味が楽しめる。
・栽培地の標高が高いほど香りがよく品質が高いとされている。
■ ブルーマウンテン
・“珈琲の王様”と称される。
・カリブ海に浮かぶ島国のジャマイカの山が名前の由来で、日本で流通しているブルーマウンテンの8割がジャマイカからの輸入。
・癖のない風味と口当たりの良さ、のどごしのバランスがとれたテイストが日本人好み。
■ ハワイコナ
・ジャマイカのブルーマウンテンと並んで世界最高の珈琲と称される。
・酸味が特徴的で、苦みが少なく甘い香りとスッキリさわやかな味わいはとても上品。
・ハワイ島南西部のコナ地区でのみ栽培されている。希少性が高く世界の珈琲生産量の1%以下(少々値が張る)。
・収穫は機械を使わず人の手で一粒一粒完熟したものだけが摘み取られる。
■ モカ
・ヨーロッパ諸国へ珈琲豆を輸出していたイエメンの港町の名前が由来。
・最も古い品種。
・独特の強い酸味と、モカ特有のフルーティーな豊かな香りが特徴で、甘みとコクを堪能できる。
・「モカ・シダモ」「モカ・ディマ」など収穫地の名前で呼ばれるが、どれも苦みより酸味が強いという味の特徴は共通している。
■ コロンビア
・生産国コロンビアは、美味しい珈琲を作るために必要な環境条件の「温度差」「降雨量」「日照量」が整っている。
・芳醇な甘み、柔らかな苦みとコクでフルーティーな味わいが特徴で、バランスのいいマイルドな珈琲。
■ マンデリン
・インドネシアのスマトラ島で生産。
・インドネシアではロブスタ種が多く生産されているが、マンデリンはアラビカ種。
・強めの苦みがコク深い。酸味が少なくほろ苦さのバランスが絶妙。
・ブレンドやカフェオレで飲まれることが多い。
■ エメラルドマウンテン
・アンデス山脈の麓に広がる地域で栽培され、栽培地はほとんど急斜面のため、機械ではなく人の手によって丁寧に作られている。
・コロンビア珈琲に分類されるが、その中でも厳選された、わずか3%未満の高級豆だけに付けられる呼称。
・甘い香りとコクに酸味と甘みがうまく調和した上品な味わい。
■ グァテマラ
・グアテマラ共和国は適度な降雨量と日照時間に恵まれ、ふかふかして耕しやすく廃水がいい火山灰土壌の性質を活かし、水はけのいい山の斜面や高原地帯での栽培が盛ん。
・甘い香りと少し強めの上品な酸味、ほどよい苦みのバランスがいい芳醇な味わいが特徴の珈琲。
■ コスタリカ
・コスタリカの気温は一年を通して低めで安定した日照量と降水量、適度な気温が保たれている地域。
・芳醇な香りとしっかりした苦み、控えめな酸味がとても上品な味わい。フルーティーでさっぱりした後味が癖になる。
■ コピ・ルアク
・世界一高価で希少な珈琲。
・インドネシア産でジャワ島やバリ島などで栽培されている。
・完熟した珈琲の実のみをジャコウネコが食べ、その排泄物から採取する豆を集め、それを洗浄し乾燥させたもの。
・独特な香りが特徴的で、珈琲特有の酸味や苦みが少なくさっぱりしていて飲みやすい味。
<参考にしたHP>
■ コーヒー豆って何種類あるの?人気の品種とおいしい飲み方をチェック(MACARONI)
それにしても、なぜ品種で呼ばれず銘柄・生産地で呼ばれるのか、不思議ですね。
それに答えてくれるHPを見つけました;
□ 品種ではなく、産地の名前で流通するコーヒー豆(通販コーヒー完全ガイド)
珈琲豆の銘柄
■ キリマンジャロ
・キリマンジャロ(アフリカ大陸最高峰の山)の麓で栽培。
・上質な酸味と珈琲の苦みのバランスがよく調和し、甘いコクと上品な香りに優れている。
・焙煎度(浅い〜深い)により様々な風味が楽しめる。
・栽培地の標高が高いほど香りがよく品質が高いとされている。
■ ブルーマウンテン
・“珈琲の王様”と称される。
・カリブ海に浮かぶ島国のジャマイカの山が名前の由来で、日本で流通しているブルーマウンテンの8割がジャマイカからの輸入。
・癖のない風味と口当たりの良さ、のどごしのバランスがとれたテイストが日本人好み。
■ ハワイコナ
・ジャマイカのブルーマウンテンと並んで世界最高の珈琲と称される。
・酸味が特徴的で、苦みが少なく甘い香りとスッキリさわやかな味わいはとても上品。
・ハワイ島南西部のコナ地区でのみ栽培されている。希少性が高く世界の珈琲生産量の1%以下(少々値が張る)。
・収穫は機械を使わず人の手で一粒一粒完熟したものだけが摘み取られる。
■ モカ
・ヨーロッパ諸国へ珈琲豆を輸出していたイエメンの港町の名前が由来。
・最も古い品種。
・独特の強い酸味と、モカ特有のフルーティーな豊かな香りが特徴で、甘みとコクを堪能できる。
・「モカ・シダモ」「モカ・ディマ」など収穫地の名前で呼ばれるが、どれも苦みより酸味が強いという味の特徴は共通している。
■ コロンビア
・生産国コロンビアは、美味しい珈琲を作るために必要な環境条件の「温度差」「降雨量」「日照量」が整っている。
・芳醇な甘み、柔らかな苦みとコクでフルーティーな味わいが特徴で、バランスのいいマイルドな珈琲。
■ マンデリン
・インドネシアのスマトラ島で生産。
・インドネシアではロブスタ種が多く生産されているが、マンデリンはアラビカ種。
・強めの苦みがコク深い。酸味が少なくほろ苦さのバランスが絶妙。
・ブレンドやカフェオレで飲まれることが多い。
■ エメラルドマウンテン
・アンデス山脈の麓に広がる地域で栽培され、栽培地はほとんど急斜面のため、機械ではなく人の手によって丁寧に作られている。
・コロンビア珈琲に分類されるが、その中でも厳選された、わずか3%未満の高級豆だけに付けられる呼称。
・甘い香りとコクに酸味と甘みがうまく調和した上品な味わい。
■ グァテマラ
・グアテマラ共和国は適度な降雨量と日照時間に恵まれ、ふかふかして耕しやすく廃水がいい火山灰土壌の性質を活かし、水はけのいい山の斜面や高原地帯での栽培が盛ん。
・甘い香りと少し強めの上品な酸味、ほどよい苦みのバランスがいい芳醇な味わいが特徴の珈琲。
■ コスタリカ
・コスタリカの気温は一年を通して低めで安定した日照量と降水量、適度な気温が保たれている地域。
・芳醇な香りとしっかりした苦み、控えめな酸味がとても上品な味わい。フルーティーでさっぱりした後味が癖になる。
■ コピ・ルアク
・世界一高価で希少な珈琲。
・インドネシア産でジャワ島やバリ島などで栽培されている。
・完熟した珈琲の実のみをジャコウネコが食べ、その排泄物から採取する豆を集め、それを洗浄し乾燥させたもの。
・独特な香りが特徴的で、珈琲特有の酸味や苦みが少なくさっぱりしていて飲みやすい味。
<参考にしたHP>
■ コーヒー豆って何種類あるの?人気の品種とおいしい飲み方をチェック(MACARONI)
それにしても、なぜ品種で呼ばれず銘柄・生産地で呼ばれるのか、不思議ですね。
それに答えてくれるHPを見つけました;
□ 品種ではなく、産地の名前で流通するコーヒー豆(通販コーヒー完全ガイド)