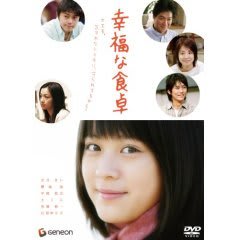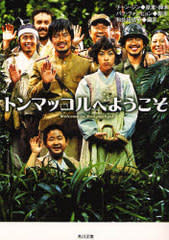映画「永遠と一日」
19世紀の詩人ソロモスについて研究している主人公アレクサンドロス(詩人)は、重病を患い、追憶に慕っている。
最愛の妻を亡くし、自分の妻と過ごしたかけがえのない海辺の家を、娘夫婦に売却される。自分の居場所さえ無くなり、大事な思い出の家を失い、余命わずかのアレクサンドロスは、孤独の中を彷徨っていた。旅に出ようと決意したが、何処へ行こうとも、新しい世界など見つけられそうもない年老いたアレクサンドロス。
そんな中、ギリシア系アルバニア人の難民の少年と出会う。家族を失い、生まれ故郷を捨てたが、海の向こうに新しい世界を夢見ることのできる少年。
2人とも居場所がないという点では共通している。
過去と現実が交錯する物語。冬の厳しい寒さと現実の閉塞感によって心を圧迫されるアレクサンドロスにとって、唯一の幸せは、妻と愛し合った夏の海辺の時間。アレクサンドロスの追憶の中で、幸せな過去のイメージが壮大に広がる。
また少年は、共に国境を超えるという命がけの旅をした親友セリムを亡くす。そして少年は、難民の仲間たちとフェリーで旅(密航)すると言う。
アレクサンドロスは少年を誘い、海辺の循環バスに乗る。コミュニストの青年、喧嘩をする恋人、弦楽科の音楽学生たち、そして詩人ソロモスが同乗する。この循環バスは、アレクサンドロスの魂の中を運転しているのだろうか。ソロモスは「人生は美しい。そう、人生は美しい」と言う。アレクサンドロスは、下車するソロモスに「明日の長さはどれくらいか」と尋ねるが答えは無い。
その後、少年は難民の子供たちと共に、フェリーで海の向こうの新しい世界へと旅立つ。
翌朝、懐かしい海辺の家で、アレクサンドロスは、昔と同じように親戚と妻アンナに再会する。アレクサンドロスがアンナに「明日の長さは?」と尋ねると、アンナは「永遠と一日」と答える。そしてアレクサンドロスはつぶやく。「詩人は死することはない。言葉で過去を連れ戻すからである。すべては真実で、真実を待っている」と。
まるで叙情詩が映画になったような作品だった。理屈ではなく、感じる映画だと思う。
ひとつひとつの言葉が美しい。ギリシアの青い海、静かに流れていく河、アルバニア国境付近の雪などの自然が作品をより美しくさせる。また、過去の光と現実の闇との対比がとても切なく感じられる。
詩人とは、自ら紡ぎ出す言葉によって時空を超え、過去や未来の人物たちと語り合うことのできる存在なのだろう。言葉はいつまでも消え去らない。
まるで永遠は一日のようで、一日は永遠のようだ。この逆説を随所に感じられた。まさにアレクサンドロスが妻アンナと過ごした至福の時間は、そういうものだったんだろうな。僕もアレクサンドロスのように、幸せな過去の壮大なイメージを忘れたくないと強く思った。
過去・現在・未来という時間の壁を打ち破った、この映画はすごい。
人間というものは、言葉を切符にして、時空を旅することができるのだろう。
だからこそ人生は美しいのかもしれない。
どれほど苦しい人生であろうとも、身近にある見えない幸せに気付くことができれば、その幸せはいつまでも人間の心に残るのだと思う。
たとえ忘れてしまうような泡沫の幸せでも、その人を形作っているんだよね。
この幸せこそが、暗い海の底に沈んだ日でも、青空を飛ぶことはできると人間に思わせてくれるんじゃないかな。
19世紀の詩人ソロモスについて研究している主人公アレクサンドロス(詩人)は、重病を患い、追憶に慕っている。
最愛の妻を亡くし、自分の妻と過ごしたかけがえのない海辺の家を、娘夫婦に売却される。自分の居場所さえ無くなり、大事な思い出の家を失い、余命わずかのアレクサンドロスは、孤独の中を彷徨っていた。旅に出ようと決意したが、何処へ行こうとも、新しい世界など見つけられそうもない年老いたアレクサンドロス。
そんな中、ギリシア系アルバニア人の難民の少年と出会う。家族を失い、生まれ故郷を捨てたが、海の向こうに新しい世界を夢見ることのできる少年。
2人とも居場所がないという点では共通している。
過去と現実が交錯する物語。冬の厳しい寒さと現実の閉塞感によって心を圧迫されるアレクサンドロスにとって、唯一の幸せは、妻と愛し合った夏の海辺の時間。アレクサンドロスの追憶の中で、幸せな過去のイメージが壮大に広がる。
また少年は、共に国境を超えるという命がけの旅をした親友セリムを亡くす。そして少年は、難民の仲間たちとフェリーで旅(密航)すると言う。
アレクサンドロスは少年を誘い、海辺の循環バスに乗る。コミュニストの青年、喧嘩をする恋人、弦楽科の音楽学生たち、そして詩人ソロモスが同乗する。この循環バスは、アレクサンドロスの魂の中を運転しているのだろうか。ソロモスは「人生は美しい。そう、人生は美しい」と言う。アレクサンドロスは、下車するソロモスに「明日の長さはどれくらいか」と尋ねるが答えは無い。
その後、少年は難民の子供たちと共に、フェリーで海の向こうの新しい世界へと旅立つ。
翌朝、懐かしい海辺の家で、アレクサンドロスは、昔と同じように親戚と妻アンナに再会する。アレクサンドロスがアンナに「明日の長さは?」と尋ねると、アンナは「永遠と一日」と答える。そしてアレクサンドロスはつぶやく。「詩人は死することはない。言葉で過去を連れ戻すからである。すべては真実で、真実を待っている」と。
まるで叙情詩が映画になったような作品だった。理屈ではなく、感じる映画だと思う。
ひとつひとつの言葉が美しい。ギリシアの青い海、静かに流れていく河、アルバニア国境付近の雪などの自然が作品をより美しくさせる。また、過去の光と現実の闇との対比がとても切なく感じられる。
詩人とは、自ら紡ぎ出す言葉によって時空を超え、過去や未来の人物たちと語り合うことのできる存在なのだろう。言葉はいつまでも消え去らない。
まるで永遠は一日のようで、一日は永遠のようだ。この逆説を随所に感じられた。まさにアレクサンドロスが妻アンナと過ごした至福の時間は、そういうものだったんだろうな。僕もアレクサンドロスのように、幸せな過去の壮大なイメージを忘れたくないと強く思った。
過去・現在・未来という時間の壁を打ち破った、この映画はすごい。
人間というものは、言葉を切符にして、時空を旅することができるのだろう。
だからこそ人生は美しいのかもしれない。
どれほど苦しい人生であろうとも、身近にある見えない幸せに気付くことができれば、その幸せはいつまでも人間の心に残るのだと思う。
たとえ忘れてしまうような泡沫の幸せでも、その人を形作っているんだよね。
この幸せこそが、暗い海の底に沈んだ日でも、青空を飛ぶことはできると人間に思わせてくれるんじゃないかな。